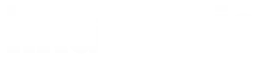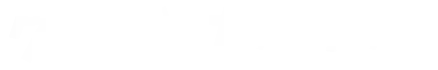梅雨の雑学まとめ。誰かに話したくなる豆知識【一般向け】
6月から7月にかけて日本に訪れる梅雨。
雨が続いてあまり好きではない、という方も多いかもしれませんね。
この記事では、そんな梅雨に関する雑学を一挙に紹介していきますね!
梅雨という名前の由来や梅雨のメカニズムのほか、この時期の植物や動物についての雑学もピックアップしました。
あまり気分が上がらない季節かもしれませんが、この記事を通して少しでも楽しんでいただければうれしいです。
知れば誰かに話したくなるようなものばかりですので、ぜひこの機会にたくさんの雑学を覚えてくださいね。
- 【一般向け】6月に関する雑学&豆知識
- おもしろい雑学のクイズ。新しい気づきに出あえる豆知識
- 雨が好きになる!梅雨に関する子供向けの雑学&豆知識クイズ
- 【子供向け】6月に関する雑学&豆知識クイズ
- 【高齢者向け】梅雨に関する雑学クイズ&豆知識問題まとめ
- 【雑学】知ってる?天気のことわざクイズ集!
- 【面白い】雑学クイズの問題まとめ
- きゅうりの豆知識クイズ。きゅうりにまつわる雑学まとめ
- もっと天気予報が楽しくなる!天気に関する雑学&豆知識
- 【一般向け】思わず誰かに話したくなる!11月の雑学&豆知識特集
- 心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ
- 知っているようで意外に知らない?8月の雑学・豆知識クイズ!
- 秋を待つ9月に関する雑学&豆知識まとめ
梅雨の雑学まとめ。誰かに話したくなる豆知識【一般向け】(21〜30)
ビニール傘は日本で生まれた
コンビニや100円ショップなど、どこでも手軽に購入できるビニール傘。
実は、日本で生まれた傘だって知っていましたか?
浅草にある老舗の傘メーカーによって開発されたのですが、初めはビニール傘ではなく、ビニールの傘カバーだったそうです。
その後、どんどん性能のいい傘が各社から登場したことによって、ビニール傘を開発。
しかし、当初日本ではなかなか売れず、ニューヨークで販売されてヒットしたことにより、やっと世界で注目を集めるようになりました。
カエルがよく鳴いていると雨が降る
雨の日の生き物といえばカタツムリ!
そしてカエルもよく見かけますよね。
実はこのカエルには言い伝えがあるんです。
それは、カエルがよく鳴いていると雨が降るというもの。
実はカエルという生き物は、皮膚呼吸しているため湿度にとても敏感。
そして湿度が高くなると鳴き始めるという習性を持っているのです!
とある大学ではこの言い伝えが研究され、やはりカエルが鳴いた場合の方が降る確率は高かったようですよ。
ただしカエルは求愛や敵が近づいた時にも鳴くので、絶対ではありません。
梅雨の雑学まとめ。誰かに話したくなる豆知識【一般向け】(31〜40)
海外の天気予報では雨を雨雲マークで表す
旅行や入学式など、大切な行事がある日は、天気予報を確認しますよね。
そのときに、雨を知らせるマークである「傘のマーク」を見たことがあるのではないでしょうか。
日本では定番のマークですが、実は海外ではほとんど傘のマークは使われないんです。
では、何のマークが使われるかというと「雨雲マーク」。
雨雲マークは、雲にしずくを合わせたようなマークです。
日本では雨の日に傘を持つ習慣がありますが、雨が降っても傘を持たない国もあるので、もしかしたらそれも関係しているのかもしれませんね。
てるてる坊主は江戸時代からあった
てるてる坊主は、浮世絵や川柳に登場することから、江戸時代からあったと言われています。
てるてる坊主の起源にはいろいろな説がありますが、中国で晴天を願って作られる掃晴娘が伝わったという説、民俗学者の柳田さんが主張している天気祭が元になっているという説が有力です。
江戸時代のてるてる坊主は「てり雛」や「てりてり坊主」と呼ばれていました。
また、紙や布で作られているのは同じですが、その姿は着物を着ていたそうですよ。
おわりに
梅雨にまつわる雑学を一挙に紹介しました。
名前の由来や仕組みはもちろん、雨に関する内容もありましたね。
知れば周りに教えたくなるような雑学ばかりだったと思いますので、この機会にぜひたくさんの雑学を覚えていってくださいね!