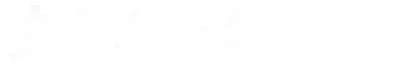【中学校】文化祭の出し物。人気の展示やゲーム、ステージ発表まとめ
中学校の文化祭で何をするか、もう決まりましたか?
教室展示やステージ発表、来場者が楽しめるアトラクションやゲームなど、出し物のアイデアはたくさんあります。
しかし「盛り上がる出し物はどれなのかわからない」「思い出に残る出し物にしたい」など、どれにするかなかなか決められないこともあるかもしれません。
そこでこの記事では、中学校の文化祭にオススメの出し物を一挙に紹介していきますね。
定番の出し物や人気の出し物をピックアップしているので、紹介する出し物を参考にして、楽しい文化祭を作ってくださいね!
- 【文化祭】出し物の人気ネタランキング
- 文化祭で盛り上がるステージイベント・出し物のアイデア
- 【文化祭・学園祭】教室でできる珍しい出し物
- 文化祭の生徒会企画にオススメのアイデア。レクやステージ企画など
- 文化祭のクラス企画のアイデア。人気の出し物まとめ
- 文化祭・学園祭で盛り上がるステージパフォーマンスのアイデア
- 【食べ物以外】文化祭の出し物。教室展示からステージイベントまで
- 縁日やバラエティ番組顔負け!?文化祭・学園祭で盛り上がるゲーム
- 【小学校】中学年の学芸会・学習発表会でおすすめの出し物アイデア
- 文化祭・学園祭で盛り上がるレクリエーションまとめ
- 【小学校向け】文化祭にオススメの出し物・レクリエーション
- 文化祭・学園祭にオススメの展示物のアイデア。上映作品も
- 【ジャンル別】文化祭・学園祭の出し物カタログ【2026】
【中学校】文化祭の出し物。人気の展示やゲーム、ステージ発表まとめ(1〜10)
クイズショー

「学校で1番知識があるのは誰だ!」白熱の対決、クイズショーはいかがでしょうか。
2チームに分かれての早押し回答していくステージイベント型のアイデアです。
スクリーンに問題を映し出し、司会者がそれを読み上げる形。
クイズ番組『全国高等学校クイズ選手権』のようなイメージですね。
問題はネットなどから拾ってきてもいいですが、せっかくなら先生たちに協力をあおいでみては。
勉強にもなるし熱くもなれる、一石二鳥な文化祭出し物ネタです!
バカッコイイ映像

日常の何気ない動作をスタイリッシュにこなす様子、その短い映像を組み合わせてひとつの作品にしたような内容です。
ゴミ箱を見ない状態でごみを投げ入れる、足を使ってリフティングのように物を片付けるなど、奇跡とも思える瞬間が繰り返される構成です。
学生の一日といった形で、とある日の行動に奇跡を重ねたような内容にするなど、ストーリーを感じられる工夫ががあるとさらに完成度の高い作品になるかもしれませんね。
こんな動きまでスタイリッシュにしなくてもいいのにといったような、思わず笑ってしまうようなツッコミをさそうポイントも取り入れておきたいですよね。
奇跡の瞬間が連続するといった映像だけで終わるのもいいですが、本編が終わったあとには、その瞬間にたどり着くまでの道のり、メイキングを流せば、努力と親しみやすさも伝えられるのではないでしょうか。
書道パフォーマンス

音楽に合わせて、手拍子やダンスをしながら書道を披露する書道パフォーマンスはいかがでしょうか?
書道パフォーマンスは、映画になったり甲子園も開かれていますよ。
大きな紙の上を、数人で大きな筆を使って文字を書いたり絵を描いていきましょう。
「一体どんな作品ができるのだろう」と見ている方もワクワクとした気持ちに。
パフォーマンスを披露する衣装も、みんなと、はかまにそろえてもいいですね。
もちろん、制服でも大丈夫ですよ。
完成したら、ずっと思い出に残るすてきな書道の作品になるのもポイントです。
【中学校】文化祭の出し物。人気の展示やゲーム、ステージ発表まとめ(11〜20)
黒板アート

教室展示のアイデアとしてオススメしたいのが、黒板アートです。
毎年春になると、入学式や卒業式の日に教室の黒板に歓迎や送別のメッセージとともに壮大なイラストを書いた黒板アートが注目を集めており、SNSなどでその様子を目にしたことがある方も多いはず。
そこでクラス展示の一環として、黒板に大きなイラストを書いてみましょう。
絵を書く工程も大切ですが、「何をどんな風に描くのか」というアイデアの部分もとても重要です。
絵を書くのが得意な人が中心となって、みんなで協力して仕上げてくださいね。
ダンス

文化祭の出し物として、ダンスは定番で欠かせない出し物ですよね!
ステージの大きさによってはクラス全員で一度に踊るのはできないかもしれませんが、グループに分かれて1曲ずつ踊るという形にしてもいいですね。
また、もし広い場所でダンスを披露できる場合には、ぜひ全員で踊れるダンスに挑戦してみてください。
ポカリスエットのCMで話題になった青ダンスや、サカナクションの『新宝島』などは参加できる人数も多いのでオススメですよ。
迷路

教室から体育館や運動場まで幅広く取り組める出し物といえば迷路です。
厚紙やダンボールで扉や壁を作り、スタートからゴールまで目指して遊びます。
行き止まりを設置したり、同じような光景で迷わせたりと作りがいがある出し物です。
クラスメイトなど大人数で作る場合は、巨大迷路を作るのもオススメ。
タイムレースをしたり、チームで競ったりとゲームとしても楽しめますよ。
ミステリアスな音楽や照明をかけることで、より迷路の世界観が深まるのではないでしょうか。
造形ワークショップ

造形あそびとは、身の回りにあるものを使って何かを作ることを指し、とくに小さい子供たちの創造力や表現力を養う取り組みです。
石や落ち葉を並べたりして何かの形や模様にしたり、ブロックを積んで何かを作ったり、好きなように絵を描いたり、その場を飾りつけたり……アイデアや工夫次第でさまざまな造形あそびがあります。
そこで、そうした造形あそびを来場者と一緒に楽しめる造形ワークショップを開いてみましょう。
みんなで一緒に取り組んだ作品は、最後にはどんな風に出来上がるのか楽しみですね。