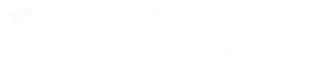密にならない室内・外遊び。1年生から6年生まで楽しめる
風邪予防やウイルス対策として、ソーシャルディスタンスを保った状態で遊べるゲームをお探しの方もおられますよね。
「なるべく会話しない」「子供同士が近づきすぎない」など、密にならない状況で遊べるものがいいでしょう。
そこでこの記事では、1年生から6年生までの小学生が楽しめるゲームを紹介していきます。
教室の中で遊べるものから室外で体を動かせるものまで幅広いテーマをピックアップしました。
低学年や高学年ごとのルールを設定して遊んでみてくださいね!
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
- 【小学校】すぐ遊べる!低学年にぴったりの室内レクリエーション
- 【小学生向け】道具なしで遊べる楽しい室内遊び
- 【子供会】簡単で楽しい室内ゲーム。盛り上がるパーティーゲーム
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 【小学校レク】お楽しみ会におすすめのゲーム・出し物
- 小学生のお楽しみ会が大盛り上がり!室内ゲームのアイデア集
- 【小学校】中学年におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 子供におすすめの野外・アウトドアのゲーム・レクリエーション
- 【子供向け】盛り上がるクラス対抗ゲーム。チーム対抗レクリエーション
- 学童保育で大活躍!道具なしでできる集団遊び&ゲームのアイデア特集
- チームワークを高められる簡単で楽しい協力ゲーム
密にならない室内・外遊び。1年生から6年生まで楽しめる(31〜40)
リコーダーでハモってみた

星野源さんがInstagramに「誰か、この動画に楽器の伴奏やコーラスやダンスを重ねてくれないかな?」とアップしたことがきっかけで『うちで踊ろう』に歌やダンス、演奏を合わせてアップする動画が広まりました。
映像を通して、家にいながら他の人と一緒に演奏しているような気分にもなれて、失敗しても気にしないで何度でも練習できますよ。
誰にでもできるので、リコーダー初心者の子供はもちろんですが、リコーダーが苦手な子供はほかの楽器で遊んでみるのもオススメ。
曲を自分の好きな曲を選んで楽しんでくださいね!
ルービックキューブ

まるでパズルの魔法のような、ルービックキューブを回して6つの面すべてをそろえる遊び。
カラフルな面がぴったり合うたびに、考える力や集中力がじっくり育ちます。
「ここまでできた!」という成功のよろこびが、自信につながりますよ。
順番や動きを覚えることで、計画を立てる力と記憶力もアップします。
友だちや家族と「時間を競ってみよう」と遊べば、協力したり応援し合う楽しさも生まれます。
まずは1面からでも、小さな挑戦をくり返して、楽しく遊んでみてくださいね!
一人でできるボール遊び

1人でできるボールの遊びを5つご紹介します!
まず1番目は「自分でボールをキックして走って足の間を通す」という遊び方です。
蹴る強さを考えるので、頭も使いますよ。
2番目は、「ボールを上にあげて腕の間を通す」遊び方。
自分の体を動かすのがポイント。
3番目は、「ボールの上にボールをのせて止める」という遊び。
4番目は「ボールを頭の上に持って、体を反らして足の間を通してキャッチ」するからだが柔らかくなる遊びです。
最後は、フラフープを使った遊びです!
フラフープを回している間にボールを移動しましょう。
どれも思い切り投げたり、蹴ったりしなくても楽しめるのでぜひ挑戦してみてくださいね。
作って遊べる!ひとり風船バレー

風船と輪ゴムを使って子供がひとりで遊べる「風船バレー」。
小学生はもちろん、小さい子供も室内で楽しめる遊びです。
例えば、風船を輪ゴムでつないで、飛んできた風船を軽くつないだり返したりすることで、力もちょうどよく調整できて、安全に遊べます。
風船のふんわりした動きを眺めたり、ゆっくり追いかけたりしながら、自然に集中力、動作のタイミングも育ちますよ。
サッカーのように足でけってみたり、ちょっとした工夫で繰り返し遊べるのがおすすめポイント。
室内での遊びにピッタリなので、ぜひ遊んでみてくださいね!
昔遊びの技

最初はむずかしく思えるけん玉やコマですが、くり返しチャレンジして成功すると「できた!」という達成感が生まれますよ。
練習している過程で、指先の細かい動きや、体のバランス、目と手のタイミングがどんどん鍛えられていくのもポイント。
集中して遊ぶことで、がんばる力やあきらめない気持ちも育ちます。
練習して、友達や家族といっしょに技を見せ合えば、お互いの「すごいね!」の言葉で勇気や自信もわいてきます。
楽しく遊びながら、心も体も大きく伸ばしてくれるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!
密にならない室内・外遊び。1年生から6年生まで楽しめる(41〜50)
身近な材料でプラバン遊び

身近なものが、実はプラバンの材料になるんです。
プラスチックにはいろいろな種類があって、どれでも使えるわけではありません。
ポリスチレンなら大丈夫。
容器についているマークをよく見て選んでくださいね。
使えるものが見つかったら、通常のプラバンと同じように絵を描いていきます。
ポリスチレンのカップは丸くつぶれるように焼けていくので、見ているのも楽しそうです。
アルミホイルはくっつくことがあるようなので注意してくださいね!
コースターにしたり、腕時計のおもちゃを作れますよ。
容器を捨てる前にぜひチェックして、遊んでみてくださいね!
ボールあて鬼ごっこ

室内でも子供達が全力で走り回れる「ボール当て鬼ごっこ」は、学童保育で大人気のアクティブゲーム。
鬼がボールを持って追いかけ、逃げる子供たちに当てるシンプルなルールながら、そのスピード感とスリルで大盛り上がり!
ボールに当たった子が次の鬼になるため、次々と展開が変わり、飽きずに楽しめます。
柔らかいボールを使えば、室内でも安心。
狭いスペースでは、ラインを決めたり小さく走るルールにすることで調整も可能。
元気いっぱいの時間を作りたい時に、ぜひ取り入れてほしいゲームです。