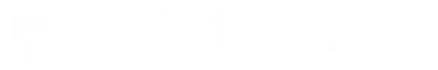夜空に輝く星の雑学&豆知識まとめ
夜空にキラキラと輝く星にはどんな意味があるのか、考えだすと気になる方も多いかと思います。
この記事では、星にまつわる雑学や豆知識を紹介していきますね。
星の大きさやかたち、輝きはそれぞれ違っているので、夜空を見上げながら星の名前を探し当てるのも楽しみの一つです。
星座や恒星、惑星などの知識が深まるとともに、まだまだ知られていない宇宙の神秘を考えるきっかけにもなります。
宇宙の歴史や星に興味のある方はぜひ最後までご覧になってくださいね。
- 知って楽しい!宇宙の雑学まとめ【レク】
- 夢とロマンにあふれた宇宙に関する雑学&豆知識まとめ
- 宇宙の雑学クイズ。太陽系の惑星や宇宙飛行士にまつわる3択問題
- おもしろい雑学のクイズ。新しい気づきに出あえる豆知識
- 【宇宙】知ってる?土星の豆知識クイズ
- 【子供向け】11月の雑学クイズ&豆知識問題。楽しく知識を深めよう!
- 【七夕クイズ】豆知識や雑学が楽しめる3択問題
- 思わず誰かに話したくなる!12月の雑学&豆知識特集
- 思わず誰かに話したくなる!1月の雑学&豆知識特集
- 地球に関する心がざわつく雑学&豆知識まとめ
- もっと天気予報が楽しくなる!天気に関する雑学&豆知識
- 花粉症にまつわる雑学。対策にもなる豆知識
- 梅雨の雑学まとめ。誰かに話したくなる豆知識
夜空に輝く星の雑学&豆知識まとめ(1〜10)
星の色は表面温度と関係している
夜空に輝く星には、白っぽいものから赤っぽいものまで、いろいろな色が存在しますよね。
その色は表面温度の違いからきていることをご存じでしょうか。
青白いものが最も温度が高く、10000度以上、最も温度の低い赤い色の星で4000度くらいだそうです。
そして温度の高い青白い星は、年齢が若く、人間でいえば子供の頃にあたります。
温度の低い赤い星は人間でいえば老人にあたり、そうなると今度は爆発を起こしてちりぢりになります。
明けの明星と宵の明星は金星のことを指す
明け方の東の空に目立って輝く星を明けの明星、夕方に西の空に目立って輝く星を宵の明星といいますが、これはどちらも金星のことを指します。
ではどうして明けの明星や、宵の明星になるのでしょうか。
金星は地球よりも太陽に近い位置にあり、ちきゅよりも内側を公転しています。
ですので太陽の反対方向である地球の夜側に現れることがないのです。
そしてルシファーは明けの明星を意味するラテン語で、光を掲げるものという意味を持つそうです。
こちらも雑学として覚えてみてください。
星は大きく分けると恒星、惑星、衛星の3種類がある
星の出ている夜空を眺めていると、キラキラと星が輝いて見えますよね。
どの星も光っているように見えますが、全部の星が自ら光っているわけではありません。
星は、大きく分けると3種類に分けられます。
自ら光っている星を恒星といい、地表はなく水素を原料にして燃えてます。
代表的な星は太陽です。
恒星の光を反射して光って見えるものを、惑星と衛星と言います。
惑星は、太陽の周りを回っている星のことで、水星から海王星の8個です。
衛星は惑星の周りを回っている星のことで、地球を回る月も衛星です。
夜空に輝く星の雑学&豆知識まとめ(11〜20)
火星が赤く見えるのは土や岩が錆びているから
火星というと赤い星というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、どうして赤いかを知っていましたか。
1976年に火星に降り立ったバイキング探査機により、火星は参加した鉄でおおわれていることがわかりました。
酸化しているということは酸素があるということで、以前は水もあったと考えられています。
こんな理由から火星に人が住めるのでは、という研究がなされているのもうなずけますよね。
ただ大きさは地球よりだいぶ小さく、半径は半分程度です。
土星には六角形の雲の模様がある
土星の模様について深く観察したことがある方は少ないかもしれません。
しかしよく見ると、土星の北極部分には六角形の雲のような模様が見えます。
これはいったい何なのでしょうか。
これが最初に発見されたのは宇宙探査機ヴォイジャー2号による観測の際でした。
一説によると大気の循環の渦がぶつかって、それが六角形を作っていると考えられていますが、仮説の域を出ません。
それにしてもこのような模様があることが不思議ですし、神秘的ですよね。
水星の1日は1年よりも長い
地球上にいると一年が一日より長いということはありえませんが、そんな常識を覆す惑星が太陽系にあるのを知っていましたか。
それは水星です。
水星は88日で公転するのに、自転するのに176日かかるのです。
地球の感覚でいうと、二年以上かけて1日が終わるといったイメージでしょうか。
昼も夜も異常に長いので、昼間の気温は320~430℃、夜の気温はマイナス160~170℃と寒暖差が激しいのです。
同じ太陽系の惑星でも個性がいろいろあっておもしろいですよね。
太陽を除いて地球から1番明るく見える星はシリウスである
地球に一番近い恒星はもちろん太陽なので、太陽が一番明るく見えるのは当然なのですが、その次に明るい星は何だと思いますか。
それはおおいぬ座にあるシリウスです。
シリウスは実際太陽の2倍の大きさがあり、地球からは8.6光年という比較的近い場所にあります。
そして興味深いことに、このシリウスは実はシリウスAと呼ばれるメインの星と、シリウスBと呼ばれる白色矮星からなる連星だったのです。
メインの星は先に寿命を終えたシリウスBに引っ張られ、軌道が揺れ動いているそうで、このことも興味深いですね。