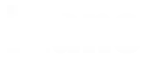【ピアノ】冬に聴きたい&弾きたいクラシックの名曲たち
厳しい寒さで外出するのが億劫になりがちな冬は、温かい室内で音楽鑑賞&ピアノ演奏を楽しんでみませんか?
今回は、冬を連想させるクラシックの名曲のなかから、ピアノ曲やピアノアレンジがすてきなオーケストラ作品などをピックアップしました。
冬の透き通った空気や美しい雪景色は、ピアノの音色にぴったり。
おうちでゆったりと聴くのもよいですが、実際にピアノ演奏にチャレンジしておうち時間を充実させるのもオススメですよ。
ご自分にピッタリの心地よい方法で、冬にちなんだクラシック作品をお楽しみください!
- 【クリスマス】ピアノで弾けたらかっこいい!名曲&定番曲をピックアップ
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 切なく美しい!おすすめのピアノ曲まとめ
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ×暗い曲】悲しみにどっぷり浸れるクラシックの名曲
【ピアノ】冬に聴きたい&弾きたいクラシックの名曲たち(11〜20)
組曲「子供の領分」第4曲「雪は踊っている」Claude Debussy

大人が子供らしい気分に浸ることを目的に作曲された、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーのピアノ組曲『子供の領分』。
第4曲『雪は踊っている』は、舞い降りてきた雪の妖精たちが地表を白いビロードで覆う様子を描いているのだそうです。
落ち着いた曲調は「妖精たちは一体何をしているんだろう?」と不思議そうに眺める子供たちの様子を表しているのかもしれませんね。
しんしんと降り積もる静かな夜に、ぼんやり窓の外を眺めながら聴いてみてはいかがでしょうか?
歌曲集「冬の旅」第1曲「おやすみ」S.561 R.246Schubert=Liszt

フランツ・シューベルトが亡くなる1年前に作曲した連作歌曲集『冬の旅』。
リストがピアノ独奏用に編曲しました。
失恋した若者が冬の夜に故郷を去る様子が描かれており、静かでメランコリックな雰囲気が漂います。
シューベルトの美しい旋律をそのままに、リストならではのピアノ技巧が加わり、より深みのある作品に仕上がっていますよ。
ピアノの音色だけで、降り続く雪の静けさや冷たさ、そして主人公の絶望感が見事に表現されています。
冬の夜、窓の外を眺めながら聴いてみてはいかがしょうか?
「四季」-12の性格的描写 12月「クリスマス」Pyotr Tchaikovsky

ロシアの作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーが、母国の1年の風物を12のピアノ曲で描いた『「四季」-12の性格的描写』。
12月『クリスマス』では、弾むようなワルツのリズムにのせて温かみあふれるクリスマスの様子が描かれています。
この曲を聴けば、クリスマス当日はもちろん、プレゼントを考えたりクリスマスツリーを飾り付けたりケーキを作ったりといった準備もより一層楽しくなるはず!
寒さの厳しい冬に、温かくほっこりとした気持ちにさせてくれる1曲です。
くるみ割り人形より「トレパーク」Pyotr Tchaikovsky

ピョートル・チャイコフスキーによるバレエ『くるみ割り人形』の第2幕に登場するロシア舞曲は、1892年3月の組曲初演でアンコールされるほど熱狂的に迎えられた一曲です。
2分の4拍子で畳みかけるような疾走感と、コサック風の力強いリズムが特徴的で、ディズニー映画『ファンタジア』やゲーム音楽にも使われ、幅広い世代に親しまれています。
短いながらも豪快なエネルギーを放つ本作は、パーティーで盛り上がりたいときや、クリスマスの高揚感を表現したいときにぴったり。
ピアノで弾けば、オーケストラとはまた違った躍動感と華やかさを楽しめますよ!
前奏曲集 第1巻より第6曲「雪の上の足跡」Claude Debussy

冬の静寂を表現した名曲、クロード・ドビュッシーの代表作。
1909年12月に完成したこの曲は、ピアノの音色が雪の上の足跡を思わせる繊細な表現力に満ちており、印象派音楽の魅力が詰まっています。
雪の冷たさや孤独感、そして心の揺れまでもが、繰り返されるリズムや和音の揺らぎによって見事に描かれています。
ドビュッシーの革新的な手法が光る本作は、冬の情景に思いを馳せたい方や、静かな時間を過ごしたい方にオススメ。
ゆったりとした気分で聴くことで、雪景色のなかを歩むような感覚が味わえるでしょう。
超絶技巧練習曲 S.139 第12番「雪あらし」Franz Liszt

卓越した演奏技術を要するピアノの魔術師フランツ・リスト作曲の『超絶技巧練習曲 S.139』。
その中でも最高峰の難易度を誇るとされているのが、第12曲『雪あらし』です。
静かに降り続けていた雪がだんだん勢いを増し、辺り一面真っ白の猛吹雪に!
超絶技巧で奏でられる高速の連符が、予測できない自然の猛威を感じさせます。
『雪あらし』をはじめ、リストの練習曲はとにかく難易度の高い作品ばかり!
おうち時間が増える冬場に、じっくりピアノでさらってみるのもよいかもしれませんね。
【ピアノ】冬に聴きたい&弾きたいクラシックの名曲たち(21〜30)
子守唄 変ニ長調 作品57Frederic Chopin

冬の静寂と美しさを感じさせるショパンの名作。
1844年に作曲された本作は、繊細な子守唄の旋律に基づく16の短い変奏から構成されています。
ノアンにあるジョルジュ・サンドの別荘で過ごした静穏な環境が、ショパンの創作意欲を刺激したのでしょう。
優美な雰囲気が特徴的で、繰り返されるベースラインの上に装飾的な旋律が重ねられ、聴く人を包み込むような温かさが感じられます。
技術的にも高度な本作は、ピアニストにとってもよいレパートリーに。
静かな冬の夜に、ぜひ寝る前に聴いてみてくださいね。