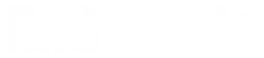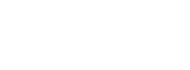障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ
運動会の定番競技の一つである障害物競走。
スタートからゴールまでの間にさまざまな障害物が用意されており、それらを乗り越えながら1位を目指すレースですね。
どんな障害物を用意するかは、障害物競走をおこなう上で競技の難易度や盛り上がり度を大きく左右します。
そこでこの記事では、障害物競走に取り入れたい障害物のアイデアを一挙に紹介します。
足の速さだけでなく、器用さや運が必要な障害物もたくさん取り上げました。
みんなで楽しめる障害物競走になるよう、ぜひ参考にしてくださいね!
障害物競走にオススメの障害物アイデアまとめ(1〜10)
ホッピング

バランスを取りながらばねを弾ませるホッピングは、1950年代や1980年代など、度々ブームがやってくる定番のおもちゃですね。
そんなホッピングを競走に取り入れて、それぞれのバランス感覚と試していきましょう。
おもちゃとして楽しむ場合はその場で弾ませるのが多いですが、障害物競走に取り入れる場合は、前に移動する要素によってより繊細なコントロールが要求されますね。
前に進もうとする焦りが高まるほどに、バランスも崩れやすいので、まずは落ち着いて弾ませることが重要ですね。
トンネルくぐり

白熱する運動会の障害物競走にぴったりな、トンネルくぐり。
ダンボールやイスを使ってトンネルをつくり、四つんばいになってくぐってもらう競技です。
コース上にトンネルを配置して、誰が速くくぐり抜けられるか、競いましょう。
トンネルくぐりに挑戦する方も、応援する側も一緒に盛り上がれる競技です。
トンネルの広さや暗さにも注意して、制作してみてくださいね。
けん玉

日本の伝統的なおもちゃであるけん玉は、遊んだことがあるという人も多いかと思います。
そんなけん玉の初歩ともいれるお皿に乗せる動きを、障害物競走に取り入れてみようという内容です。
その場で挑戦してお皿に乗せればクリアという形でもいいですし、得意な人が集まっていた場合には、横の大皿と持ち手の端っこの中皿に交互に乗せながら走ってもらうパターンもオススメですよ。
急いでクリアしようと焦るほどに、バランスも崩れてしまうので、目の前のけん玉にしっかりと集中して挑みましょう。
ボールはさみ

早く走りたいのに走れないもどかしさを演出してくれるのが、ボールはさみです。
こちらはゴム製のボールを足に挟んでむというもの。
足を動かすと次第にボールが後ろ側へずれていき、落ちてしまいます。
リレー形式の場合は、このボールを次の走者に足で渡すという風にしてみるのもいいでしょう。
ただし、ボールをはさんでいる間は他の障害物に挑戦できないと思うので、その辺りは工夫してみてくださいね。
ちなみにボールは硬い物だと足がいたくなるので注意です。
段ボールキャタピラ

段ボールキャタピラは、その名の通り輪っか状にした段ボールの中に人が入り、キャタピラのように前へ進んでいく競技です。
よつんばいの体勢が意外とキツく、高校生や大人の方にとっては難易度が高い競技になるかもしれません。
「よつんばいの体勢と進む」と聞くと、ハイハイのように手を交互に前に出しながら進むのをイメージしますが、雑巾がけのように手は動かさずに進んでいくのが速く進むコツですよ。
とはいえ急ぎすぎればコケてしまいますし、意外と真っすぐ進むのが難しいというのもこの競技のおもしろいところです。
網くぐり

障害物競走といえば網くぐりのシーンを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
網くぐりは地面に置かれた網の下をはうようにしてくぐり抜ける障害物です。
幼稚園児たちよりも中学生や高校生など、体が大きい選手の方が難しく感じるかもしれませんね。
ただ単に地面に網を置いただけでは簡単にくぐり抜けられるので、係員が両サイドから網を引っ張れば難易度が上がりますよ。
定番の障害物ですから、コースの序盤に設置するのがオススメです。
フラフープ

幼稚園や小学校では、フラフープを使って遊ぶことも多いのではないでしょうか?
そこで、障害物競走にフラフープを取り入れてみましょう。
「◯秒間落とさずに回せたらクリア」「◯回転できたらクリア」のように、独自にルールを設定してみるといいでしょう。
ルールは、競技参加者の年齢や人数に合わせて調整してくださいね。
また、どうしてもフラフープが回せない方のために何か代わりの障害物を用意しておくこともオススメですよ。