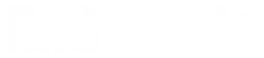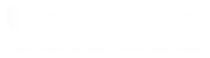小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
5年生の自主学習と言われると、何をしてよいか迷ってしまうこともありますよね。
まずは、自分が興味を持っていることを見つけてみましょう。
好きなことを学ぶと、楽しく続けられますよ。
こちらでは、毎日少しずつ学ぶことで、驚くような発見ができる簡単な自主学習のネタを集めてみました。
資料や本、動画など、いろんな方法を使ってみてくださいね。
友達や家族と一緒に学ぶと、より楽しめますよ。
学ぶことで新しい世界が広がって、新しい発見を生み出してくれることもあります。
今までの興味をいかして、楽しい自主学習に取り組んでみてくださいね。
小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集(81〜90)
プログラミング

2020年から小学校の必修となった「プログラミング」を、自由研究にしてみるのはいかがでしょうか?
プログラミングといえば命令文となる専用のコードを覚えたり難しそうに感じますが、子供でも簡単に勉強できるフリーソフトもあるんです。
たとえば教材としても人気の『Scratch』。
こちらは無料で使えますし、コードを打ち込む必要がないのでタイピングが苦手でも大丈夫。
「イベント」「動き」などのカテゴリーから、コードの代わりとなるブロックを選び積み重ねるだけでプログラミングができてしまうんです!
中学生なら「Scratch」でプログラミングしたあと、実際にはどんなコードを使うのか調べてまとめてみてもいいかもしれないですね。
ペットボトルロケット

自由研究の定番の1つであるペットボトルロケットもオススメです。
作る工程は勿論、飛ばす際も迫力があって楽しいんですよね。
ちなみにペットボトルロケットは工作用のキットが販売されているので、手軽に制作できますよ。
完成したあとは「どうしたらもっと遠くへ飛ばせるかな」と工夫しながら考えてみてください。
自由に発想して工夫できるのもペットボトルロケットの魅力です。
入れる水を炭酸水に変えるなど、さまざまな方法を試してみてください。
ペンデュラムウェーブ

小学校5年生の理科では振り子の運動について学ぶので、その特性を応用し、ペンデュラムウェーブを作ってみましょう。
ペンデュラムウェーブとは、周期が異なる複数の振り子が一定時間後にその周期が一致する現象のことを言います。
周期というのは振り子が一往復する時間のことで、周期が異なる振り子を同時に動かせば最初はバラバラに動くのですが、うまく調整すればそれぞれの周期が一定時間後にそろうのです。
どうすれば振り子の周期を調整できるのかを考えながらペンデュラムウェーブを作り、その条件をレポートにまとめてみるとよいでしょう。
ミョウバンの結晶作り

1リットルの水に対してどれだけの塩やミョウバンが溶けるのか、水の温度を変えるとそれぞれが溶ける量は変わるのかなど、物の溶け方について5年生の理科で習います。
それに関連した自由研究として、ミョウバンの結晶を作るのはいかがでしょうか?
ミョウバンを溶かしたお湯にモールを浸してそのまま冷めるまで放置すると、モールの周りに結晶ができます。
これを何度も繰り返すと大きなミョウバンの結晶ができるんです。
結晶ができたら、なぜ結晶ができるのかについて考察したり調べたりして、それをレポートにまとめると立派な自由研究の完成です。
メダカの走流性を調べる

魚のたんじょうについても5年生で習う内容ですよね。
そこで、それに関連してメダカの性質である走流性について調べてみましょう。
走流性とは、水の流れに対して一定の運動をする性質のことで、メダカの場合は水の流れに逆らって動くんですよね。
実験方法はメダカが泳いでいる水槽の中を優しく円を描くようにかき混ぜて水流を作り、メダカどのように泳ぐかを観察します。
またこれに関連して、メダカが泳いでいる水槽の周りをしま模様の紙で覆い、それを回すとメダカどのように泳ぐのかも観察すると興味深いレポートが完成するでしょう。