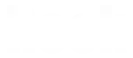ビジュアル系文学ロックバンド、Plastic Treeの魅力
皆さんはビジュアル系と聞くとどんなイメージを持ちますか?
派手、激しい、化粧がすごい、ゴールデンボンバーみたいな……そのように捉えてる人が大半でしょう。
少し音楽に詳しい人ならヘビーメタルのような楽曲をイメージするかもしれません。
ところで、みなさんはPlastic Treeというバンドをご存じでしょうか?
彼らはそんなビジュアル系の印象を覆すバンドです。
この記事ではそんな彼らについて書いていこうと思います。
Plastic Tree(プラスティック トゥリー)とは?
Plastic Treeは1993年に千葉県市川市で結成された四人組のロックバンドで幾度化のメンバーチェンジを繰り返し、現メンバーは
- 有村竜太朗(ありむら りゅうたろう):ボーカル & ギター
- 長谷川正(はせがわ ただし):ベース兼リーダー
- ナカヤマアキラ:ギター、プログラミング
- 佐藤ケンケン:ドラム、2009年正式加入
の4人です。
歴史はかなり長く、1993年に結成され1997年にメジャーデビュー、今年でメジャーデビュー20周年を迎えます。
メンバーの交代はあっても一度も活動休止を挟まず精力的に活動し続け、ロック・イン・ジャパン・フェスティバルのような非ビジュアル系の多いフェスにも出演するなどジャンルにとらわれない活動スタイルも魅力の1つです。
最近ではボーカルの有村竜太朗がソロ活動を始めたりするなど個人での活動もよく行っており、ギターのナカヤマアキラはCoaltar of the Deepersのサポートにも参加するなど特に活発なバンド外活動を行っています。
音楽性
ビジュアル系というジャンルはその成立の過程上、パンクやヘビーメタルの影響がかなり強いジャンルで、Plastic Treeもその例にもれず、パンクとヘビーメタルをルーツの1つにしています。
ただ、彼らが主に影響を受けたのはThe CureのようなゴシックなUKロックでも有るため、初期はどことなく陰鬱で繊細感がありましたが、2002年のアルバム「トロイメライ」以降、Coaltar of the DeepersのNARASAKIがプロデュースを担当したことや、ギターのナカヤマアキラ作曲の作品が増えることで、音楽性がかなりロック寄りになりました。
それに伴い、有村竜太朗の描く世界も徐々に現実感を帯びたものに変化していきます。
これらの要素が総合され、楽器隊の激しさと現実感を持つ繊細な歌詞とが同居した独特な音楽性と世界観を持つことが特徴です。
そして彼らにはほかのビジュアル系とは明確に違う特徴がありますが、次で記述します。
他のビジュアル系と違うところ
Plastic Treeはほかのビジュアル系とは異なるところが存在します。
それは先程述べた音楽性と現実感です。
先程も音楽性については列挙しましたが、彼らは他にもグランジ・ロックやオルタナティブ・ロック、さらにシューゲイザーを取り込んで表現しています。
そのため、ビジュアル系的な音作りというよりは純粋に非ヘビーメタルのUKロックとしての音作りやシューゲイザー直系のノイズの表現など、普通ビジュアル系ではやらないような作品が多く存在します。
また、ヘビーメタル的なザクザクとした刻みやテクニカルなギターソロだけではなく、Coaltar of the Deepersのようなカッティング主体のギターリフも多く見られるなど、イメージに反してかなりビジュアル系のフォーマットとは違うように思えます。
もう1つの特徴は現実感です。
ビジュアル系というのはやはりルーツがポジパンだったりニューロマンティックがあったりするため、歌詞はかなり抽象的な内面世界や感情だけに目を向けた内省的なもの、逆にとてつもなくきらびやかなものなどとにかく現実感の欠如という特徴があげられると思います。
しかし、このバンドは、同じ内面表現でもより現実に根ざした未練や後悔、はたまた日常の小さな喜びなど、おおよそビジュアル系の歌詞には似つかわしくない現実感を帯びた歌詞が多いです。
さらに、歌詞に千葉やプラットホームなど具体的な地名や物の名前を登場させることもあるため、より現実味を帯びていたりもします。
非常に文学的な歌詞の表現ですが、その中身は普通のビジュアル系バンドとは異なる現実的なものため、後続のバンドへの影響に関しては非ビジュアル系のバンドへ与えたものが大きいように思います。
私小説的な文学性を帯びた歌詞をヘビーメタル由来の激しさのあるロックに載せて表現した邦楽のバンドの走りなのではないかと思うくらいです。
そんな、Plastic Treeというバンドの特異性を認識していただいたところで、おすすめの曲を紹介したいと思います。
なお、作詞作曲の名義は今のバンドメンバーの表記に習ってすべてフルネームで統一させていただくのでご了承ください。
おすすめの曲
Sink(作詞:有村竜太朗、作曲:長谷川正)
1999年リリースで彼らのシングルの中でももっとも売上枚数の多い楽曲です。
初期のPlastic Treeらしい、耽美(たんび)さとポップさに満ちた楽曲とキャッチーなサビが印象的です。
テレビアニメ「金田一少年の事件簿」のエンディングテーマにも起用されました。
プラットホーム(作詞:有村竜太朗、作曲:ナカヤマアキラ)
2002年のアルバム「トロイメライ」収録のナンバーです。
この時期、Coaltar of the Deepersのサポートを始めたナカヤマアキラの影響が如実に出たのか、ギターリフや楽曲構成がかなり似ています。
しかもCoaltar of the DeepersのNARASAKIが編曲とギターを担当したこともあり、当時は「プラをディーパーズにするな」という批判もあったそうです。
楽曲自体は非常に疾走感がある上、終盤のギターが畳み掛けるように速弾きを重ねるところはとても格好いいです。
春咲センチメンタル(作詞作曲:有村竜太朗)
2004年に発売されたシングル曲です。
桜を見ると別れた君を思い出すという趣旨の歌詞がピアノとバンドサウンドの絡みに乗せられて、非常に繊細感の強い楽曲に仕上がり、有村竜太朗の声と世界観を十二分に表現しています。
有村竜太朗が作詞作曲をすると疾走感よりも叙情性と詩的表現を聴かせるような楽曲に仕上がるのが特徴で、初めて聴く人がバンドの顔としてイメージしやすい楽曲ができ上がることが多いです。
ザザ降り、ザザ鳴り(作詞作曲:有村竜太朗)
こちらも作詞作曲は有村竜太朗です。
2007年のアルバム「ネガとポジ」に収録されています。
タイトルの通り、雨が似合う楽曲でありその要素は歌詞よりも、グランジのようなヘビーメタルとは違うディストーションサウンドに理由があるかもしれません。
テクニカルな要素はないのですが、純粋にリフの良さも感じられるという楽曲であるため、ファンからの人気曲の1つでもあります。
梟(作詞:有村竜太朗、作曲:有村竜太朗、長谷川正)
2009年のアルバム「ドナドナ」に収録された楽曲です。
非常に疾走感のあるカッティングと、別れを感じさせる歌詞の切なさがマッチしていてロック的なキメとキャッチーさを感じる楽曲です。
個人的にはサビ前のギターのフレーズが大好きで、一種のキメのように思っています。
くちづけ(作詞:有村竜太朗、長谷川正、作曲:長谷川正)
2012年のアルバム「インク」に収録された楽曲です。
ピアノとアルペジオのフレーズから始まり、禁じられた恋を切なさたっぷりに文学的に装飾した歌詞との相性が抜群です。
この曲にどこかポストロック的な要素を感じるあたり、ビジュアル系のセオリーからはかなり外れているバンドであることが伺えるかと思います。
ギターもベースもドラムもヘビーメタル的な刻むような細かいフレーズはないのですが、最小限のバンドサウンドを巧みに構築することで一個の楽曲としてまとまりを持たせることができるあたりに、このバンドのすごさとキャリアの重みを感じます。
マイム(作詞:有村竜太朗、作曲:長谷川正)
2015年のアルバム「剥製」に収録されたナンバーです。
ミニマル・ミュージックのようにフレーズを繰り返す楽器隊とデジタルサウンドの大胆な使用がPlastic Treeの新章を感じさせる楽曲です。
おそらく、初期の彼らならまず書かないような曲だったと思います。
繰り返される曲調がまるでダンス・ミュージックのように心地よく、ライブでも即効性があり盛り上がることのできる楽曲です。
Plastic Treeの楽曲はどれも一般的なイメージのビジュアル系とはかなり違っていて、そちらの方面にあまりなじみのない方でも入り込めるものが多いと思います。
特に日本語を多用した文学的な歌詞が好きな方はぜひ、聴いてみてくださいね!