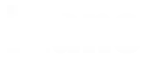ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介
ピアノへの造詣が深い方は、ある程度のピアノへの知識や技術が身についてくると難易度の高い楽曲を好んで聴くような時期があると思います。
さまざまなジャンルがあるなかで、クラシックとジャズピアノは特に難易度の高い作品が多く、長年にわたって多くの弾き手にとって壁として君臨しています。
今回はそんなピアノの難しい曲をピックアップしました。
速弾きを重視したジャズピアノから、音階の飛びが激しいクラシック、さらにはその両方の特徴を持つ現代クラシックまで、幅広いジャンルからチョイスしているので、ぜひチェックしてみてください。
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【最高難度】ピアノの魔術師・リストが手掛けた難しい曲を厳選
- かっこいいジャズピアノ。定番の人気曲から隠れた名曲まで
- 【2026】ジャズピアノの名曲。定番曲から近年の人気曲まで紹介
- 【超上級】上級者でも難しい!難易度の高いピアノ曲を厳選
- ピアノの難しい曲|プロでも弾けない!?超絶技巧を要するクラシック
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ワルツの名曲】ピアノのために書かれたクラシック作品を一挙紹介!
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【中級者】オススメのピアノ連弾曲|かっこいい&華やかな作品を厳選
- 【高難度】ピアノの詩人ショパンの難しいピアノ曲を一挙紹介!
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介(11〜20)
ピアノ協奏曲第2番セルゲイ・プロコフィエフ

20世紀を代表する偉大なロシアの作曲家、セルゲイ・プロコフィエフ。
近代音楽をたしなんでいる方なら誰でも知っている作曲家ですね。
いくつもの名曲を残してきているセルゲイ・プロコフィエフですが、こちらの『ピアノ協奏曲第2番』は特に難易度が高い作品として知られています。
基本的にセルゲイ・プロコフィエフは難易度が高いことで知られているのですが、この作品はそれが特に顕著で、ピアノ・ソロの場面も多いため、弾き手にとっては緊張することでしょう。
鍵盤の飛び、指の回り。
持久力。
全ての要素が高い次元で求められる偉大な作品です。
さすらい人幻想曲フランツ・シューベルト

ロマン派音楽を代表する偉大な作曲家、フランツ・シューベルト。
偉大な作曲家の多くが幼い頃から楽器の才能に恵まれていることが多いのですが、シューベルトは決して技巧派とは言えない実力でした。
そんな彼でも技巧派な作品を作っているのですが、そのなかでも特に有名な作品がこちらの『さすらい人幻想曲』。
この作品は作曲したシューベルトでも弾くのが難しかったらしく、よく「こんな曲、悪魔に弾かせてしまえ」と愚痴をこぼしていたそうです。
夜のガスパールモーリス・ラヴェル

近代のクラシックに絶大な影響を与えたフランスの偉大な作曲家、モーリス・ラヴェル。
フランスを代表する作曲家は芸術性の高い繊細なサウンドを得意としている傾向がありますが、ラヴェルもまたその1人で、他の作曲家には見受けられない圧倒的な個性と芸術性を秘めています。
そんなラヴェルの作品のなかで、難しいと言われている作品が、こちらの『夜のガスパール』。
全曲を合わせると相当な難しさで、芸術性を維持したまま、弾きこなせるのは一部の上級者だけです。
ピアノのための練習曲集第2巻より第13番「悪魔の階段」リゲティ・ジェルジュ

ルーマニア出身の作曲家、リゲティ・ジェルジュ。
今回、紹介している作曲家のなかで最も最近の作曲家で、現代クラシックにおいて大きな影響を残しました。
彼の音楽は実験的で、なかでも練習曲に関してはピアノという楽器の限界を求めるかのように、さまざまな挑戦が繰り返されました。
そんな彼の作品のなかで、特にオススメしたい難しい作品が、こちらの『ピアノのための練習曲集第2巻より第13番「悪魔の階段」』。
音階の上がり下がりが非常に多いだけでなく、その状態を5分以上続けなければならないという、ピアニスト泣かせな1曲です。
半音階的大ギャロップフランツ・リスト

ハンガリーを代表する作曲家、フランツ・リスト。
難しいピアノ曲を作った作曲家といえば、まずフランツ・リストをイメージする方は非常に多いと思います。
ピアニストとしても活躍を続けてきたからこそ、いくつもの難易度の高い楽曲を残してきました。
そんなリストの作品のなかでも、特にオススメしたい難しいピアノ曲が、こちらの『半音階的大ギャロップ』。
上行半音階と和音が入り乱れる作品で、とにかく指の回りが重視されます。
革命のエチュードフレデリック・ショパン

ショパンというと技巧的な作品というよりも芸術性の高い作品をイメージする方が多いと思います。
もちろん、芸術性の高さはどの作品もピカイチなのですが、なかには技巧に重きを置いた作品が存在します。
そのなかでも特にオススメしたい楽曲が、こちらの『革命のエチュード』。
圧倒的な技巧と芸術性を両立させた作品で、指の回りが特に重要視されます。
序盤から激しい打鍵が続くので、ある程度の持久力も求められるでしょう。
ぜひチェックしてみてください。
ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介(21〜30)
「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ S.434Franz Liszt

1851年にローマで初演されたヴェルディのオペラ、『リゴレット』。
こちらの『「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ S.434』は劇中の1曲です。
クラシックを知らない層にとってはマイナーな部類にあたりますが、クラシック愛好家からは高難易度かつ至高のオペラ作品として有名ですね。
非常に繊細なタッチが求められる作品で、指の力加減がうまい演奏家でなければ、音が固くなってしまいます。
演奏家によって雰囲気が変わる作品なので、ぜひ聴き比べながらこの曲を味わってみてください。