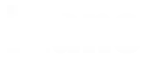ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介
ピアノへの造詣が深い方は、ある程度のピアノへの知識や技術が身についてくると難易度の高い楽曲を好んで聴くような時期があると思います。
さまざまなジャンルがあるなかで、クラシックとジャズピアノは特に難易度の高い作品が多く、長年にわたって多くの弾き手にとって壁として君臨しています。
今回はそんなピアノの難しい曲をピックアップしました。
速弾きを重視したジャズピアノから、音階の飛びが激しいクラシック、さらにはその両方の特徴を持つ現代クラシックまで、幅広いジャンルからチョイスしているので、ぜひチェックしてみてください。
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【最高難度】ピアノの魔術師・リストが手掛けた難しい曲を厳選
- かっこいいジャズピアノ。定番の人気曲から隠れた名曲まで
- 【2026】ジャズピアノの名曲。定番曲から近年の人気曲まで紹介
- 【超上級】上級者でも難しい!難易度の高いピアノ曲を厳選
- ピアノの難しい曲|プロでも弾けない!?超絶技巧を要するクラシック
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ワルツの名曲】ピアノのために書かれたクラシック作品を一挙紹介!
- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【中級者】オススメのピアノ連弾曲|かっこいい&華やかな作品を厳選
- 【高難度】ピアノの詩人ショパンの難しいピアノ曲を一挙紹介!
- 【ピアノの名曲】聴きたい&弾きたい!あこがれのクラシック作品たち
ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介(41〜50)
夜のガスパール 第3曲「スカルボ」Maurice Ravel

ラヴェルの作品のなかでも、屈指の難易度をほこると言われている作品『夜のガスパール 第3曲「スカルボ」』。
前衛的な表現を作り上げたラヴェルですが、本作でもその個性はいかんなく発揮されており、速いパッセージや難しいオクターブが連発するなかで、細かい表現を達成しなければなりません。
単純な難易度だけなら他の高難易度の曲に劣ることもあるものの、弾くのに精いっぱいの状態であれば、細かい表現を演出していくのは相当難しいといわざるをえません。
表現力に自信のある方は、ぜひ取り組んでみてください。
ピアノの難しい曲|クラシックからジャズピアノまで紹介(51〜60)
水の戯れMaurice Ravel

独創的な音楽性でいくつもの名曲を生み出してきた偉大な作曲家、モーリス・ラヴェル。
こちらの『水の戯れ』はそんなラヴェルの作品のなかでも、特に有名な1曲です。
左手の8分音符と右手の16分音符から始まるこの楽曲は、控えめな構成でありながらも芯のある音を出さなければならないため、相当な表現力が求められます。
4小節目や同じ音型で2オクターブ上がる部分など、地味に弾きづらいところが多いのですが、その分、しっかりと聴き映えする楽曲でもあります。
8つの演奏会用練習曲 Op.40 第1曲「プレリュード」Nikolai Kapustin

ウクライナ出身のロシアの作曲家ニコライ・カープスチンさんによる明るくエネルギッシュな曲調が特徴のこの曲。
リズミカルで、ジャズのスウィング感とクラシックの精密さが見事に融合していて、聴いていて思わず体が動きだしてしまいそうです。
ピアノ1台でまるでジャズコンボが演奏しているような錯覚を覚えるかもしれません。
演奏者にとっては高度なテクニックが必要で、挑戦しがいのある1曲。
しかし、聴く側にとっては軽快で楽しい曲なんです。
クラシックとジャズ、両方のジャンルが好きな方にぜひ聴いてほしい1曲ですね。
8つの演奏会用練習曲 Op.40 第3曲「トッカティーナ」Nikolai Kapustin

ハイセンスな音楽性で多くのファンに愛された偉大な作曲家、ニコライ・カプースチン。
彼の作品のなかでも特に難曲としてオススメしたいのが、こちらの『8つの演奏会用練習曲 Op.40 第3曲「トッカティーナ」』。
非常に有名な作品ですね。
本作はジャズテイストに仕上げられた作品なのですが、プレリュードがとにかく難しい!
単純な難しさで言えば他にも難しい楽曲はいくつも存在しますが、本作の高い演奏効果を発揮しながら演奏するには、相当な実力が求められます。
クライスレリアーナ Op.16 第7曲Robert Schumann

非常に情熱的で劇的な表現が特徴的なこの曲。
急速なテンポとハ短調の調性が融合し、聴く者の心をつかみます。
約2分30秒の短い演奏時間ながら、ロベルト・シューマンの内面的な葛藤や情熱が凝縮されています。
激しいアクセントを持つアルペッジョの繰り返しが緊張感を高め、中間部のフガートとの対比が印象的です。
1838年に作曲された本作は、シューマンがクララ・ヴィークとの結婚に反対され苦悩していた時期の作品。
ロマン派音楽の特徴である感情表現の豊かさが存分に発揮されており、ピアノ演奏の技術と表現力が試される1曲です。
クラシック音楽の深い感動を味わいたい方におすすめの名曲です。
トッカータ ハ長調 Op.7Robert Schumann

シューマンの難曲として名高い作品、『トッカータ ハ長調 Op.7』。
「トッカータ」は日本語で「触れる」といった意味で、シューマンは演奏家の指ならしをかねた即興曲として作ったようです。
しかしこの作品、指ならしといっても決して簡単な曲ではありません。
むしろ、シューマンの作品のなかでもトップクラスの難易度をほこります。
高い演奏効果を追い求めた結果、難所が非常に多く、第1主題も第2主題も高度なテクニックを求められる仕上がりとなっています。
12の超絶技巧練習曲 Op.11 第10番「レズギンカ」Sergey Lyapunov,

セルゲイ・リャプノフの名作『12の超絶技巧練習曲』。
この作品はフランツ・リストの名作『超絶技巧練習曲』に対抗して、彼が使用しなかった12の調を使って作曲されました。
対抗しているのは調だけではなく、演奏もリストのものと肩を並べる圧倒的な難易度をほこります。
その中でも特にオススメしたいのが、こちらの『12の超絶技巧練習曲 Op.11 第10番「レズギンカ」』。
舞踊音楽をベースとしており、鍵盤を非常に強くたたき続けるハードな演奏が特徴です。
難易度のベクトルとしては『鬼火』に近い感じですね。