AI レビュー検索
井上靖 の検索結果(81〜90)
あせってはいけません。ただ、牛のように、図々しく進んで行くのが大事です。夏目漱石

『吾輩は猫である』、『坊っちゃん』、『こゝろ』など、数多くの名作を残した小説家、夏目漱石さん。
千円紙幣の肖像にもなった事があるので、日本人ならまず知っているでしょう。
彼の作品は、教科書にも多数掲載されています。
こちらは、夏目漱石さんが芥川龍之介さんへ送った手紙に記されていた言葉です。
誰に何を言われようとも、自分が信じる道をただひたすらに突き進む。
簡単なようで難しい事ですが、勇気が出る言葉ですよね。
才能とは、 情熱を持続させる能力のこと宮崎駿
スタジオジブリの代表として知られる宮崎駿さん、生み出してきた作品の数々は日本のアニメーションに大きな影響を与えてきました。
そんなアニメーションの歴史に名を刻んだ人物が語りかける、才能とは何かについての考え方を表現した名言です。
情熱を持続させることこそが才能、成果が出るまでやりきった人が周りから評価されるのだということを力強く伝えていますね。
情熱を長く持つことが困難だからこそそれが才能に感じられる、誰にでも才能は眠っているのだということも思わせてくれる言葉ですね。
困難は私を鍛えてくれる最高の試練である高市早苗
これまでの経歴の中で逆風や批判を受けてきた高市さんだからこそ語れる、前を向いて進む意志を感じさせる言葉です。
注目度が高いからこそ困難も多く、普通ならくじけそうな状況ですが、そのうえで前に進んできたことが強さになったのだと肯定的に表現しています。
あきらめずに進み続けていくこと、どんな状況でも信念を持ち続けている点も、安心や信頼を感じるポイントですよね。
困難に直面するほどに鍛えられるということで、どこまで力が蓄えられていくのか、今後の状況も期待されます。
千日の稽古をもって鍛となし、万日の稽古をもって錬となす宮本武蔵
二刀流「二天一流兵法」の流祖、宮本武蔵。
自著である『五輪書』には、数ある勝負にて無敗であったという記載があり、最強の剣士として有名です。
こちらは「鍛錬」の語源にもなった、『五輪書』に書かれている言葉。
何かを極めるためには、長年努力を継続する必要がある、という意味ですね。
宮本武蔵は鍛錬を怠らず技を極めたからこそ、無敗を誇る剣豪として名をはせたのでしょう。
コツコツ努力することは、やはり何事においても大切なのですね。
世界には、君以外には誰も歩むことのできない唯一の道があるフリードリヒ・ニーチェ

実存主義の代表的な思想家として知られている古典文献学者、フリードリヒ・ニーチェ氏。
「世界には、君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある」という名言は、後に「その道はどこに行き着くのか、と問うてはならない ひたすら進め」と続きます。
多くの人は自分と名人を比べて一喜一憂してしまいますが、自分にしか歩けない道であれば、そこに優劣は存在しないのではないでしょうか。
自分らしく生きることの大切さを教えてくれる、1日1日を正しく頑張れるようになれるメッセージです。
百年兵を養うは、ただ平和を守るためである。山本五十六
兵士といえば攻め込む人というイメージも強いですが、実際には国を守るために尽力している部分も強いですよね。
そんな兵士を育てることの重要性、何のために育てていくのかという考え方を示した言葉です。
いざという時に国を守れる存在があることで、攻め込むことをためらわせれば、平和にもつながっていくのだと主張しています。
平和という大きな目標のために何ができるのかという、考え方がしっかりと伝わってくるような内容ですね。
井上靖 の検索結果(91〜100)
俺はいいけどYAZAWAが何て言うかな?矢沢永吉
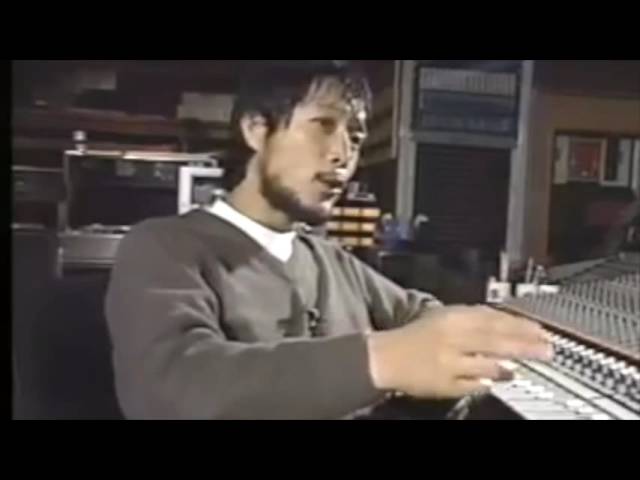
熱狂的ファンの多い、日本を代表するロックスターの矢沢永吉さんです。
YAZAWAという一人のロックアイコンという存在を矢沢永吉さん自身がプロデュースしてて、ファンの思う理想のYAZAWAで常にいなきゃならないというプロとしての意識の高い一言ですね。
