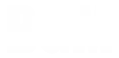【クラシック】クラシック音楽のBGM。作業用BGM・勉強用BGMにおすすめのクラシック音楽
「集中したいけど音楽は欲しい……」「作業中に聴くBGMを探している」そんな方におすすめなのが、クラシック音楽です。
心地よい旋律と上品な響きは、頭をクリアにして作業効率を高めてくれます。
けれども「クラシックってたくさんありすぎて、どれを選べばいいのかわからない」という声も多いですよね?
この記事では、作業用BGMや勉強用BGMとして特におすすめのクラシック音楽を紹介していきます。
静かに集中したいときも、リラックスしながら作業を進めたいときも、シーンに合わせて選べる曲ばかりですので、ぜひお気に入りの一曲を見つけてください。
- 【2026】作業用・勉強用におすすめ!かっこよくておしゃれなBGMまとめ
- どこかで聴いたことのある悲しいBGMまとめ【有名】
- BGMにおすすめのクラシックの名曲。癒やしのクラシック音楽
- 【ピアノ】ピアノで奏でるBGM。作業用BGM・勉強用BGMにおすすめの名曲、人気曲
- 勉強に集中できる曲。勉強がはかどる音楽
- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- テンション上がる!作業用BGMに最適な邦楽の人気曲・名曲を厳選
- 作業用BGMで集中力アップ!仕事やテスト勉強の人気曲・おすすめ曲
- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介
- 朝に聴くとテンションが上がる曲
- 【感動のBGM】作業用・勉強用におすすめの名曲&人気曲を厳選!
【クラシック】クラシック音楽のBGM。作業用BGM・勉強用BGMにおすすめのクラシック音楽(41〜50)
威風堂々第一番Edward Elgar

イギリスの作曲家エドワード・エルガーが作曲した行進曲です。
その高揚感溢れる力強い楽曲は有名で、日本の運動会などでも使用されているほどです。
エルガーが完成させたのは5曲だけですが、21世紀初頭に未完の第6番を新たに加えられて完成形になりました。
愛の挨拶Edward Elgar

イギリスの作曲家エドワード・エルガーが初期に製作した楽曲です。
宗教の違いや身分の差などで周囲に結婚を反対されていたエドワードが、妻であるキャロライン・アリス・エルガーに送った愛の曲だと言われています。
ピアノ独奏用、ピアノとヴァイオリン用、小編成の管弦楽などいくつかの版が残っています。
優しく愛おしい本楽曲は心を落ち着かせ、作業や勉強BGMとして流すと集中力を高めてくれることでしょう。
クシコスポストの郵便馬車Hermann Necke

ドイツの作曲家ヘルマン・ネッケが作曲した曲です。
その疾走感あふれる明るい曲調は日本では運動会でなどよく親しまれており、一般にも大変有名で人気の高い楽曲です。
長らく日本以外では知名度も高くなかったのですが、徐々に世界でも知られるようになってきています。
天国と地獄(地獄のギャロップ)Jacques Offenbach

ドイツ生まれの作曲家ジャック・オッフェンバック作曲のオペレッタです。
「地獄のオルフェ」が正式な名前ですが日本では「天国と地獄」という名で知られ、その高揚感溢れる曲調から運動会などでも使用され、一般にも馴染みのあるクラシックの名曲です。
トランペット・ヴォランタリーJeremiah Clarke

イングランドの作曲家であるジェレマイア・クラーク作曲の曲です。
イギリスのアン女王の夫カンバーランド公ジョージの為に作られた曲です。
長い間同じイングランド作曲家のヘンリー・パーセルが作曲した曲だと思われていました。
トリッチ・トラッチ・ポルカJohann Strauss II
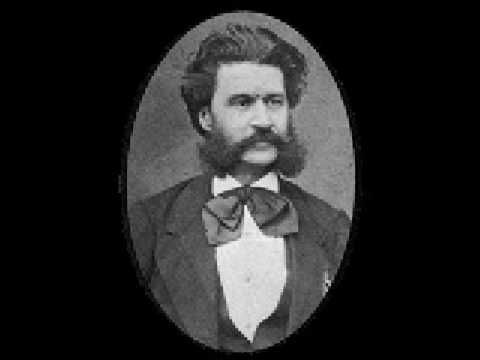
オーストリアのヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカです。
サンクトペテルブルクで出会ったオルガ・スミルニツキーとの結婚を彼女の家族に反対されたヨハンが、彼らのゴシップを載せた雑誌を揶揄して作曲したと言われています。
狩りのポルカJohann Strauss II

ヨハン・シュトラウス2世が作曲したポルカです。
オペレッタに登場した音楽をポルカやワルツに編曲する事が多かったヨハンが、875年に作曲された『ウィーンのカリオストロ』の中の「おお、私の駿馬よ」から引き出して作曲した曲です。