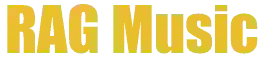【魅惑の即興演奏】フリー・ジャズの代表作・人気のアルバム
たとえば既存のクラシック音楽から全く違った様式や手法を試みたものが現代音楽と呼ばれるようになり、通常のスタイルのロックとは違ったアプローチを展開したポスト・ロックと呼ばれるジャンルがあったり、一定のジャンルにおけるサブジャンルは多く存在していますよね。
「フリー・ジャズも、まさに言葉通り前衛的な方法論やフリーキーな即興演奏が特徴的な、ジャズという括りの中で新たに生まれたジャンルです。
今回はそんなフリー・ジャズと呼ばれる作品の代表的な1枚や人気作を選出してみました。
決して万人受けするような音楽ではありませんが、興味を持たれた方はぜひこの機会に挑戦してみてください!
- 【まずはここから!】ジャズロックの名曲。おススメの人気曲
- アシッドジャズの名曲。おすすめの人気曲
- 【2026】ジャズの今を知る!最新の注目曲・人気曲まとめ
- 【2026】ジャズピアノの名曲。定番曲から近年の人気曲まで紹介
- 【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!
- スウィングジャズの名曲。おすすめの人気曲
- ジャズファンクの名曲。ジャズとは一味違うオススメの人気曲
- 【ジャズの殿堂】ブルーノート・レコードの名盤。おすすめのジャズアルバム
- 【初心者向け】モダンジャズの名盤。まずは聴きたいおすすめのアルバム
- 踊れるジャズ!~アシッドジャズの名盤・オススメのアルバム
- 【まずはこの1枚】ジャズの名盤。必聴のアルバムセレクション
- 【本日のジャズ】今日聴きたい!往年の名曲や現代ジャズをピックアップ
- 【ジャズとは】ジャジーな感じにしてほしいと言われたら?
【魅惑の即興演奏】フリー・ジャズの代表作・人気のアルバム(1〜10)
クレイ山下洋輔トリオ

日本におけるフリー・ジャズは、決して欧米の後追いなどではなく、むしろ世界に誇るべき驚きの個性と実力を持ったミュージシャンたちによって生まれました。
海外から輸入したというよりは、日本でも1960年代の時点で独自の音楽を鳴らすジャズ・ミュージシャンが現れて、同時代的にそれぞれのムーブメントが勃発していたのだと言えそうです。
当時の日本のフリー・ジャズがどれほどのものであったのかを私たちに教えてくれる作品の1つとして、今回は山下洋輔トリオの傑作ライブ・アルバム『クレイ』を紹介します。
1974年、ドイツにて行われたジャズのフェスティバルに出演した彼らの演奏が録音された本作は、ピアニストの山下洋輔さん、サックス奏者の坂田明さん、ドラムスの森山威男という3人の日本人による新しいジャズの形を、当時のヨーロッパのジャズ愛好家たちに知らしめた歴史的事実を真空パックしたもの。
アバンギャルドな演奏ながら、小難しい理屈をねじ伏せる暴力的なまでのパワーは、今聴いても衝撃的の一言ですね。
演奏が終わり、耳の肥えたオーディエンスから万雷の拍手と大歓声が巻き起こったのも当然でしょう。
AmajeloDon Cherry

フリー・ジャズの開祖的な存在、オーネット・コールマンさんとともに活動し、フリー・ジャズ史における重要作『ジャズ来るべきもの』や『フリー・ジャズ』などに参加したのが、アメリカはオクラホマ州出身のドン・チェリーさんです。
トランペット、そしてコルネット奏者であるチェリーさんは「ポケット・トランペット奏者」と呼ばれ、60年代においては多くのフリー・ジャズ系のミュージシャンと共演し、70年代以降はスウェーデンに定住して多彩なジャズ・サウンドを世に送り続けました。
チェリーさんの代表作の1つと呼ばれている『mu” First Part』は、1969年にフランスのジャズ・レーベルから発表されたタイトルです。
トランペットだけでなくフルートやピアノも担当したチェリーさんと、多くの作品でタッグを組んだジャズ・ドラマーのエド・ブラックウェルさんの2人だけで作り上げられた本作は、音楽家同士のスピリチュアルな対話の如きサウンド。
プリミティブな衝動を軸とした即興演奏から生まれたフレーズとリズムの応酬は、実験音楽という括りをこえた純度の高い創造物の結晶と言えるでしょう。
Space Is the PlaceSun Ra
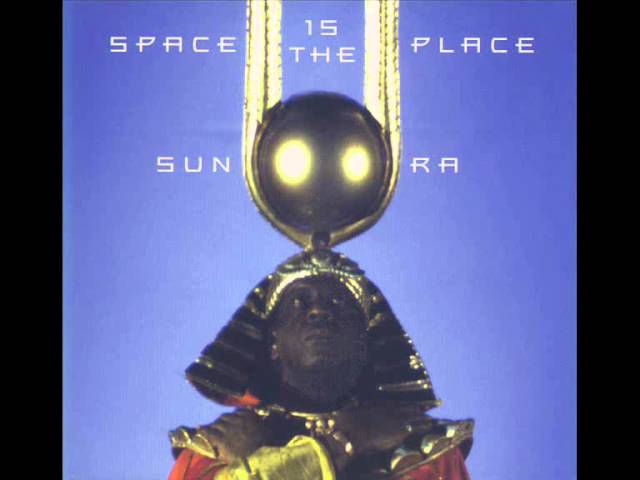
スピリチュアル、と書くとなんとなくうさん臭さを感じてしまう方も多いかもしれませんが、自らを土星生まれと称する伝説的な音楽家にして独自の宇宙哲学の持ち主、サン・ラさんの生み出したフリー・ジャズ~スピリチュアル・ジャズに広がる豊潤な音世界は、決してこけおどしなどではありません。
ジャズというジャンルの中で位置づけられているのは単なる偶然であって、あまりにも自由なサン・ラさんの魂を音として表現した結果、というだけな気もしますね。
1972年にリリースされた宇宙的傑作『Space Is The Place』は、タイトル自体がサン・ラさんの座右の銘であり、自ら「アーケストラ」と名付けた自身の楽団による演奏は、一切の音楽理論の制約から解き放たれた原始的な異国の祝祭のようです。
20分をこえる表題曲からして、アフリカン・リズムのグルーヴと飛び交うモーグとオルガンの響きでまったく違う世界へと聴き手を連れていってしまいす。
サンプリング・ソースとしてクラブ世代にも人気がある作品ですし、女性ヴォーカルの導入も含めて、サン・ラさんの宇宙に足を踏み入れるための入門編としても、ぜひ。
【魅惑の即興演奏】フリー・ジャズの代表作・人気のアルバム(11〜20)
Sun In The East高柳昌行

19歳という若さでプロのギタリストとして活動をはじめ、日本のフリー・ジャズ・シーンにおいて偉大な足跡を残した高柳昌行さん。
私生活は破天荒な芸術家を地で行くようなもので、幾度も逮捕されながらも裁判官に音楽家としての才能を惜しまれたというのもすごいですよね。
後に『あまちゃん』などの音楽を担当する音楽家の大友良英さんも、高柳さんのギター・レッスンを受けていたというのですから、その技術と才能は突出していたのでしょう。
今回紹介している『フリー・フォーム組曲』は、実際にオーディエンスを迎え入れたスタジオ・ライブという形で1972年に録音された作品です。
高柳昌行とニュー・ディレクション・フォー・ジ・アートという名義で発表された本作は、フリー・ジャズのみならず、ブルースやフォークなどの多彩なジャンルがまさに「フリー・フォーム」な演奏で表現された傑作であり、当時の空気感のようなものまで感じ取れる逸品となっておりますよ。
スピリチュアル・ジャズの歴史的な名曲『Sun In The East』をまずは聴いていただいて、その豊潤な音世界の一端を味わってみてください!
The Magic of Ju-JuArchie Shepp

1937年生まれのアーチー・シェップさんは、フリー・ジャズの歴史において欠かせないサックス奏者であり、1981年に公開されたフリー・ジャズのドキュメンタリー映画『イマジン・ザ・サウンド 60年代フリー・ジャズのパイオニアたち』にも出演している重要な存在です。
フリー・ジャズだけではなく、従来のジャズはもちろん、ブルースにR&Bといったブラック・ミュージックの領域においても作品を発表しており、一定のジャンルにとらわれない幅広い活動を続けている方でもあるのですね。
そんなシェップさんが1967年に録音、翌年の1968年に発表した『The Magic of Ju-Ju』は、まさにフリー・ジャズの世界で精力的な活動を続けていた60年代のシェップさんによる、攻撃的かつ過激な実験精神を全面に押し出した作品です。
重いテナー・サックスの響きと、アフリカ音楽からの影響が感られる原始的なリズムを生み出すパーカッションによる呪術的な雰囲気は、まさにおどろおどろしい骸骨のアルバム・ジャケットそのものといった趣。
急進的な60年代フリー・ジャズの醍醐味を味わいたい方は、ぜひ一度体験してみてほしいですね。
Titan MoonEvan Parker

1970年にリリースされたアルバム『The Topography of the Lungs』は、ヨーロッパのフリー・ジャズの歴史において非常に重要とされている1枚です。
イギリス出身のサックス奏者、エヴァン・パーカーさんの自己名義による初のアルバムであり、同じくイギリス出身で即興演奏のカリスマ的なギタリストであるデレク・ベイリーさんと、オランダ生まれのドラマー、ハン・ベニンクさんが参加しており、まさに当時の欧州フリー・ジャズ界における異能プレイヤーが集まって生み出された作品と言えるでしょう。
全編に渡り繰り広げられる3人の即興演奏は破壊的かつ無秩序でありながらも、時折差し込まれる静寂のパートが緩急をつける役割を果たしているように感じられます。
通常のバンド・アンサンブルとはまるで違う音世界は難解であり、フリー・ジャズをかなり聴き込んだ方でないと聴き通すのは難しいかもしれません。
3人がそれぞれの配置で演奏していますから、この作品を体験する際にはヘッドホン推奨ですね。
People In SorrowArt Ensemble Of Chicago
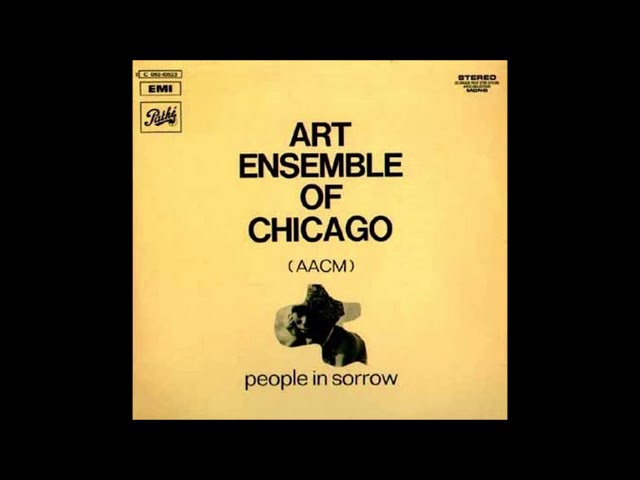
フリー・ジャズ系の代表的なバンドといえば、名前の通りシカゴ出身のアート・アンサンブル・オブ・シカゴでしょう。
シカゴのアフリカ系アメリカ人音楽家たちによって創立された非営利組織「AACM」のメンバーを中心として結成され、1968年にはレコード・デビューを果たしています。
初期の仕事としては、フランス出身のアバンギャルドなミュージシャン、ブリジット・フォンテーヌさんが1969年にリリースした名盤『ラジオのように』への参加などが挙げられます。
今回紹介しているアルバム『People In Sorrow』は1969年に発表されたもので、バンド・メンバーがヨーロッパに滞在時に録音されたもの。
『苦悩の人々』という邦題から、何やら高尚な雰囲気を感じ取ってしまうかもしれませんが、当時のメンバー4人による即興演奏から生まれたサウンドは、とくに前半は静寂なパートが多く盛り込まれ、混沌とは無縁の風景が描かれた非常にエモーショナルな世界です。
後半以降はフリー・ジャズらしい演奏の応酬もありながらも、テーマ性を持ったメロディは哀愁の響きを兼ね備え、アルバム全体的を通してもドラマティックな構造を持ち、意外に取っ付きやすいと言えるのではないでしょうか。