岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
民謡が多い地域です。
つまり地元に根付く文化が音楽と密接に関わってきたことを証明していますね。
季節的なでき事を歌う曲がメインで、その内容は日本的な審美感が表現されていると感じました。
今なら日本好きの外国の人に需要がありそうですね。
ぜひチェックしてみてください。
- 【岩手の歌】歌い継がれる故郷のこころ|岩手を思いながら聴きたい名曲集
- 【秋田の民謡・童謡】ふるさと愛を感じる郷土の名曲を厳選
- 【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い
- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集
- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌
- 【青森の歌】雄大な自然の様子や人々の温かさを描いたご当地ソング集
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌
- 【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
- 【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集
- 広島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 新潟の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ(1〜10)
南部長持ち唄中屋敷晃

長持ち唄とは結婚の時に歌われる歌であり、元々は、花嫁行列の時に長持を担いで歌ったことがその名の由来です。
この歌は雫石町や西和賀町などに伝えられています。
婿方の家と嫁方の家では違う歌詞を歌うなど、さまざまな決まりがあったようです。
沢内甚句中村美由紀

西和賀町の沢内と呼ばれる地域には、かつて隠し田が存在していました。
飢饉の折に、年貢を減らしてもらう引き換えとして藩に庄屋の娘を差し出したという悲しいエピソードから作られた歌です。
「ナニャドヤラ」が原曲とも言われています。
めんこい仔馬二葉あき子、高橋祐子
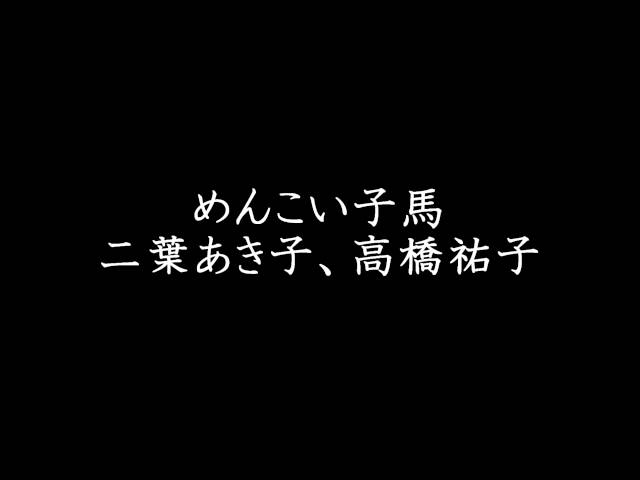
めんこい仔馬もやはり、戦時色があるため歌詞が改められたという歴史を持つサトウハチロー作詞の童謡です。
スタジオジブリの「火垂るの墓」の劇中に登場するため、知っている方も多いでしょう。
この動画では改変前の歌詞が歌われています。
岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ(11〜20)
からめ節友野ヒロミ

盛岡藩では金山の開発が行われており、ゴールドラッシュと言えるほど多くの金が採掘されていました。
金を精製する作業のことを「からめる」と言い、その様子を真似て踊らせたのがこのからめ節です。
「金山踊」とも呼ばれます。
道中馬方節唄/後藤吟竹、尺八/高橋竹山

馬喰が競り落とした馬を引いて帰る時に歌われた歌です。
慣れていない若駒を引く時には、日中ではなく夜の間に引くことが多かったようです。
この歌には馬の気持ちを落ち着ける意味と、自分自身の眠気を覚ます意味があるのです。
雫石どどさい節天笠弘子

盛岡城が築城される折に、現在の秋田県から岩手県へと移り住んだ人たちがいました。
彼らが歌っていた「仙北サイサイ」が伝えられ、変化したものがこのどどさい節です。
この歌が「ドンパン節」の原曲になったとも言われています。
ナニャドヤラ成田雲竹

岩手県の他、青森県や秋田県でも歌われている盆踊りの歌です。
意味のわからない歌詞が特徴で、民俗学者である柳田國男は女性が男性に呼びかけた歌であると解釈しています。
その他にもヘブライ語説や梵語説など、さまざまな説が存在します。





