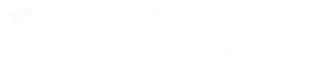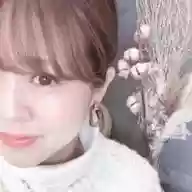6月におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
雨が続く6月の梅雨の時期は、室内で過ごす時間が長くなりますよね。
外で遊ぶのが大好きな子供たちの中には、雨の日に気分がどんよりしてしまう子もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、そんな子供たちが笑顔になるオススメの室内遊びを紹介します。
体を思いっきり動かす遊びはもちろん、友達や先生との関わりを楽しむ集団遊び、手先を使いながら集中して取り組む製作遊びなど、幅広いジャンルの遊びが盛りだくさん!
子供たちの年齢や発達に合わせて内容をアレンジしながらたくさんの遊びを取り入れて、雨の日もみんなで楽しく過ごしてくださいね。
- 【こども向け】放課後デイサービスで楽しむ、室内ゲームのアイデア特集
- 【高齢者向け】6月にちなんだ遊び。オススメのレクやゲーム集
- 【子供向け】本日のおすすめレクリエーションアイデア集
- 【子供向け】冬休みにオススメの室内で楽しめる遊び・レクリエーション
- 【大人向け】雨の日の楽しい遊び方まとめ
- 【第2弾】12月におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 【大人向け】雨の日に楽しめる遊び・趣味アイデア
- 【高齢者向け】簡単なテーブルゲーム。盛り上がるレクリエーション
- 7月におすすめの室内遊び・レクリエーションゲーム
- 春におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 夏におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム
- 雨でも安心!体育館でできる楽しいレクリエーション
- 子供向けの室内レクリエーション。盛り上がる遊びまとめ
6月におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム(1〜10)
ハンカチ落とし

みんなで円になってすわり、その後ろを鬼がハンカチを持ってまわります。
そしてすわってる人に見つからないようにハンカチをそっと落とし、すぐに逃げます。
落とされた人は鬼を追いかけますが、捕まえられなかったら自分が鬼になります。
たくさんの人数で遊べるので、学校や施設など広いところでも楽しめます!
フルーツバスケット

ジメジメとした6月。
雨が降る日が多くぜんぜん外で遊べなくて退屈になってしまいますよね。
そんなあなたにフルーツバスケットをご紹介します!
遊んだことがある人も多いのではないでしょうか?
こちらの動画のように大人の方でも大盛り上がりしますよ!
小麦粉粘土

手でこねる感触が楽しい粘土遊び。
その中でも、小麦粉粘土を使って室内での時間を楽しみましょう!
小麦粉粘土はその名の通り、小麦粉を粘土状にしたもので、手軽に作ることも可能です。
作る際は、小麦粉と水を混ぜ合わせ、色をつけたい場合は、食紅などを使いましょう。
塩を入れるともちが良くなり、油を入れるとモチモチ感がアップします。
子供たちの年齢によっては、粘土を作る工程から参加してもらうのもオススメです。
できた粘土を使って、いろんなものを作ってみてくださいね!
6月におすすめの室内で楽しめる遊び・レクリエーションゲーム(11〜20)
カードめくりゲーム

床に並べられたカードを自分のチームの色側にめくっていく、カードめくりゲーム。
まず、床に裏表で2色の色が塗られたカードをたくさん並べます。
スタートの際はそれぞれの色が同じ数、表に向いている状態にしましょう。
あとは、スタートの合図で自分のチームの色になっていないカードをめくって、どんどん自分のチームの色に変えていきます。
相手のチームにめくられてしまっても、制限時間内は何度でもめくり直しOKです。
最終的に、自分のチームの色にたくさんカードをめくれたチームが勝ち!
意外に運動量がしっかりある遊びなので、お子さんが運動不足かもと感じたらぜひ試してみてくださいね。
ハイハイ鬼ごっこ

鬼も逃げる人もみんなハイハイで動き回る、ハイハイ鬼ごっこ。
大人にはなかなか姿勢が厳しいですが、ハイハイに慣れている子供たちなら、通常の鬼ごっこと同様に楽しめますよ!
決して立たずに、ハイハイだけで動くというルール以外は、通常の鬼ごっこと同じ遊び方です。
壁になるような障害物を置いて、ハイハイしている姿が近くまで行かないと見えないような状態にしておくのもオススメ。
ルールを厳しくしすぎずに、ただ保護者の方や先生、お友達からハイハイで逃げるというだけにすれば、ハイハイを始めたばかりのお子さんでも取り組みやすいでしょう。
忍者ゲーム

雨の日は部屋の中で、みっちり忍者修行というのはいかがでしょうか。
忍者がやるようなあらゆる動きをマネして、体を動かしていきます。
ゆっくり足音を立てずに抜き足差し足で歩いてみたり、敵から身を隠すために忍法で木や石などに変身したり……。
また、1人が両手を合わせて素早くスライドさせ、あらゆる方向に手裏剣を打っている動きをし、もう1人がその手裏剣から逃れるという動きを繰り返すのもいいでしょう。
いろんな動きを組み合わせて、しっかり忍者になりきってくださいね!
マット運動

運動の際のクッションのイメージが強いマットを、遊ぶための道具として利用する内容です。
重たいマットを動かしていくゲームをとおして、力を合わせるということも楽しんでもらいましょう。
マットを引っ張り合うようなゲーム、ひっくり返すスピードを競うゲームなど、さまざまな方法でマットの重さを体験してもらいましょう。
少ない人数であるほど、マットを動かすために強い力が必要なため、重さを実感するとともに、協力することの大切さも感じてもらえるのではないでしょうか。