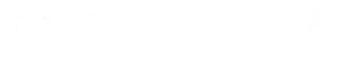【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング
お正月の雰囲気を盛り上げるBGMは、新しい一年のスタートに欠かせない存在ですよね!
おせち料理を囲む団らんの時間や、親戚が集まる賑やかなひととき、初詣の準備をしながら流したい音楽など、シーンによって選びたい曲も変わってくるのではないでしょうか?
この記事では、伝統的な和の雰囲気を感じられる楽曲から「正月」をテーマにしたJ-POPまで、幅広い音楽作品を集めてみました。
あなたのお正月をより華やかに彩る1曲が、きっと見つかりますよ!
- 【お正月の歌】新年に聴きたい名曲・人気のお正月ソング
- 【1月に聴きたい名曲】お正月がテーマ&新年に合う曲&ウィンターソング
- 【和の心】琴の名曲。日本の美しい調べ
- 【和風BGM】日本の伝統が織りなす美しい音色
- 【正月】新年会・忘年会で盛り上がるボカロ曲まとめ【年忘れ】
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる冬の歌。BGMやレクにオススメ名曲集
- 懐かしくも新しい!BGMに使ってほしい昭和に生まれたヒットソング
- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲
- 【高齢者向け】1月に歌いたい冬の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心温まるひととき
- 【冬ソング】冬に聴きたい名曲。冬に恋しくなる歌
- 【冬の歌】冬に聴きたい名曲&人気のウィンターソングベスト
- 【2026】新年を祝う洋楽の名曲。年の始まりに聴きたい人気曲
- 【2026】年末に聴きたい!年越しソング・冬のJ-POPまとめ
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(1〜10)
謹賀新年チャットモンチー

チャットモンチーが2011年にリリースしたアルバム『YOU MORE』収録曲。
新年を迎えた主人公が初詣に向かう人の列を眺めながら、隣にいるパートナーとの日々を思うラブソングです。
屋台の誘惑やドライブの思い出といった日常の断片を通して、これから先もずっと一緒にいられるようにという願いが表現されています。
そして橋本絵莉子さんのキャッチーな歌声と軽やかなバンドサウンドが心地いいんですよね。
かわいい雰囲気のお正月ソングをお探しの方にぴったりの1曲ですよ。
A HAPPY NEW YEAR松任谷由実

年明けを大切な人とともに迎えたいという願いが込められた、松任谷由実さんのこの楽曲。
1981年にアルバム『昨晩お会いしましょう』に収録され、同時期リリースのシングル『夕闇をひとり』のB面としても発表されました。
相手の幸せを祈る温かな気持ちがピアノの静かな響きとともに歌われています。
パートナーとお正月を過ごす方や、新しい年に特別な思いを寄せる方にぴったりの1曲です。
新高砂

明治初年に寺島花野さんが作曲したこの地歌箏曲は、能楽の待謡から歌詞を採った祝儀曲の代表作として知られています。
播磨国の高砂と摂津国の住吉に生える相生の松を夫婦和合や長寿の象徴とする伝承を背景にした、高低二部からなる箏の合奏と尺八、唄が織りなす重厚な響きが魅力です。
1997年5月に『箏曲名作選(九)明治新曲2』に収録、唯是雅枝さん、中島靖子さん、唯是震一さん、山本邦山さんらによる演奏が決定盤とされています。
結婚披露宴や式典といった晴れやかな場面で演奏されてきた本作は、おせち料理を囲む団らんや親戚が集まる賑やかなひとときにも、格調高い和の雰囲気を添えてくれるはずです。
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(11〜20)
餅ガールゲスの極み乙女。

お餅って年中食べてもいいはずなのですが、なぜかお正月しか食べないという方も多いのでは?
そんな餅にスポットライトを当てたゲスの極み乙女のこの楽曲。
2013年にリリースされたミニアルバム『踊れないなら、ゲスになってしまえよ』に収録されています。
トリッキーなサウンドと遊び心満載の歌詞で、餅への気持ちがあふれんばかりに表現!
聴けばお腹が空いてしまうかもしれません。
YOUNG BLOODS佐野元春

1985年に国連が定めた「国際青年年」の日本におけるテーマソングに起用、NHKなどでオンエアされたことで大きな話題になった楽曲です。
アルバム『Café Bohemia』にも収録されたこの曲は、旧来の価値観に縛られない若者たちの連帯と、自らの感性で新しい時代を切り開こうとする熱いメッセージが込められています。
UKソウルやR&Bの要素を取り入れたアップテンポなサウンドに、疾走感のあるビート、ホーンセクションが印象的。
「今年もがんばるぞ!」という決意を後押ししてくれる1曲です。
お年玉ユニコーン

お正月のワクワク気分を穏やかに描いた、ユニコーンの楽曲。
1992年12月にリリースされたシングル『雪が降る町』のカップリングとして収録されており、年末の情景を描いたA面と対比の効いた、新年への祈りが込められた温かなメロディーが印象的です。
歌詞では、お正月特有の神聖な雰囲気や良い年を願う気持ちが優しくつづられており、平和な年越しの風景が浮かんできます。
アコーディオンやバンジョーなどの多彩な楽器を使ったさわやかなアレンジが心地いいんですよね。
春の海宮城道雄

聴いただけでもすぐにお正月感を感じられるのが『春の海』です。
本作は日本の琴曲家であり、作曲家である宮城道雄さんが1929年に作曲し、それ以来100年以上にわたり日本人だけでなく、海外の人にも日本の心を表した曲として親しまれています。
近年ではお正月のデパートの初売りや、おせちが並ぶ食品コーナーなどでよく耳にしますよね。
そんなことからお正月のイメージが定着した『春の海』を聴いて、新たな1年の始まりをしみじみと喜んでくださいね。