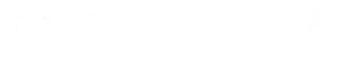【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング
お正月の雰囲気を盛り上げるBGMは、新しい一年のスタートに欠かせない存在ですよね!
おせち料理を囲む団らんの時間や、親戚が集まる賑やかなひととき、初詣の準備をしながら流したい音楽など、シーンによって選びたい曲も変わってくるのではないでしょうか?
この記事では、伝統的な和の雰囲気を感じられる楽曲から「正月」をテーマにしたJ-POPまで、幅広い音楽作品を集めてみました。
あなたのお正月をより華やかに彩る1曲が、きっと見つかりますよ!
- 【お正月の歌】新年に聴きたい名曲・人気のお正月ソング
- 【1月に聴きたい名曲】お正月がテーマ&新年に合う曲&ウィンターソング
- 【和の心】琴の名曲。日本の美しい調べ
- 【和風BGM】日本の伝統が織りなす美しい音色
- 【正月】新年会・忘年会で盛り上がるボカロ曲まとめ【年忘れ】
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる冬の歌。BGMやレクにオススメ名曲集
- 懐かしくも新しい!BGMに使ってほしい昭和に生まれたヒットソング
- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲
- 【高齢者向け】1月に歌いたい冬の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心温まるひととき
- 【冬ソング】冬に聴きたい名曲。冬に恋しくなる歌
- 【冬の歌】冬に聴きたい名曲&人気のウィンターソングベスト
- 【2026】新年を祝う洋楽の名曲。年の始まりに聴きたい人気曲
- 【2026】年末に聴きたい!年越しソング・冬のJ-POPまとめ
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(21〜30)
五段砧光崎検校

琴の繊細な音色が織りなす美しい旋律が、新年の清々しい雰囲気を醸し出す光崎検校さんの作品。
『五段砧』という名の本作は、5つの段から構成される箏曲の金字塔と呼ばれる名曲です。
砧打ちの音をモチーフに、秋の情景や遊女たちの魅力を表現した歌詞が、お正月の晴れやかな気分にぴったり。
19世紀の箏曲の中でも最高峰とされる本作は、高度な演奏技術を要する複雑な構成ながら、その美しさは聴く人の心を捉えて離しません。
お正月の静寂な朝、あるいは初詣の帰り道に聴きたい一曲。
伝統音楽に興味のある方にもおすすめの、日本の文化が詰まった珠玉の名曲です。
ふじの山作詞:巖谷小波

富士山の雄大さを称える文部省唱歌として知られるこの楽曲。
作詞を担当したのは、日本の近代児童文学の先駆者として知られる巖谷小波さんです。
富士山の頂が雲を突き抜け、四方の山々を見下ろす様子を詩的に表現した歌詞が印象的ですね。
1910年に『尋常小学読本唱歌』に掲載されて以来、小学校の音楽教材として広く親しまれてきました。
2007年には「日本の歌百選」にも選ばれるなど、日本の音楽文化において重要な位置を占める楽曲です。
お正月に富士山を眺めながら、この曲を口ずさむのもいいかもしれません。
伊勢音頭

江戸時代に伊勢国で生まれ、全国に広まった民謡として知られるこの曲。
「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ」という有名なフレーズは、地域の相互依存関係を巧みに表現しています。
三味線の軽快なリズムに乗せて唄われる歌詞には、伊勢参りの文化や風習が色濃く反映されており、日本の伝統的な新年の雰囲気を感じさせてくれますね。
昭和7年に復興され、現在の形となったこの曲は、お正月の祝い歌としても親しまれています。
新年を迎えるにあたり、日本の伝統文化に触れたい方にぴったりの一曲といえるでしょう。
梅は咲いたか

お正月の風情を感じさせる和楽器の音色が心地よく響く、日本の伝統文化の魅力を存分に味わえる作品です。
春の訪れを告げる季節の花々が歌詞に織り込まれており、新年の喜びと希望を感じさせてくれます。
2014年に宝塚歌劇100周年を記念して、宝塚駅の発車メロディに採用されるなど、その魅力は発表から長い時間のたった今も色あせることがありません。
日本の伝統音楽に触れたい方にぴったりの1曲と言えるでしょう。
高砂

最重要の伝統芸能である能の代表的な作品『高砂(たかさご)』。
詩の内容は高砂の松と住吉の松が遠くはなれた場所にあるのに、どうして相生の松と言われるのかという疑問に対し、老夫婦が夫婦の絆にたとえて答えるというものです。
現在の日本では結婚式の定番曲として有名ですね。
新年おめでとう WoO 165Ludwig van Beethoven

新年を祝う心温まる旋律が印象的な、ベートーヴェンさんによる短いカノン作品。
わずか30秒ほどの演奏時間ですが、4声が次々と追いかけるように「新年おめでとう」という言葉を歌い上げる構成が、新年の喜びと希望を見事に表現しています。
1815年に完成したこの曲は、ベートーヴェンさんが友人への新年の挨拶として贈ったものだそうです。
カントゥス・ノヴス・ウィーンなどによる『カノンと音楽の冗談』というアルバムに収録されており、ベートーヴェンさんの知られざる一面を楽しめます。
新年を迎えるときや、大切な人に新年の挨拶をする際のBGMとしておすすめ。
ベートーヴェンさんの人間味溢れる魅力を感じられる一曲です。
千鳥の曲吉沢検校

最も知名度が高い琴曲の一つである、こちらの『千鳥の曲』。
吉沢検校さんにより作曲されたこちらの曲は、『六段の調』と同じく、それまでにはなかった新しい音楽スタイルで、明治以降の音楽に多大な影響をもたらしました。
静寂すら音の一部と捉える日本音楽の良さがつまった1曲です。