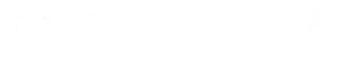【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング
お正月の雰囲気を盛り上げるBGMは、新しい一年のスタートに欠かせない存在ですよね!
おせち料理を囲む団らんの時間や、親戚が集まる賑やかなひととき、初詣の準備をしながら流したい音楽など、シーンによって選びたい曲も変わってくるのではないでしょうか?
この記事では、伝統的な和の雰囲気を感じられる楽曲から「正月」をテーマにしたJ-POPまで、幅広い音楽作品を集めてみました。
あなたのお正月をより華やかに彩る1曲が、きっと見つかりますよ!
- 【お正月の歌】新年に聴きたい名曲・人気のお正月ソング
- 【1月に聴きたい名曲】お正月がテーマ&新年に合う曲&ウィンターソング
- 【和の心】琴の名曲。日本の美しい調べ
- 【和風BGM】日本の伝統が織りなす美しい音色
- 【正月】新年会・忘年会で盛り上がるボカロ曲まとめ【年忘れ】
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる冬の歌。BGMやレクにオススメ名曲集
- 懐かしくも新しい!BGMに使ってほしい昭和に生まれたヒットソング
- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲
- 【高齢者向け】1月に歌いたい冬の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心温まるひととき
- 【冬ソング】冬に聴きたい名曲。冬に恋しくなる歌
- 【冬の歌】冬に聴きたい名曲&人気のウィンターソングベスト
- 【2026】新年を祝う洋楽の名曲。年の始まりに聴きたい人気曲
- 【2026】年末に聴きたい!年越しソング・冬のJ-POPまとめ
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(11〜20)
六段の調八橋検校

『千鳥の曲』に並ぶ日本の代表的琴曲である、こちらの『六段の調』。
作曲したと言われている八橋検校さんは、近世の琴の基礎やを作った人物と言われています。
シンプルな構成でありながら、静寂のなかにも風情を漂わせた、まさに至高の1曲といえる素晴らしい芸術作品です。
さくら変奏曲宮城道雄

聴いたことがなくてもこの曲を知っている方は多いと思います。
というのも、こちらの『さくら変奏曲』は日本の代表曲『さくらさくら』のアレンジした曲なので、『さくらさくら』のフレーズが至るところに登場します。
作曲者である宮城道雄さんが西洋音楽からヒントを受けた、日本の代表的な変奏曲です。
早春賦中田章

文化庁と日本PTA全国協議会が選定している日本の歌百選にも選ばれた、この曲『早春賦』。
1913年に吉丸一昌さんが作詞、中田章さんによって作曲されたこちらの曲は、長野県を中心に支持を得ています。
春を迎える安曇野一帯をテーマに書かれた歌詞は、情景描写が素晴らしく、懐かしい気分にさせてくれます。
Runner of the Spirit久石譲

ゲーム好きな方には『二ノ国』や『天外魔境』シリーズで、ジブリ映画ファンには『魔女の宅急便』や『風の谷のナウシカ』などですっかりおなじみの久石譲さん。
その久石さんの『Runner of the Spirit』をご存じですか?
あの箱根駅伝の中継に流れる曲といえば「ああ、あの曲かあ」となる方も多いはず。
希望あふれるお正月のBGMとしてもびったりですよね。
新春のマラソン大会やカルタ大会などの行事ごとにも重宝する1曲です。
この曲、なんと久石さんによるCD化はされていないとか。
どうしても音源が欲しい方は東京佼成ウインドオーケストラの『吹奏楽燦選/嗚呼!アフリカン・シンフォニー』というCDを探してみてくださいね!
越天楽

初詣に行くと必ずといっても過言ではないくらい耳にするのがこの音楽ですよね。
聴いたことはあるけど名前が分からないという人も多い本作は『越天楽』といいます。
中国から伝わり、日本の古典音楽とされる雅楽の中では最も有名な曲といわれています。
普段の生活ではあまり耳にしないような特徴的な楽器の何重にも重なった音色が荘厳な雰囲気を醸し出していますよね。
年末年始には古くから日本のお正月を彩る歴史ある本作を聴いてお正月気分に浸ってくださいね。
お正月電気グルーヴ

お正月といえばお昼から美味しいものをたらふく食べてお年玉をもらってぐうたらして……という具合にとにかくおめでたい日でもありますよね。
そんなおめでたさを目一杯音楽として表現したのが電気グルーヴの『お正月』です。
独特な展開を繰り広げる本作、一度聴いたらクセになって特にやることもないお正月に繰り返し聴いていたくなります。
アウトロまで陶酔感たっぷりで引きずりこまれていくような感覚がたまりませんね。
味わったことのないようなお正月気分に浸ってみてください!
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(21〜30)
UFO神社LOVE JETS

宇宙から飛来した覆面ロックンロールユニットLOVE JETSによる、異色のお正月ソングはいかがでしょうか?
初詣や神社での参拝風景を、地球に降り立った宇宙人の視点で描いたユニークな1曲で、2003年12月に発売されたシングルに収録されています。
ロックンロールの骨太なビートにディスコやテクノの要素を組み合わせた、踊れるサウンドが魅力的です。
日本の年中行事と宇宙スケールの視点が交錯する歌詞の軽やかさに、思わず笑みがこぼれますよ!
お正月の伝統行事を少し違った角度から楽しみたい方や、新年会で盛り上がりたいときにピッタリの楽曲です。