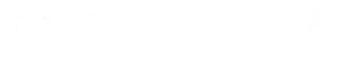【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング
お正月の雰囲気を盛り上げるBGMは、新しい一年のスタートに欠かせない存在ですよね!
おせち料理を囲む団らんの時間や、親戚が集まる賑やかなひととき、初詣の準備をしながら流したい音楽など、シーンによって選びたい曲も変わってくるのではないでしょうか?
この記事では、伝統的な和の雰囲気を感じられる楽曲から「正月」をテーマにしたJ-POPまで、幅広い音楽作品を集めてみました。
あなたのお正月をより華やかに彩る1曲が、きっと見つかりますよ!
- 【お正月の歌】新年に聴きたい名曲・人気のお正月ソング
- 【1月に聴きたい名曲】お正月がテーマ&新年に合う曲&ウィンターソング
- 【和の心】琴の名曲。日本の美しい調べ
- 【和風BGM】日本の伝統が織りなす美しい音色
- 【正月】新年会・忘年会で盛り上がるボカロ曲まとめ【年忘れ】
- 【高齢者向け】口ずさみたくなる冬の歌。BGMやレクにオススメ名曲集
- 懐かしくも新しい!BGMに使ってほしい昭和に生まれたヒットソング
- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲
- 【高齢者向け】1月に歌いたい冬の名曲。懐かしい童謡や歌謡曲で心温まるひととき
- 【冬ソング】冬に聴きたい名曲。冬に恋しくなる歌
- 【冬の歌】冬に聴きたい名曲&人気のウィンターソングベスト
- 【2026】新年を祝う洋楽の名曲。年の始まりに聴きたい人気曲
- 【2026】年末に聴きたい!年越しソング・冬のJ-POPまとめ
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(21〜30)
おばあちゃんが言ってた~新しい一年が生まれる朝は~magcafe at garden

お正月には「年神様」という神様が幸せを届けに来てくださるという言い伝えをおばあちゃんから聞いた、という話が歌詞になっています。
また、小さな子どものことも歌詞に盛り込まれています。
しっとりした演奏におばあちゃんや小さい子どもなど、心が温かくなるような1曲です。
お正月のもちつき

新春の訪れを告げるBGMとして、古くから親しまれています。
豊穣と家族の健康を祈る言葉が込められており、何世代にもわたり日本の家庭で愛されてきました。
和楽器の温かみが感じられる旋律は、心穏やかな新年のスタートを飾るのにぴったり。
幼いころに手遊び歌として楽しんだ方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
【お正月BGM】時代をこえて愛されるお正月ソング(31〜40)
ひとつとや

お正月に親しまれるわらべ歌として数え歌の『ひとつとや』がありますね。
数え歌とは数詞を盛り込んだり、数えることをテーマとした歌のことで、本作『ひとつとや』はお正月飾りや子供の遊びを歌詞に取り入れた数え歌です。
時代や地域によってパターンが異なるそうなので、自分の地域はどんな歌詞なのか、お正月の家族や親戚が集まるタイミングで聞いてみるのもいいかもしれません。
小さなお子さんとも一緒に楽しめるのでいろいろなパターンを覚えておいてくださいね。
一月一日

フジテレビの人気年始番組『新春かくし芸大会』のテーマソングとして採用されていたので、知っている方も多いかもしれません。
こちらの『一月一日(いちがついちじつ)』は稲垣千櫂さんと小山佐之助さんによるもの、千家尊福さんと上真行さんによるもの、葛原しげるさんと小松耕輔さんによるものの3つの作曲パターンがあります。
八千代獅子

お正月の風物詩として親しまれる伝統的な地歌・箏曲の名曲。
優雅な旋律と縁起の良い歌詞で新年の喜びを表現しています。
三味線や箏を中心とした和楽器の響きが、日本の伝統美を感じさせますね。
歌舞伎の下座音楽や長唄にも取り入れられ、古くから親しまれてきた曲です。
宮城道雄さんによる大管弦楽版など、様々な編成でも演奏されており、多彩な魅力を持っています。
お正月のBGMとして聴くのはもちろん、新年会や成人式など、祝い事の席でかけるのもおすすめ。
日本の伝統音楽に触れる良いきっかけにもなりそうです。
凧の歌

こちらの『凧の歌』は滝廉太郎さんの『お正月』とまではいきませんが、日本の有名な童謡です。
当時日本の中心であった関西圏で呼ばれていた紙鳶(いかのぼり)に対抗して、江戸っ子がイカの反対としてタコを名前にしたことが凧上りの語源とされています。
この曲の影響で、現在の紙鳶は凧上りと呼ぶようになりました。
初春

端唄の名曲である、こちらの『初春』。
タイトルからもわかるとおり、新しい年の訪れを歌った曲で、獅子舞やウラジロなどの正月にまつわる行事や風習が歌詞で多く登場します。
あまり有名な曲ではありませんが、聴けばたしかに春らしさを感じる素晴らしい1曲です。