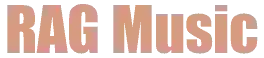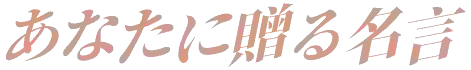【書き初め】新年にふさわしい四字熟語。心に響く言葉と意味をご紹介
次の書き初めにはどんな言葉を書こうか考えていますか?
毎年人気の四字熟語には、短い文字数の中に深い意味が込められており、新年の抱負を表現するのにぴったりです。
しかし「どんな四字熟語を選べばいいのだろう?」と迷ってしまう方も多いはず。
そこでこの記事では、書き初めにふさわしい四字熟語を紹介していきます。
力強く書き映える言葉から、新年の決意にふさわしい言葉まで、あなたにぴったりの言葉を見つけてくださいね。
- 新年の抱負に使いたい四字熟語!やる気が出る言葉のアイデア集
- 心に響く四字熟語で前向きになれる!一般的だけど深い意味を持つ言葉たち
- 【小学生】書き初めで書きたい!四字熟語のアイデア集
- 【一般】頑張る気持ちを後押しする四字熟語。心に響く力強い言葉たち
- 【小学生向け】新年の抱負に使える四字熟語。かっこいい目標の立て方!
- 【四字熟語】かっこいい響きが印象的!一般教養として知っておきたい名言集
- 意味も学べる!小学生が覚えたいかっこいい四字熟語
- 目標達成に効く四字熟語!一般的な場面で使える言葉たち
- 未来を切り開く四字熟語。座右の銘にもぴったりな挑戦や努力を表す力強い言葉
- 小学生が覚えやすい前向きな四字熟語!心が明るくなる言葉たち
- 小学生の学級目標にオススメ!四字熟語で心に響くアイデア集
- 目標に向かって頑張る!小学生の心に響く四字熟語のアイデア
- 団体で使える四字熟語のスローガン!力強いメッセージを伝える言葉
【書き初め】新年にふさわしい四字熟語。心に響く言葉と意味をご紹介(91〜100)
才色兼備
頭がよくて、さらにきれいな人という意味です。
つまり、頭のよさと見た目の美しさ、どっちも持っているすごい人のことをいいますよ。
たとえば、学校の発表でしっかり話せて、しかも笑顔もかわいい人がいたら、その人は「才色兼備」だと言えるかもしれません。
子供でも大人でも、かっこよくてステキに使える言葉なので、覚えておくのもオススメです。
ぜひ、「才色兼備」をめざして、勉強もがんばって、おしゃれも楽しんでくださいね!
文武両道
「勉強もスポーツも、どっちもがんばろう!」という意味の四字熟語。
学校でしっかり勉強しながら、友達と元気に遊んだり、運動したりすることが大切という意味です。
例えば、毎日漢字を覚えたり本を読んだりしながら、サッカーやバスケットボールも楽しむと、心も体も強くなっていきます。
文武両道をめざすと、頭も体もバランスをとりながら成長できて、毎日がもっと楽しくなるんですよ。
大人になっても、仕事と趣味の両方を大切にするのは「文武両道」の考え方と同じです。
ぜひ「文武両道」で毎日をかっこよく過ごしてみてくださいね!
【書き初め】新年にふさわしい四字熟語。心に響く言葉と意味をご紹介(101〜110)
晴耕雨読
晴れた日は畑で農作業して、雨の日は家で本を読むという、とてもステキな生活のことを表す四字熟語です。
自然と仲良くしながら、体も心も大切にするという意味が込められていますよ。
例えば、「今日はいい天気なので庭で遊んで、雨が降ったら家で本を読みましょう」というように使います。
晴耕雨読の暮らしは、毎日をのんびり楽しむヒントにもなります。
子供も大人も、心地よい時間を大切にできる言葉です。
忙しいときも、時々晴れの日に外で元気に動いて、雨の日はゆっくり読書をしてリフレッシュしてくださいね。
月下美人
月下美人はお花の名前、「ナイトクイーン」という別名でも親しまれる、夜にだけ咲くという性質が語られる種類です。
人々が寝静まる夜に、こっそりと美しさを発揮するという点が、自分の魅力をあえてかくしているようにも見えてきますよね。
その美しさからさまざまな俗説が流れている点もポイントで、特殊な花として親しまれてきたことがここからも感じられます。
厳密には四字熟語ではなくただの名称ですが、4文字のかっこいい言葉としてはオススメですよ。
有言実行
「言ったことをしっかり行う」という意味の四字熟語です。
たとえば、「明日から毎日勉強するよ!」と言ったら、本当に毎日勉強を続けることが有言実行です。
口だけで終わらせず、やると決めたことをやりとげると、自分にも自信がつきますよ。
例えば、サッカーの試合で「ゴールを決める!」とみんなに言って、本当にゴールを決められたら、とってもカッコいいし、うれしいですよね。
小さなことでも、できることから少しずつ、自分の言葉に責任をもって行動することで、周りの人からも信頼されます。
今日からぜひ、「有言実行」を目指してみてくださいね!
未来志向
「これからのことを前向きに考えて、よりよい未来を目指す気持ち」のことです。
例えば、テストで間違えても、「次はがんばろう!」と思うのが未来志向です。
むかしの失敗やイヤなことにとらわれず、「どうすればもっとよくなるかな?」と考えることが大切です。
「まだ泳げないけど、毎日練習すれば、いつか泳げるようになる!」という気持ちも未来志向ですよ。
大人も子供も、未来志向をもつことで、気持ちが明るくなり、行動も前向きになれます。
未来はこれからつくるもの。
だからこそ、「できること」「やりたいこと」に目をむけて、毎日をたのしくすごしていってくださいね!
百花繚乱
たくさんの花が一斉にきれいに咲いている様子を表す四字熟語。
これは、いろんなものが同時に美しく輝いているという意味もあります。
例えば、学校の文化祭でみんながそれぞれが違う得意なことを披露しているとき、「百花繚乱のようだね」と言えます。
たくさんの個性や才能が、一度にキラキラと輝いている感じがこの言葉のイメージです。
花がいっぱい咲く春の景色を思い浮かべると覚えやすいですよ。
それぞれの良いところが集まると、まるで百花繚乱の花畑みたいに、世界がもっと楽しくなりますよ。