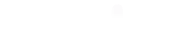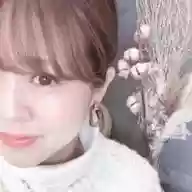【保育】少人数から大人数まで!楽しいゲームのアイデア特集
遊ぶのが大好きな子供たち!
毎日楽しいことを見つけ、ワクワクしながら過ごす姿は無邪気でとってもかわいいですよね。
たくさんの遊びを通してさまざまな経験を重ねながら、心も体ものびのびと成長してほしいですね。
今回この記事では、保育向けの楽しいゲームのアイデアをたくさんご紹介します。
園やご家庭で楽しめる遊びが盛りだくさん!
年齢や発達に合わせた内容の遊びを選んだり、子供たちの興味に合わせてルールをアレンジしたりすると、よりいっそう盛り上がりますよ。
みんなで楽しい時間を過ごしてくださいね。
- 【保育】3歳児におすすめ!みんなで楽しめる遊びアイデア
- 【保育・運動遊び】体を動かす楽しい遊び
- 保育園、幼稚園向けのレクリエーション。たのしい子どもの遊び
- 【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
- 【保育】みんなで楽しみたい言葉遊びやゲームアイデア
- 保育で使える!手遊びやゲームなど本日のおすすめレクリエーション!
- 【保育】元気いっぱい!体を動かす室内遊びのアイデア集
- 【保育】みんなで遊ぼう!集団遊びやゲームのオススメアイデア集
- 冬の保育で盛り上がる!子供たちが楽しめるゲーム&製作のアイデア集
- 【保育】お泊まり保育アイデア。遊びからゲームまで
- 夏だから楽しい子どもの遊び。保育&おうちでマネしたいアイデア
- 保育にオススメ!夏祭りで盛り上がるゲーム、出し物のアイデア
- 【保育】運動会の競技アイデア。運動会を盛り上げよう!
【保育】少人数から大人数まで!楽しいゲームのアイデア特集(111〜120)
ムカデオニ
@yokohama_rs #ムカデおに#レクリエーション#こどもの遊び#スポーツ#保育#保育士#専門学校#横浜#リゾスポ やってみよう! #アジリティトレーニング
♬ Boom, Boom, Boom, Boom!! – Vengaboys
機敏に動いて危機を回避しよう!
ムカデオニのアイデアをご紹介します。
鬼ごっこには氷オニや色オニなどさまざまな種類がありますよね。
仲間と協力して鬼から逃げるムカデオニはご存じでしょうか?
配役は鬼役1人、その他はムカデ役です。
ムカデ役は友達の肩に手を置いて離れないようにつながりましょう。
ムカデの最後尾の人が鬼にタッチされたら鬼の交代です。
自由に動く鬼から逃げるのは大変ですが、協力することでムカデチームは絆が育まれるでしょう。
宇宙人送還ゲーム
https://www.tiktok.com/@asobiinlife/video/7304249524820708609友達と協力して宇宙人を助けよう!
宇宙人送還ゲームのアイデアをご紹介します。
準備するものは風船、ペン、スタートラインやゴールラインがわかるものです。
このアイデアは宇宙人に見立てた風船をゴールまで運ぶシンプルなゲームですが、友達と協力するのが絶対条件です。
なぜなら4人1組で手をつないで、手を離さないことがルールなのです!
つないだ手や頭、肩やお尻などタイミングを合わせて声をかけ合いましょう。
協力して宇宙人を助けてください!
引っ張りフープあそび
https://www.tiktok.com/@soramame.sensei/video/7230741022383312146おもいやりの気持ちが勝利のポイント!
引っ張りフープのあそびアイデアをご紹介しますね。
準備するものはフラフープまたは新聞紙でつくった輪っか、スズランテープ、スタートとゴールラインです。
動く人は動くフラフープに合わせて歩みを進めましょう。
この時、フラフープから足が出ないようにバランスをとってください!
フラフープを引っ張る人はスピードや力加減をコントロールして仲間をゴールへ導きましょう!
ぜひ、遊んでみてくださいね。
輪っかリレー
https://www.tiktok.com/@kidschallengeclub/video/74020613455390835382種類の輪っかリレーのアイデアをご紹介します。
準備するものはスタートラインやゴールラインがわかるものです。
1つ目は前に並んでいる人の足の下をくぐって、すぐに立って足を広げてトンネルをつくってゴールにつなげる輪っかリレー。
2つ目は2人1組で輪っかをつくり、次に並んでいる人にくぐってもらいながらゴールを目指す輪っかリレーです。
どちらも1人ではゴールできないのがポイントです。
チームごとで競うのもおもしろいですね!
ちゅーりっぷしゃーりっぷ

友達と手をつなぎ、名前を呼びながら触れ合って遊ぼう!
ちゅーりっぷしゃーりっぷのアイデアをご紹介しますね。
準備するものはないので、歌をみんなで口ずさみながら遊びましょう。
歌の中で名前を呼ぶポイントがあるので、友達の名前を覚えられるのも魅力的ですよね。
転入園児や新入園児のいるクラスには特にオススメですよ!
遊び方がアレンジできるので乳児から幼児まで楽しめるアイデアです。
ぜひ、活動に取り入れてみてくださいね。
センサリートイあそび

年齢を問わず遊べる!
センサリートイのあそびアイデアをご紹介しますね。
準備するものは食品保存用袋、色水、オイル、あずき、消しゴム、金魚のおもちゃ、ビーズ、鈴、ヘアジェル、テープです。
ヘアジェルと一緒に準備した素材を袋に入れていきましょう!
色や素材のバリエーションをアレンジすると感触が変わっておもしろいですよ!
乳児だけでなく幼児クラスも夢中になるセンサリートイは、見て触れて楽しめるのでオススメですよ。
お引越しゲーム

お引越しゲームは、先生の「お引越し!」という合図で、子供たちが教室の反対側へ移動します。
その際に真ん中に立っている先生に捕まらないようにする遊びです。
先生の人数を増やしたり、ハイハイで移動するルールや静かに移動するルールにしたりなど、さまざまなアレンジも楽しみましょう。
また遊びを通して瞬発力や判断能力を高められるのもこの遊びの魅力です。
「うまく逃げられるかな」とワクワクしながら遊んでほしいと思います。