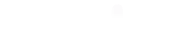【保育】10月に楽しみたい!4歳児さんにオススメの製作アイデア
秋になるとまた一段とたのもしくなる4歳児さん。
「来年は年長さんだね!」なんて会話も聞かれるようになるのではないでしょうか。
製作の活動も、自身のイメージをどう表現しようか迷ったり、想像力を活かしたアイデアを提案したりとより一層活動に深みが出ます。
今回はそんな4歳児さんと取り組みたい10月の製作アイデアをまとめました。
季節の素材やモチーフのものから、4歳児さんの発想力を活かせるものまでさまざまなアイデアを用意しましたよ。
ぜひ参考にしてください。
子供たちが作ったものは作品として扱うため、文中では「制作」と表記しています。
- 【10月】保育に使える!秋の製作アイディアを紹介
- 【4歳児】製作遊びのアイデア
- 【4歳児】11月にオススメ!秋を感じる製作遊び
- 【4歳児】作って楽しい!ハロウィン製作のアイデア集
- 秋に4歳児の取り組みたい製作アイデア!季節のモチーフや行事に合わせて製作活動を楽しもう
- 4歳児の9月の製作が盛り上がる!秋のモチーフで楽しむアイデア特集
- 【保育】10月にぴったり!5歳児さんと楽しむ秋の製作
- 【保育】5歳児さん向け!秋の製作アイデア
- 【4歳児向け】室内でできる集団遊びや製作遊びのアイディア
- 5歳児さんの9月の製作にオススメ!秋を楽しむアイデア集
- 【3歳児製作】秋に楽しみたいアイデア特集!季節のモチーフを取り入れよう
- 【保育】3歳児さんにぴったり!10月の製作アイデア
- 年中児さんの10月の折り紙!季節を感じるアイデア集
【保育】10月に楽しみたい!4歳児さんにオススメの製作アイデア(21〜30)
封筒を使ったみのむしのペーパークラフト
茶封筒を使って作るみのむしのアイデアをご紹介しますね。
封筒の上部をハサミで切り落ちし、上の左右の角を裏側に折ります。
白と黒の丸シールを重ねて作った目を貼ったら、体の部分に色紙や毛糸を貼ってミノを表現しましょう。
色紙は事前に小さくやぶっておき、毛糸も適度な長さに切っておいてくださいね。
最後に封筒の裏側に麻ヒモをテープで付けたら完成です。
色紙や毛糸のほか、お散歩で拾ってきた葉っぱや小枝を接着してもかわいくなりそう。
ゆらゆら楽しい!紙コップみのむし

壁に飾れば、カラフルで楽しいミノムシたちにたくさん出会えるこちら。
まず、好きな色の折り紙を2枚用意し、それぞれ4等分程度にわけられるように、たてにビリビリ破ります。
次に、破った折り紙の片方の端にのりをつけて、紙コップの底に近い側面にランダムに貼っていきます。
2色の折り紙を交互に貼っていってもいいですし、同じ色をまとめて貼っていくのでもOK!
このときに、画用紙や折り紙で作ったミノムシの目も貼ってくださいね。
あとは、紙コップの底に千枚通しで穴をあけて、ぶらさげるためのたこ糸を通して固定すれば完成です!
千枚通しで穴をあける作業は、幼稚園や保育園の先生、保護者の方が対応してくださいね。
作って遊べる!ミノムシけん玉
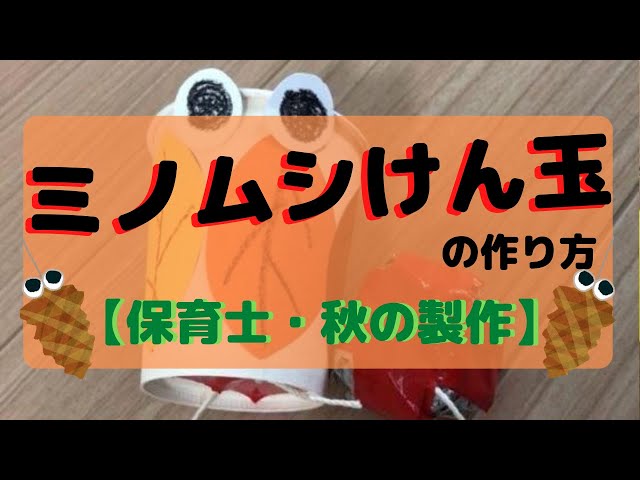
ボールをてっぺんにさしたり、横のお皿に乗っけたりして楽しめるけん玉をミノムシ型にしてみませんか?
まず、新聞紙を丸めてビニールテープで整え、けん玉の玉を作ります。
このとき、両端を固結びしたたこ糸の一方の端も一緒にくっつけておきましょう。
次に、もう一方のたこ糸の端を紙コップの外側の底面に貼ります。
そして、画用紙や折り紙を切り出して作ったミノムシの目や落ち葉のような体を紙コップの周りに貼れば完成です!
通常のけん玉よりも簡単に玉が入るので、お子さんも楽しく遊べますよ。
手形で作る!ゆらゆらみのむし
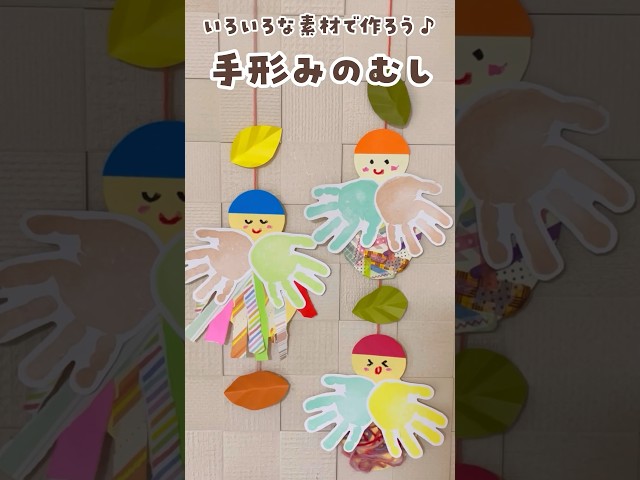
子供たちの手形、足形を使って作るみのむしのアイデアです!
まず、色画用紙でみのむしの体を作ります。
次に、好きな色の折り紙を縦長にびりびりとやぶっていきましょう。
のりなどで体に貼っていき、子供の手形でお洋服を着せてあげてくださいね。
お顔を描いて、ぶらさげる用の毛糸のひもをつければ完成!
折り紙のほかにも毛糸でアレンジする方法もありますよ。
いろいろな色でいっぱい作って飾ると、とってもかわいいのでオススメです。
ぜひ子供たちと一緒にちぎったり、貼ったりしながら楽しんでみてくださいね!
折り紙で作れるコスモスリース

コスモスには7.5センチ、土台には15センチの折り紙を4枚ずつ使います。
まず、7.5センチの折り紙を三角に折り、左右の角を内側に向かって交差させ、キレイに重なるように折ります。
折った部分を外側の辺に合わせて折り返し、折り目を付けたらその部分をひらいてつぶしてください。
つぶした部分の両角を裏側に折り込み、上の角3つに三角の切り込みを入れたら花びらパーツのできあがり。
4つ接着してコスモスを作り、中央に丸シールを貼ってくださいね。
土台は、上下の角を折り紙の中心に合わせて折り、さらにそのまま上下を重ねて二つ折りします。
上の左右の角に合わせて、下の辺をそれぞれ折り上げ、折り目がついたらその部分をつぶしましょう。
こちらも4つ作って円形に接着、コスモスを飾ったらリースの完成です。
コスモスは色違いで作ると華やかですよ。
毛糸まきまき!ミノムシのオーナメント

毛糸遊びも楽しめる、みのむしの制作にチャレンジしてみましょう。
まずは白い画用紙に色画用紙を貼り付けて、たまごの形にカットしてください。
フチに細かく切り込みを入れたら、切れ込みに挟みながら毛糸をくるくると巻きつけていきますよ。
画用紙がゆがまないようにやさしく、だけど毛糸がゆるんで外れない強さで巻いてくださいね。
毛糸が巻けたら丸シールでミノを飾り付け、ペンで顔を描いてチークで頬をピンクに染めたら完成です!
秋の壁面!キノコとみのむし

のりでペタペタ貼るのが楽しいきのことミノムシの壁面です。
まず、パーツを作ります。
好きな色の画用紙でいろいろな形のきのこを切りましょう。
小さい子供の場合には、先に切って準備しておいてくださいね。
きのこに切り込みを入れたら、きのこの軸になるように別の画用紙を切ります。
次にミノムシを作ります。
目を描くなど、子供たちができるところは一緒にやってみてくださいね。
ここから制作です。
台紙になる画用紙にミノムシの体になるように画用紙をちぎって貼っていきましょう。
目と帽子も貼ってくださいね。
最後に、きのこを切り込みで重ねて立体になるように貼れば完成です。