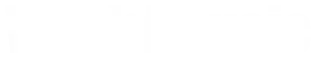【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽
荘厳なハーモニーが響き渡り、聖書の物語を音楽で表現する壮大な音楽形式「オラトリオ」。
その歴史はバロック時代にまで遡り、宗教音楽の最高峰として親しまれてきました。
今では教会だけでなくコンサートホールでも演奏される、クラシック音楽の重要なジャンルとして愛されています。
オラトリオの魅力は何と言っても合唱とオーケストラが織りなす圧倒的な音の厚みと迫力。
オペラとはまた異なる音楽の世界が広がっているのです。
この記事では、クラシック音楽の歴史に残る名作オラトリオをご紹介します。
- 【コラール】コラールの名曲。おすすめの人気曲
- 【涙腺崩壊】心が震えるほど泣ける歌&歌詞が心に染みる感動する曲
- 【2026】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
- 華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集
- 【アルペジオ】美しい洋楽の名曲たち。珠玉のギターサウンド
- 【2026】ワールドミュージックの今。多様な音楽文化を楽しめる名曲を紹介
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- サルサの名曲。おすすめの人気曲
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- 【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌
- 【2026】合唱コンクールで歌ってみよう!おすすめの洋楽まとめ
- 世界のゴスペル・シンガー。ゴスペル・ミュージックの名曲、おすすめの人気曲
- 【英語で歌える合唱曲】合唱コンクールで歌えるオススメ曲も!
【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽(1〜10)
マタイ受難曲J.S.Bach

バロック音楽を代表するヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲した、受難オラトリオの最高峰と称される大作です。
二つの合唱とオーケストラが織りなす壮麗な音の建築は、まさに圧巻の一言。
この楽曲は、聖書の物語をなぞるだけでなく、登場人物の痛切な心情を映すアリアや、聴き手自身の祈りとなるコラールが深く胸に響きます。
1829年にメンデルスゾーンが再演し、バッハ再評価の大きなきっかけとなったことでも有名ですよね。
カール・リヒター指揮の名盤『Matthäus-Passion』をはじめ数々の録音が存在し、時代を超えて愛され続けています。
本作は、壮大な音楽の世界に身を委ね、深い感動に浸りたいときにぴったりの不朽の名作です。
ヨハネ受難曲J.S.Bach

荘厳なハーモニーと劇的な展開で、聖書の物語を音楽で表現する受難オラトリオの金字塔。
音楽の父ヨハン・ゼバスティアン・バッハによる本作は、福音史家の語りを軸に、激しく感情をぶつける群衆の合唱と、個人の深い嘆きや祈りを歌うアリアが交錯する構成なのです。
まるで壮大なオペラを聴いているかのような緊張感と、魂を静めるコラールの安らぎが同居する世界観に引き込まれますよね。
この大作は1724年4月7日にライプツィヒで初演され、今日ではBach Collegium Japanによるアルバム『J.S. Bach: St. John Passion, BWV 245』など数多くの名盤が存在します。
物語性豊かなクラシック音楽にじっくりと浸りたいとき、そのドラマティックな響きに心を委ねてみてはいかがでしょうか。
オラトリオ「日蓮聖人」黛敏郎
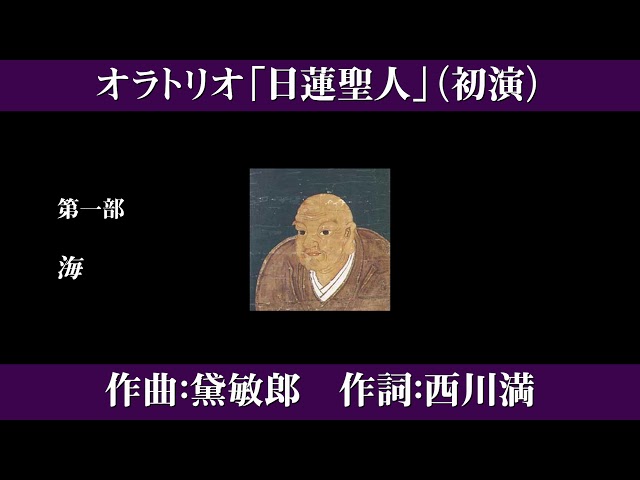
戦後の日本音楽界を代表する作曲家として知られる黛敏郎さん。
現代音楽のみならず映画音楽の分野でも活躍した音楽家です。
黛さんの作品のなかでも、仏教的世界観を西洋のオラトリオ形式で表現したこの大作は、まさに圧巻の一言に尽きます。
日蓮の生涯を「海・花・光・雪・山」の5部構成で描き、日本語の朗読と重厚な合唱、シンフォニックなオーケストラが一体となって壮大な物語を紡ぎだすのですね。
終盤、題目を反復しながら高揚していくクライマックスは、聴く者の魂を揺さぶるでしょう。
本作は、日蓮聖人第七百遠忌の記念事業として1982年4月に初演された作品です。
西洋音楽の枠組みに日本の精神性を融合させた、唯一無二の音楽体験を求める方にぜひ聴いていただきたい名曲です。
【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽(11〜20)
聖エリーザベトの伝説Franz Liszt

ピアノの魔術師として有名なフランツ・リストですが、祖国ハンガリーの聖女をテーマにした壮大な宗教音楽も作曲したことはご存じでしょうか?
この楽曲は、テューリンゲン方伯家に嫁いだ王女エリーザベトの慈愛に満ちた生涯を描いたオラトリオです。
実はこの壮大な構想は、ワルトブルク城にある連作フレスコ画から着想を得たという経緯があるのです。
聖女を象徴する祈りの旋律が全編を通じて繰り返し現れ、物語に深い精神性と統一感を与えているのが本当に素晴らしいですよね。
1865年8月にリスト自らの指揮で初演された本作は、ヤーノシュ・フェレンチク指揮の『Hungaroton』盤などで聴くことが可能です。
オペラとは違う、荘厳な合唱と管弦楽が織りなす感動的な音の世界に浸りたい時にオススメです!
復活祭オラトリオJ.S.Bach

輝かしいファンファーレが復活の朝を告げる、ヨハン・ゼバスティアン・バッハによる祝祭的なオラトリオです。
本作は、トランペットやティンパニが織りなす壮麗な器楽パートと、4人の独唱者が演じる登場人物たちの劇的な対話が大きな魅力ですよね。
主の墓へと急ぐ弟子たちの高揚した足取りや、驚きから確信へと変わる心の機微が、音楽を通して鮮やかに描かれています。
1725年4月の復活祭当日に初演されたこの楽曲は、もともとは別の祝賀カンタータだったという興味深い制作背景も持っています。
オーケストラと声楽が生み出す荘厳な響きに包まれ、希望と喜びに満ちた物語の世界に浸りたいときにぴったりの名作です。
オラトリオ『使徒たち』 作品49Edward Elgar

『威風堂々』といった作品でも知られるイギリスの作曲家、エドワード・エルガーのオラトリオ作品。
新約聖書を題材にした、上演時間およそ2時間にもおよぶ壮大な楽曲ですよね。
本作の聴きどころは、なんといっても登場人物たちの克明な心理描写にあるのかもしれません。
エルガーは、罪に苦悩するユダや救いを求めるマグダラのマリアの感情を、ワーグナーの影響を感じさせる緻密な動機を用いて表現しています。
古代の羊角笛ショーファールが鳴り響くなど、オーケストラと合唱ならではのドラマチックなダイナミクスを楽しめるのも魅力です。
1903年に初演された作品で、サー・マーク・エルダー指揮の演奏は2013年のBBCミュージック・マガジン・アワードで受賞するなど、現代でも高く評価されています。
物語性豊かなクラシックの世界に深く浸りたい方におすすめですよ。
サムソン HWV.57「序曲」Georg Friedrich Händel

後期バロック音楽を代表するゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル。
ヘンデルがかの有名な『メサイア』完成直後に手がけ、1743年2月に初演されたオラトリオ『Samson』の序奏を飾る作品です。
このオラトリオは英雄の悲劇を扱いますが、本作はその物語を直接描くのではなく、壮大なドラマへの期待感を高める役割を担っています。
そんな本作の魅力は、輝かしい金管楽器が力強く響き渡る部分。
英雄が持つ威厳や物語の神聖さを予感させ、聴く人の心を一気に引き込みますね。
ニコラウス・アーノンクール指揮による録音でも知られるこの作品は、集中して物事に取り組む前の導入や、クラシックの壮大な世界観に浸りたいときにぴったりではないでしょうか。