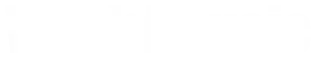【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽
荘厳なハーモニーが響き渡り、聖書の物語を音楽で表現する壮大な音楽形式「オラトリオ」。
その歴史はバロック時代にまで遡り、宗教音楽の最高峰として親しまれてきました。
今では教会だけでなくコンサートホールでも演奏される、クラシック音楽の重要なジャンルとして愛されています。
オラトリオの魅力は何と言っても合唱とオーケストラが織りなす圧倒的な音の厚みと迫力。
オペラとはまた異なる音楽の世界が広がっているのです。
この記事では、クラシック音楽の歴史に残る名作オラトリオをご紹介します。
- 【コラール】コラールの名曲。おすすめの人気曲
- 【涙腺崩壊】心が震えるほど泣ける歌&歌詞が心に染みる感動する曲
- 【2026】美しきアンビエントの世界。一度は聴きたいおすすめの名盤まとめ
- 華麗なる歌声の世界。オペラから歌曲まで、人気の声楽曲特集
- 【アルペジオ】美しい洋楽の名曲たち。珠玉のギターサウンド
- 【2026】ワールドミュージックの今。多様な音楽文化を楽しめる名曲を紹介
- アカペラの名曲。美しいハーモニーが際立つおすすめ曲【洋楽&邦楽】
- サルサの名曲。おすすめの人気曲
- ケルト音楽の名曲。おすすめのアイリッシュ音楽
- 【讃美歌】有名な賛美歌・聖歌。おすすめの讃美歌・聖歌
- 【2026】合唱コンクールで歌ってみよう!おすすめの洋楽まとめ
- 世界のゴスペル・シンガー。ゴスペル・ミュージックの名曲、おすすめの人気曲
- 【英語で歌える合唱曲】合唱コンクールで歌えるオススメ曲も!
【クラシック】オラトリオの名曲。おすすめのクラシック音楽(21〜30)
楽園とペリRobert Schumann

「トロイメライ」で有名なドイツの作曲家、ロベルト・シューマンによるオラトリオです。
オラトリオはキリスト教を題材としたテーマが多いですが、このオラトリオはペルシア世界が題材となっています。
罪を犯して楽園を追放されたペリ一族の子供が再び楽園に入ることを許されるために捧げものを探すという内容となっています。
初演は1843年12月4日、ライプツィヒのゲヴァントハウスでシューマン自らの指揮で行われ、大成功を収めたオラトリオです。
同時期に活躍したクラシックの作曲家メンデルスゾーンも本曲の賛辞をシューマンに贈っています。
オリーヴ山上のキリストLudwig van Beethoven

誰もが知っているドイツの楽聖ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンのオラトリオです。
しかしこのオラトリオは上演の機会がほとんどなく知られていません。
オリーヴ山上でのキリストの祈りと、その後キリストが捕縛される場面を描いたオラトリオで、1803年に作曲されてウイーンで初演されました。
ベートーヴェンの自作の演奏会でのちに代表作となる交響曲第1番と第2番、ピアノ協奏曲第3番が初演されていますが、当時として成功を収めたのは本オラトリオの方で、1825年に再演が行われた際に、ベートーヴェンの会話帳の中で「再演の度に満員の盛況」と記述がみられることから当時の聴衆に多く受け入れられているのがわかります。
ベートーヴェンと当時の聴衆のトレンドが分かる作品でおすすめのオラトリオとなっています。
長崎Alfred Schnittke

ソビエト連邦のドイツ・ユダヤ系作曲家アルフレート・ガリエヴィチ・シュニトケがモスクワ音楽院の卒業制作として作曲したオラトリオです。
長崎の原子爆弾投下をモチーフにした作品で、島崎藤村の「朝」や米田栄作の「川よとわに美しく」をロシア語に直したものがテキストに使用されました。
オラトリオは日本語では「聖譚曲」と呼ばれ、主に宗教曲が扱われることも多いのですが、本作品は日本で起こった出来事を題材としているため、異色のオラトリオとなっており、ロシアの作曲家スヴィリドフに絶賛される一方で作曲家同盟からは評価を得られず、1958年に作曲されるものの2006年まで演奏されることはありませんでした。
劇中音楽の雰囲気も近く、他のオラトリオとは異なる視点で視聴してみてください。
ゲロンティアスの夢Edward Elgar

オーケストラ作品「威風堂々」や「愛の挨拶」で有名なイギリスの作曲家、エルガーが作曲したオラトリオです。
『ジェロンティアスの夢』と表記されることもあり、エルガーが32歳で結婚した時に枢機卿からもらった長編詩「ゲロンティアスの詩」から感銘を受けて作曲されました。
エルガーのオーケストラ作品は「威風堂々」を代表とするように非常に厳格でキビキビしたものが多いですが、本オラトリオは壮大でロマンチックです。
初演の際、ヘンデル風のオラトリオを期待されましたが、エルガーの新しいアプローチには驚いた聴衆も多かったようです。
しかし、バーナード・ショウを含む一部の批評家たちは『ゲロンティアスの夢』を傑作と認め、曲の神秘と詩情、効果的な合唱書法、鮮やかな音楽的心象、気高い精神性などが賞賛されました。
7つの封印の書Franz Schmidt

このオラトリオは、オーストリアの作曲家フランツ・シュミットが1938年に作曲しました。
新約聖書の「ヨハネの黙示録」をモチーフにしたテキストで、グレゴリオ聖歌やバッハの宗教音楽の要素とモダンな響きを織り交ぜた壮大な作風が印象的です。
ソロモンの裁きMarc-Antoine Charpentier

バロック期、フランスを代表する作曲家シャルパンティエは非常に多くの宗教音楽を書いています。
青年期にローマに留学し、オラトリオをフランスに持ち帰りました。
30曲以上のオラトリオを作曲し、その中でも代表的なのが「ソロモンの裁き」です。
ゴルゴタFrank Martin

スイス人プロテスタントの作曲家、フランク・マルタンはジュネーヴに生まれ、ジュネーヴ大学で数学と物理学を学びながら作曲とピアノも本格的に勉強していました。
近代音楽でどんどん調性が崩壊していくのに対して、無調には反対して調整に固執したのがフランク・マルタンです。
ゴルゴタは1949年に作曲され、日本でも1978年に東京交響楽団によって演奏されています。