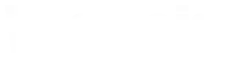【流行】昔よく聴いた・懐かしいボカロ曲まとめ
最新技術なイメージも強い合成音声技術のボカロですが、初音ミクが発売されたのは2007年。
そう考えるとシーンが出来上がってけっこうな時間がたっているんですよね。
子供の頃からボカロ曲を聴いている世代のことを「ネイティブボカロ世代」なんて呼び方をすることも。
今回この記事では「懐かしいボカロ曲」をテーマに作品をまとめてみました!
「昔よくボカロ曲を聴いていた」という方にとってはとくに響く内容かも。
一緒にボカロの歴史をひも解いていきましょう!
【流行】昔よく聴いた・懐かしいボカロ曲まとめ(71〜80)
エンヴィキャットウォークトーマ
物語性のある楽曲を中心にリスナーから人気を集めるボカロPのトーマさん。
彼が2011年に制作した『エンヴィキャットウォーク』は、初音ミクのメカニカルな歌声とロックサウンドが絡み合うボカロ曲です。
疾走感のあふれるバンド演奏にのせた彼女の滑らかな歌唱が展開。
スリリングな恋愛模様が思い浮かぶ歌詞をリズミカルに歌いこなしています。
楽曲の後半でテンポが上がるとともに、情熱的なサウンドが加速するロックナンバーです。
懐かしくも新しいボカロを改めて聴いてみてはいかがでしょうか。
粘着系男子の15年ネチネチ家の裏でマンボウが死んでるP

家の裏でマンボウが死んでるPさんの独特な世界観が詰まった楽曲『粘着系男子の15年ネチネチ』。
15年間にわたって一人の女性に執着し続ける男性の物語を、ユーモアと切なさを織り交ぜながら描いています。
聴く人の心に深く残る印象的な歌詞とキャッチーなメロディーが特徴ですよね。
大切な存在を失ってしまった経験がある方や、いちずな恋に悩む方にぜひ聴いてほしい一曲です。
切ない恋心を抱えている時に聴くと、共感と癒やしを感じられるかもしれませんね。
なりすましゲンガーKulfiQ

軽やかなメロディーに込められた切ない思い。
ボカロPのKulfiQさんが手がけた楽曲で、2012年1月に公開されました。
ギターロックなサウンドアレンジに、影のある世界観を組み合わせた作品です。
自己否定的な思考や、他者との比較による劣等感といった現代人の抱える葛藤を描き出しています。
ボカロファンの間で長年愛され続け、2022年には「マジカルミライ 10th Anniversary Live」でも披露。
ぜひまた聴いてみてください!
【流行】昔よく聴いた・懐かしいボカロ曲まとめ(81〜90)
from Y to YジミーサムP

失恋をして悲しいとき、これほど刺さる曲はそう簡単にはないんじゃないでしょうか。
ボカロシーン初期をけん引した存在の1人、ジミーサムPさんによる楽曲で、2009年に発表されました。
歌詞につづられているのは大切な人との別れの心情なのですが、サウンドアレンジに明るさがあるからか、聴き終わりはすっきりとした気分になれます。
曲後半の感情的な展開がまたいいんですよね……。
後ろ向きな考え方から立ち直りたいとき、この曲が助けになってくれるかもしれません。
ミラクルペイントOSTER project

明るい雰囲気に笑顔になってしまう、ビッグバンドジャズなボカロ曲です!
ふわふわシナモン名義でも知られるOSTER projectさんによる楽曲で、2007年11月にリリースされました。
イラストを描いてくれる友人への感謝が込められた作品で、ハッピーな気持ちが曲調と歌詞から伝わってきます。
ウォーキングベースと軽やかなピアノにノリノリになっちゃうんですよね。
「初音ミクがスキャットする」という手法も当時、珍しい調声でした。
ワンダーラストsasakure.UK

『トンデモワンダーズ』『フューチャー・イヴ』なども手がけた、ボカロシーンの第一線で活躍し続けているボカロPの1人、sasakure.UKさんによる楽曲で、2009年2月に発表されました。
予想できない曲展開とチップチューンを入れ込んだ前衛的なサウンドが特徴的な作品です。
このころからすでに「sasakure.UKさんの音楽」って感じで良いですよね。
発表から時間がたった今でも「新しい」と思えてしまいます。
2019年にリメイク版が投稿されていますので、まだの方はぜひ!
鎖の少女のぼる↑P

TKサウンドにも通じる洗練されたエレクトリックチューンです。
『白い雪のプリンセスは』『ショットガン・ラヴァーズ』でも知られるボカロP、のぼる↑さんによる楽曲で、2009年に発表されました。
「自分らしく、自分のために生きたい」という意志が投影された歌詞は、切なさの奥に力強さが感じられる仕上がり。
そのメッセージ性が曲の終わりに向かって盛り上がっていく展開と合わさり、胸が熱くなります。
2019年に発表されたリアレンジバージョンもぜひ聴いてみてくださいね。