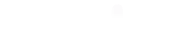【保育】8月の製作。夏に作りたいかわいいアイデア
暑くなる8月には、保育園、幼稚園でも室内で過ごすことも多くなります。
水遊びやプールでも涼しめますが、1日中は入りませんよね。
そこで、こちらでは夏にピッタリの涼しさを感じられる製作や遊びを紹介しています。
子供たちが喜ぶ楽しいアイデアがいろいろありますよ。
材料も廃材や100均で手に入るものがいっぱいあるので、手軽に保育に取り入れてみてくださいね。
ぜひ、こちらを参考にして、涼しい夏の製作を子供たちと楽しんでください!
子供たちが作ったものは作品として扱うため、文中では「制作」と表記しています。
- 【2歳児】8月に楽しみたい製作アイデア!夏らしいモチーフや技法を取り入れよう
- 【保育】海モチーフの製作アイデア!壁面から立体工作まで
- 【5歳児】8月の製作アイデア
- 1歳児向け!8月にオススメの製作アイディア
- 【4歳児】7~8月に年中児と作りたい!夏を感じられる製作遊び
- 【保育】8月の遊び。夏を楽しむ感触遊び、製作、歌、手遊びなど
- 【4歳児】8月にオススメ!製作アイデア。さまざまなモチーフを楽しもう
- 【保育園】夏祭りにオススメ!ゲームの手作りアイデアまとめ
- 【本日の工作】本日オススメの保育に役立つ楽しい工作のアイデア!
- 【保育】夏にぴったりの楽しい製作アイディアや製作遊び
- 【保育】8月の壁面アイデア
- 【保育】夏の壁面アイデア。たのしい夏の製作遊び
- 夏だから楽しい子どもの遊び。保育&おうちでマネしたいアイデア
【保育】8月の製作。夏に作りたいかわいいアイデア(81〜90)
Tシャツ
夏の清々しさを感じられるアイデアとして、Tシャツ型の壁面飾りを紹介します。
こちらは画用紙をTシャツの形にカットした紙に、模様を付けるという内容。
野菜ハンコやヤクルトの容器を使えば、手軽に楽しく取り組めそうです。
完成したTシャツは、干してある洗濯物のように並べて飾ります。
するとなんとなく温かい日差しや、吹き抜ける風を連想させてくれます。
または、虹や太陽、海に関係のある飾りを組み合わせるのもありです。
すずらんテープのくらげ
ユラユラとした見た目がかわいらしい、すずらんテープのくらげを紹介します。
こちらは、作る工程も楽しいアイデアです。
まず用意するのは、プラスチック容器とスズランテープ。
容器をフタとカップに分け、それぞれをクラゲの体に見立てます。
次にスズランテープを割いていきます。
この工程は手遊びになりそうですね。
最後に容器とテープを組み合わせたら完成です。
風が吹くとテープがなびくので、風鈴のような雰囲気もあります。
見ると涼しさを感じられそうです。
ちぎり絵のやどかり
海に行くと、磯や砂浜で見かけることのあるやどかり。
そんなやどかりをちぎり絵で作ってみるのは、いかがでしょうか。
やどかりの大切なおうちである貝殻の形に切った画用紙に、細かくちぎったお花紙をランダムに貼っておうちをデザインしていきます。
お花紙をちぎって貼る作業は、子供たちにおこなってもらいましょう。
できたら画用紙で切り出したやどかりのあたまやハサミと組み合わせて、完成です!
目などの顔のパーツは、丸シールで作るのもいいでしょう。
にじみ絵しろくまパンツ
暑いのが苦手なしろくまも、少しは夏を楽しみたいと思っているかもしれませんよね。
そんなしろくまに、少しでも夏気分を味わってもらうために、かわいいパンツを作ってあげましょう!
パンツの形に切り出した画用紙を霧吹きでぬらし、多めの水で溶かした絵の具を何色かのせてにじみ絵にします。
色が乾いたら、しろくまの形に切り出した画用紙、目や口などのパーツと組み合わせれば完成です!
目や口などは、後から子供たちにクレヨンなどで描いてもらうのもいいかもしれませんね。
カニの手型アート
子供たちにも参加してもらって、夏らしい壁面飾りを制作!
両手をパーにした状態で手首部分をくっつけたそのシルエットがまるでカニ、という着想から生まれたユニークなアイデアの飾りです。
子供たちの手形を取ったら切り出して、シンメトリーになるよう配置。
中心辺りに目を貼り付け、親指付近にハサミをつければ完成!
目がくりくりなのがかわいらしいんですよね。
照りつける太陽、吹き抜ける風……夏の海辺がイメージできる、さわやかな壁面飾りです!
スタンプでとうもろこし
子供たちが大好きなトウモロコシを、夏の制作モチーフにしてみてはいかがでしょうか。
梱包素材のプチプチを使ったスタンプと、段ボールを使ったスタンプ、どちらもオススメですよ。
土台のトウモロコシと葉っぱは、色画用紙で前もって作っておきましょう。
綿を丸めてプチプチで包み、輪ゴムで留めたスタンプと、段ボールをくるくる丸めて、テープで留めたスタンプ。
どちらも黄色い絵の具をインクにして、ポンポンと自由に押す感覚を楽しんでくださいね!
【保育】8月の製作。夏に作りたいかわいいアイデア(91〜100)
ビー玉転がしできんぎょがにげられない
お祭りなどでよく見かける金魚。
逃げてしまわないように、しっかり袋に入れてあげないといけませんね。
ということで、袋の中で元気に泳ぐ金魚の工作をしてみましょう。
涼しげな水の中を表現する意味で、白い画用紙の上に絵の具をつけたビー玉を転がして、模様をつけていきます。
そこに、画用紙で切り出した金魚を貼って完成!
指スタンプで、海藻などを描くのもオススメです。
子供たちにはビー玉を転がす作業や、指スタンプを使う工程をおこなってもらい、画用紙の切り出しやパーツののり付けは先生がおこなうようにしましょう。