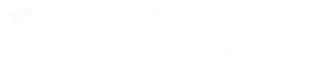親子向け室内ゲーム 体や頭を使ったたのしい遊び
親子で楽しめる室内ゲームを集めました。
道具がなくても遊べるわらべうたや遊びうた、こどもたちが思いきり体を動かせる運動ゲームなど。
保育現場や小学校での親子レク、おうちでの日常遊びに大活躍するゲーム・遊びが盛りだくさんです!
「こどもと大人がふれあえる簡単な遊び」を探している方は、よければ参考にしてみてくださいね。
めいっぱい楽しんでこどもたちは大喜び!
そして大人にとってもよい運動不足解消になると思います!
- 【親子レク】親子で楽しむレクリエーション、ゲーム。運動会にも
- 【子供会】簡単で楽しい室内ゲーム。盛り上がるパーティーゲーム
- 【小学校】すぐ遊べる!低学年にぴったりの室内レクリエーション
- 【小学生向け】道具なしで遊べる楽しい室内遊び
- 【子供向け】室内で遊べる!大人数のレクリエーションやゲーム
- 親子のふれあい遊び。保育・親子参観で人気のたのしい遊び
- 【子供向け】盛り上がるクラス対抗ゲーム。チーム対抗レクリエーション
- 小学1年生から6年生まで楽しめる遊びアイデア【室内&野外】
- 小学生のお楽しみ会が大盛り上がり!室内ゲームのアイデア集
- 室内で楽しめる簡単なレクリエーション・ゲームまとめ
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 親睦会・懇親会で盛り上がるゲーム
- 【幼稚園・保育園】お楽しみ会のゲーム・出し物
親子向け室内ゲーム 体や頭を使ったたのしい遊び(21〜30)
乳児さんも楽しめる!室内あそび
@nexus_official5♬ Cute heartwarming BGM(1490583) – sanusagi
寒い日でも元気に室内で楽しめる4種類の遊びをご紹介いたします。
まず「ハイハイレース」親子で声をかけながらゴールを目指します。
シンプルながら、笑顔あふれる展開で大盛り上がり。
次に「動物の真似っこゲーム」うさぎのぴょんぴょん跳びや象の鼻の動きを真似して体を思い切り動かしましょう。
「バランス遊び」は床に紐を置いてその上歩きます。
紐に触れないようにまたいではねる動きは足の力を育てます。
最後は「新聞やチラシを使った遊び」指先を使って破った紙は丸めてボールにし、別な遊びに使用できます。
どれも準備が簡単で、寒い日のおうち時間にぴったりです。
ブロックス

カラフルなピースをボードに置いて、自分の陣地を広げていく戦略系ボードゲーム「ブロックス」の紹介です。
ルールはシンプルで、同じ色のピースを角でつなげながら置いていき、他のプレイヤーの動きを考えながら陣地を広げるのがポイント。
置き方ひとつで戦略が大きく変わるため、子供から大人まで頭を使って楽しめます。
ピースの形や置き方を工夫することで、思い通りのスペースを確保したり、相手の進行を阻止したりする駆け引きが生まれ、ゲームが白熱します。
短時間でも遊べるため、家族や友だちと一緒に楽しみやすいので、ぜひ遊んでみてくださいね!
ポーズ合わせゲーム

親子で楽しめる、ポーズ合わせゲームを紹介します。
お題を決めて「せーの」の合図でお題のポーズをとりましょう。
親子でポーズがそろえばチャレンジ成功です!
ポーズがそろわなかった場合は再び同じお題にチャレンジしても盛り上がりそうですね。
親子でどれくらい気持ちが通じ合っているかが試されるユーモアのあるゲームですよ。
人数を増やしてやっても楽しめるかもしれませんね。
い想像力を高めながらお題をクリアして楽しんでくださいね。
小学生におすすめ!汗をかけるゲーム5選

「タッチでダッシュ」「フェイント鬼ごっこ」「マーカー鬼ごっこ」「計算リレー」「じゃんけん競争」。
この5つの運動遊びにはどれも走る要素があり、室内で体をたっぷりと動かせます。
また、リレー形式でビブスを拾い書いてある数字を足して20以上になったらゴール、マーカーを使って相手をうまく誘導し隙間を走り抜けるなど、体のみならず頭を使う要素も!
単純な動きだけでは飽きてしまう子供たちでも、きっと夢中になれるのではないでしょうか。
ことばでリズムあそび

語彙力やリズム感で体を動かしながら楽しめる、ことばでリズムあそびは瞬発力や考える力といったものを鍛え楽しめるゲーム遊びです。
音を聞きながら言葉を合わせていきましょう。
どんな言葉でも良いですが、リズムから外れないように言っていくのがポイントです。
初めは簡単なリズムからスタートしていき、少しずつ難易度を上げていくのがポイントです。
慣れてきたら、手拍子をつけながらゲームに参加するとさらに盛り上がるかもしれませんね。
子供から大人まで楽しめる数当てゲーム

コミュニケーション力と観察する力がポイントになってくる数当てゲームは大人数で楽しめるゲームです。
ルールはシンプルで「せーの」の掛け声に合わせ数字の数を順番に言っていきましょう。
立つか座るかを掛け声に合わせて個人で決めていきます。
言った数字と立っている数が合わなければそこでゲーム終了です。
相手の様子を観察しながら、ゲームで言う数字を考えていくため、緊張感とプレッシャーに負けないことがポイントです。
ぜひ挑戦してみてくださいね。
おうちでも遊べる運動遊び

外遊びができない時も体を動かしたい!
そんな時はおうちで運動遊びを楽しみましょう。
乳幼児の子ならベビーマッサージやふれあい遊び、年少さん〜小学生くらいの子なら、スパイごっこで宝探しをしたり、テーブル卓球を楽しんでみるのはいかがでしょうか?
スパイごっこではお部屋の中に障害物を作ったり、宝の地図を用意すると盛り上がりそう。
テーブル卓球は、ネットにティッシュ箱、ラケットにお鍋のフタ、ボールにスーパーボールなど、おうちの中にあるものを代用して遊べます。