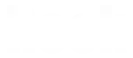【1970年代】黎明期を駆け抜けた日本のロックの名曲&ヒット曲
日本のロック・ミュージックの礎を築いた時代といえば、やはり1970年代ではないでしょうか?
この時代に出てきたミュージシャンやバンドは、後の邦楽ロックに多大な影響をもたらしました。
今回はそんな1970年代を彩った、至高の名曲を紹介しています。
誰もが知っている有名なバンドから、知る人ぞ知るミュージシャンまで、幅広くピックアップしているので、ぜひご自身に合った楽曲を見つけてみてください。
それではごゆっくりとお楽しみくださいませ!
- 【1970年代】邦楽ヒットソング集。懐かしの日本の名曲
- 【日本のロックの夜明け】70年代邦楽ロックバンドのデビュー曲まとめ
- 懐かしくて新鮮!?1970年代、80年代の懐かしの邦楽ロックの名曲
- 70年代の懐かしのヒット曲、名曲まとめ
- 60年代伝説の邦楽ロックの名曲・ヒット曲
- 1970年代懐かしの邦楽ヒット曲。アイドルと歌謡曲の黄金時代
- 70年代は洋楽ロック黄金期!おすすめの名曲・ヒット曲
- 1970年代の邦楽男性アーティストのデビュー曲
- 心に響く、昭和の泣ける名曲
- 【70年代名曲】CMに使われた洋楽まとめ
- 70年代の邦楽女性アーティストのデビュー曲まとめ
- 【かっこいいバンド】日本を代表するロックバンド
- 懐かしすぎて新しい?高度経済成長期の日本を彩った昭和レトロの名曲
【1970年代】黎明期を駆け抜けた日本のロックの名曲&ヒット曲(21〜30)
Double Dealing Woman紫

沖縄が日本に返還される以前に結成された、沖縄出身のバンドです。
ベトナム戦争がまだ終結してなかった1960年代に多数存在した、米兵向けのクラブで演奏することで腕を磨いていたそうです。
Double Dealing Womanは1976年に発売された紫のファーストアルバム「紫」の1曲目に収録されています。
ハードながら疾走感のあるサウンドと、ネイティブな雰囲気の英語の歌詞がとてもマッチしており。
当時日本バンド扱いされていなかったという事実もわかるような気がします。
美術館で会った人だろP-MODEL

独創的なプログレッシブ・サウンドで現在でも多くのマニアから愛されているバンド、P-MODEL。
このバンドは現代のプログレッシブの王様である、平沢進さんが所属していたバンドです。
活躍していたのは1980年代から2000年代ですが、実は彼らのデビューは1970年代なんですよね。
こちらの『美術館で会った人だろ』はそんなP-MODELが世間で認知されるようになったキッカケの楽曲です。
当時の邦楽ロックにはなかった独創的なサウンドは、スタイルが多様化した現在でも圧倒的な存在感を放っています。
【1970年代】黎明期を駆け抜けた日本のロックの名曲&ヒット曲(31〜40)
地獄の天使LAZY

1970年代はアイドル・バンドがブームでした。
しかし、アイドルということもあって、どうしても実力に欠けるという風潮はありました。
そんな時代のなか、「あのバンドだけは違う」と言われたアイドル・バンドが、こちらのレイジーです。
レイジーのボーカルを務めていたのは、アニソンを代表する歌手であり、現在はJAM projectのメンバーとして世界的に活躍している影山ヒロノブさんです。
彼の圧倒的な歌唱力を味わえる、こちらの『地獄の天使』はレイジーのなかでもハードなナンバーなので、実力派のアイドル・バンドを聴いてみたい方は要チェック!
銃爪ツイスト

日本のハードロックを作り上げたといっても過言ではないバンド、ツイスト。
世良公則さんのバンドですね。
1970年代後半から1980年代にかけて大活躍したツイスト。
彼らの魅力は音楽性にもあるのですが、なんといっても世良公則さんの圧倒的な歌唱力が印象的でしたね。
ブラックミュージックをしっかりと聴いているからか、他のバンドのボーカルとは歌唱力の次元が違いました。
こちらの『銃爪』はそんなツイストの名曲で、現在でも多くのメディアで使用されているハードロック・ナンバーです。
ランブリン・ライダーめんたんぴん

日本のグレイトフルデッドと呼ばれたバンドです。
当時では珍しいツインドラム、ツインリードギターにボーカル、ベースというメンバー構成でした。
ランブリン・ライダーはめんたんぴんの初期のシングルです、疾走感あふれる演奏が今も色あせず、実に爽快な気分を味あわせてくれます。
2,014年に再発売されたアルバム「MENTANPIN SECOND+1」のボーナストラックとして収録されています。
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカDOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND

後に作曲家として大成した宇崎竜童が在籍していたバンドです。
バンド名はサディスティック・ミカ・バンドに対抗して長いバンド名をつけようと宇崎竜童が考えたバンド名だそうです。
港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカは1975年に発売された4枚目のシングルで、ミリオンセラーに達し、同年の紅白歌合戦に初出場したきっかけとなった程の有名曲です。
実は最初はB面曲でした。
タイム・トラベル原田真二

どちらかと言うとポップ色の強いイメージですが、彼も当時、ツイスト、Charと並ぶ「ロック御三家」と呼ばれていました。
佐野元春がブレイク前に、感性が原田真二にそっくりと評されていた話もあります。
そういう意味では、彼も後の日本のロック界に多大な影響を与えたと言っていいと思います。
タイム・トラベルは人気絶頂時の1978年に発売された4枚目のシングルです。
日本の泥臭さを全く感じさせないポップなメロディーラインと軽快なリズムが絶妙に日本語に絡みあった名曲です。