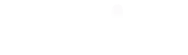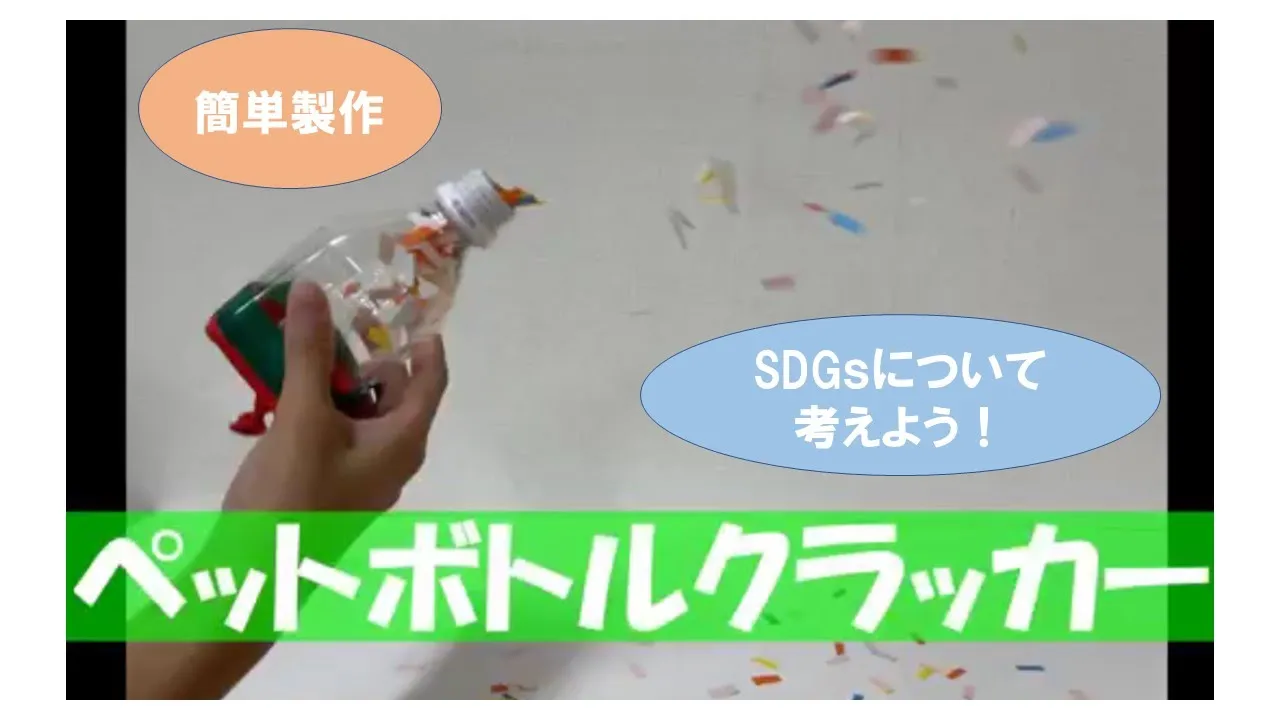【保育】SDGsを遊びながら学べるアイデア
SDGsを保育にも取り入れたいと考える先生は多いのではないでしょうか?
保育園や幼稚園では楽しく学べることが大切なので、どのように取り組もうか悩みますね。
そこで、乳幼児の時期でも楽しくSDGsの目標を感じたり考えたりできるアイデアを集めました。
先生も一緒に楽しく取りくめば、SDGsの目標が子どもたちにとって身近で当たり前のものになっていくでしょう。
未来を担う子どもたちと一緒に楽しく取り組みたいですね。
【保育】SDGsを遊びながら学べるアイデア(1〜10)
ペットボトルクラッカー

ペットボトルと風船を使ってクラッカーを作ってみてはいかがでしょうか?
一度作れば繰り返し利用できるクラッカーはゴミを減らせるため、環境にも優しいといえます。
中に入れる紙片は誤飲の恐れがあるため、乳児クラスでは扱わないようにしましょう。
お誕生日会などのお祝いや、お花見や夏祭りなどのイベントの余興として取り入れるのもいいですね!
子供たち一人ひとりが自分用をクラッカーを作れれば、きっとお気に入りのおもちゃになることでしょう。
【5歳~】手話遊び

5歳児を中心に手話遊びを取り入れてみませんか?
普段話している日本語以外にもコミュニケーションの方法があることを学ぶのは、SDGsの10「人や国の不平等をなくそう」にも発展します。
まずは園児にとって大切な挨拶を、手話でおこなってみましょう。
先生や友達と手話でコミュニケーションを楽しめば、その後の学ぶ意欲にもつながりますね。
50音表を使って自分の名前をどのように表現するのか、先生や友達と一緒にやってみるのもおすすめです!
【木育】木で遊ぼう

木で使ったおもちゃを使ってみんなで遊びましょう。
木の素材に触れることや、自然を活かしたおもちゃを使うことはSDGsの4「質の高い教育をみんなに」につながります。
また、やわらかい素材のブロック遊びは音が静かなぶん、災害時の避難所でも子供に遊びを提供できます。
日々変化の多い現代を生きる子供たちにどのような遊びが提供できるのか、大人が考えるのも大切ですね。
夢中になって子供たちが遊べるようなおもちゃを意識的に取り入れましょう。
かるた遊び

5歳児を中心にかるたを製作してみましょう。
SDGsの取り組みに発展させるポイントは、かるたをSDGsに沿った内容にすること。
先生が考えるのももちろん、子供たちの発想を活かすと面白いアイデアが生まれそうですね!
かるたを作る前にSDGsについて紙芝居や本を使って学ぶ機会をたくさん作っておくとスムーズですよ。
イラストも子供たちに描いてもらいましょう。
完成したかるたは園の完全オリジナル!
子供たちも愛着を持って遊んでくれますね。
ゴミ回収係

ゴミの回収や分別を子供たちと一緒に取り組んでみてはいかがでしょうか?
普段ならゴミ箱に捨てるだけのゴミですが、回収したり分別したりといった手間を学ぶことで、ゴミについて自然と興味が持てますね。
SDGs12の「つくる責任つかう責任」にもつながります。
また、ゴミの分別からリサイクルについて興味を持つきっかけにもなります。
子供たちにとって身近な「ゴミ」だからこそ、小さなころから興味を持つのは大切なのではないでしょうか。
園で学んだことをおうちでも発揮して、ゴミ捨てや分別のお手伝いをしてくれるかもしれませんね。
パネルシアター

SDGsを子供たちに楽しく学んでもらうために、パネルシアターを導入してはいかがでしょうか?
わかりやすいキャラクターを使うことで、SDGsが子供たちにとって親しみやすいテーマになります。
子供たちに伝えたいSDGsのテーマを決めてから製作に取りかかるとスムーズでしょう。
普段の保育に取り入れたり、行事としておこなってみたりと、パネルシアターならさまざまな場面で活躍する教材になりますね。
地球やゴミといった生き物以外の題材もキャラクターにできるのもパネルシアターの魅力の1つです。
新聞紙遊び

本来は読んだら捨てるはずの新聞紙を、遊びに取り入れましょう。
新聞紙遊びは身体を使うものから想像力を発揮できるものまで、さまざまな取り組み方ができるのが特徴です。
大人が用意するのは新聞紙とのりやテープなど、必要最低限の材料。
あとは子供たちの発想を活かせるように見守りながら遊びましょう。
すてきな作品に仕上がったらおうちに持って帰るのもいいですね。
身体を動かす遊びに活かせば、室内遊びも大変身!
子供たちが「またやりたい!」と言う遊びになるでしょう。