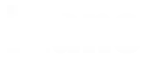【ピアノ発表会】小学3年生にオススメの名曲・人気曲を厳選!
日頃の練習の成果をおうちの方やお友達に披露するピアノ発表会。
「お気に入りの曲」「身につけたテクニックを発揮できる曲」「ピアノ教本に載っていないようなユニークな曲」といったさまざまな基準で選曲するなかで、先生と生徒さん、そして保護者の方皆が納得できる曲を選ぶのはなかなか難しいものです。
そこで本記事では、選曲のヒントにしていただけるよう、ピアノ発表会にオススメの作品をピックアップ!
今回はとくに小学校3年生くらいのお子さんにオススメの作品を選びましたので、発表会曲選びにお悩みの方はぜひ参考にしてください!
- 【小学生2年生向け】ピアノの発表会で弾きたい!おすすめの名曲&有名曲
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【小学校低学年向け】ピアノコンクールで入賞しやすい曲を一挙紹介
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【ピアノ発表会】小学生・中学年におすすめのクラシックの曲を厳選
- 【ピアノ発表会】女の子にピッタリの中級レベルの曲をピックアップ!
- 【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【ピアノ発表会】小学生・高学年にオススメのクラシック曲を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
【ピアノ発表会】小学3年生にオススメの名曲・人気曲を厳選!(21〜30)
ジュピターGustav Holst

20世紀イギリスを代表する作曲家グスターヴ・ホルストが手掛けたオーケストラ組曲『惑星』の中の1曲。
1914年から1917年にかけて作曲された本作は、壮大さと生命力に満ち溢れた曲調で多くの人々を魅了してきました。
美しいメロディと豊かな響きは、小学3年生のお子さまでも弾いていて楽しくなることでしょう。
普段電子ピアノで弾いている方は、グランドピアノで弾くことで響きの素晴らしさを感じられるので、発表会を通してホールやグランドピアノの楽しさを感じられるとよいですね。
テンポもゆったりしていて難しいリズムもないので、ピアノを始めて間もないお子さまにもピッタリです。
真夜中の火祭り平吉毅州

独特なリズムで勢いよく進行していく、情熱的な雰囲気がかっこいい!
『真夜中の火祭り』は、平吉毅州さん作曲のこどものためのピアノ曲集『虹のリズム』に収録されています。
コンクールの課題曲としても取り上げられる人気の高いこの曲は、激しさや力強さを感じさせる、元気なお子さんにピッタリの楽曲!
2拍子に感じる部分と3拍子に感じる部分が入り混じっていたり、左手の休符の入り方が複雑だったり、練習しがいのある要素が多く含まれています。
発表会でかっこよく弾きこなすために、まずは片手でリズムをしっかり把握することからはじめましょう。
波のアラベスク三善晃

きらめく水面を思わせる優雅な旋律が魅力的な、日本人作曲家三善晃の作品です。
1987年に公開されたピアノ小品集『海の日記帳』に収録されているこの楽曲は、アラビア風の装飾模様を意味するタイトルの通り、繊細な音の動きが絶え間なく続いていく情景が目に浮かびます。
嬰ト短調とロ長調が巧みに行き来する響きは、明るさの中にふと影が差すような、少々大人びた切なさを描き出します。
ピティナのコンペティション課題曲にもなる本作は、抑制の効いたペダルワークと豊かな表現力が求められる、まさに聴き映えすること間違いなしの一曲!
憧れの曲を感情が豊かに弾きこなしたい、そんな小学生や中学生のお子さんにこそ挑戦してほしい作品です。
小さなロマンスCornelius Gurlitt

19世紀のドイツを代表する作曲家、コルネリウス・グルリットが贈る、甘美な1曲。
ロマン派時代の特徴を色濃く反映しつつ、教育的要素も兼ね備えた楽曲です。
アンダンティーノのゆっくりとしたテンポで進行し、まるで小さな恋心が芽生えるかのような優しさに満ちています。
右手のメロディーが柔らかく響き、左手の伴奏が繊細にサポート。
シンプルながらも豊かな表現力を持つ曲調は、ピアノを学ぶ子どもたちの感性を育むのにピッタリ。
発表会曲としても最適で、聴く人の心を温かく包み込むことでしょう。
蝶々Henri Van Gael

19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したベルギーの作曲家、アンリ・ヴァン・ゲールが手掛けた優美な小品。
蝶が舞う様子を音楽で表現した本作は、軽やかで親しみやすい旋律が特徴です。
前半のイ短調から後半のイ長調へと移り変わる二部形式で構成され、蝶の儚さや美しさが繊細に描かれています。
1846年生まれのゲールは、生涯で約200曲もの作品を残しました。
ピアノ発表会でよく演奏される定番曲として知られ、優雅な旋律が女性や若いピアニストに人気です。
感情が豊かな表現が求められるため、技術向上だけでなく表現力も磨きたいお子さまにピッタリの1曲といえるでしょう。
ワルツ 作品38-8Muzio Clementi

18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍したムツィオ・クレメンティ。
本作は、クレメンティが1798年に発表した『12のワルツ』コレクションの中の1曲です。
軽快なリズムと華麗なピアノの旋律が特徴的で、社交ダンスの雰囲気を持ちながらも、クラシック音楽としての美しさが際立っています。
明るく楽しい雰囲気の曲を探しているお子さまにピッタリ。
クレメンティの技巧的な要素と、ダンス音楽としての魅力を同時に味わえる一曲となっています。
右手の音階が転ばないよう、ゆっくりのテンポから指の一つひとつを丁寧に弾く意識で練習してみてくださいね。
ソナチネ 第1番 ハ長調 Op.20-1 第1楽章Friedrich Kuhlau

多岐にわたるジャンルで200以上の作品を残したドイツの作曲家、フリードリヒ・クーラウの『ソナチネ 第1番 ハ長調 Op.20-1』は、その明確な構造と旋律の美しさで、練習曲や発表会曲として親しまれている作品です。
本作は、冒頭がヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの『ピアノソナタ 第16番 ハ長調 K. 545』と似ていることでも知られていますが、その親しみやすいメロディと曲調は、発表会の舞台でピアノを思い切り楽しみたい小学3年生のお子さまにもピッタリ!
メトロノームを使った練習でテンポとリズムの正確さを保ちつつ、強弱記号や発想記号にも注目して表情が豊かな演奏を心がけましょう。