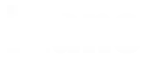6歳といえば、卒園、小学校入学を迎える節目の年齢!
手や腕まわりを含め体つきがしっかりしてきて、ピアノの打鍵も力強くなってくるこの時期のピアノ発表会では、タッチの変化で音色を変えたり、表情を変えたりするテクニックも身につけられる作品がオススメです。
そこで今回は、6歳頃のお子さまにピッタリのピアノ曲の中から、ピアノの発表会映えする作品を厳選してご紹介します。
発表会の選曲では、テクニックや表現力の成長につながるだけでなく、楽しんで演奏できる曲を選ぶことが重要!
ぜひ、お子さま、生徒さまのお気に入りの1曲選びにお役立てください。
- 【5歳児向け】ピアノ発表会にオススメの楽曲をピックアップ!
- 【ディズニーソング】6歳のピアノ発表会で弾きたい名曲をピックアップ
- 【幼児のピアノ曲】発表会で弾きたい!華やかなおすすめ作品を厳選
- 【小学生2年生向け】ピアノの発表会で弾きたい!おすすめの名曲&有名曲
- 【祝!発表会デビュー】初めてのピアノ発表会におすすめの曲を紹介
- 【ピアノ発表会】男の子におすすめ!かっこいい&聴き映えする人気曲を厳選
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
- 【5歳のピアノ発表会】ディズニーの名曲を弾こう!おすすめ作品を厳選
- 【4歳児向け】ピアノ発表会におすすめの楽曲をピックアップ!
- 【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【ピアノでディズニーの名曲を】発表会にもおすすめの簡単な楽曲を厳選
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
【6歳児向け】ピアノ発表会で映えるおすすめ楽曲をピックアップ!(1〜10)
となりのトトロ久石譲

ジブリ作品を担当し、いくつもの名曲を作り上げてきた日本の作曲家、久石譲さん。
クラシックやピアノ曲に詳しくない方でも知っている、非常にポピュラーな作曲家ですね。
そんな久石譲さんの作品のなかでも、特に6歳児にオススメしたい作品が、こちらの『となりのトトロ』。
小学校にピッタリな明るい曲調が印象的な作品で、一定のテンポのため、非常に弾きやすい特徴を持っています。
そういった作品でありながら、裏拍も学べる楽曲なので、良い経験にもなるでしょう。
ギャロップDmitri Kabalevsky

ロシアの作曲家・ピアニストであるドミトリー・カバレフスキー。
カバレフスキーはこども向けの作品を多く残していますが、どれも優れた作品として定評のある作曲家です。
「ギャロップ」とは「馬の駆け足」という意味で、19 世紀中頃流行した急速で軽快な舞曲のことを指します。
前向きなテンポと左手の刻みが、まるで馬が走ってひづめを鳴らしているかのようですよね。
右手のメロディーにある跳躍がとても印象的です。
冒頭と中間部の強弱の差がわかるよう、変化をたっぷりつけて演奏しましょう。
こどものためのアルバムより「ポルカ」Louis Heinrich Köhler

発表会で弾むように楽しい気持ちになれる曲をお探しではないでしょうか。
19世紀に教育目的で編まれた全30曲からなるピアノ曲集、アルバム『Kinder Album, Op. 210』に収められた一曲です。
ポルカの軽快なリズムに乗って、まるで舞踏会でくるくると踊っているような情景が目に浮かびます。
この楽曲は、スタッカートで元気に、レガートで優雅にといった音色の変化を学ぶのにも最適です。
聴いている人も思わず笑顔になるような明るさがあるので、これから表現力を豊かにしていきたいお子さまが、発表会で輝く一曲としておすすめです。
パリの休日William Gillock

こどもでも演奏できるほどシンプルな楽曲構成でいくつもの名曲を作り上げてきたアメリカ出身の作曲家、ウィリアム・ギロックさん。
そんなギロックさんの作品のなかでも、特にオススメしたいのが、こちらの『パリの休日』。
幼少期からピアノを始めたのなら、一度は演奏することがあるといっても過言ではないほど、有名な作品ですね。
難易度としてはブルグミュラーの前半程度といったところでしょうか。
美しくかわいらしい旋律が非常に聴き映えするので、ぜひ発表会の参考に聴いてみてください。
ブルグミュラー25の練習曲 Op.100 第20番「タランテラ」Johann Burgmüller

南イタリアの情熱的な舞曲はいかがでしょうか。
毒蜘蛛に噛まれた毒を抜くために踊ったという逸話が元になっており、曲想もそれが表すかのような緊迫感と躍動感に満ちています。
6/8拍子の弾むリズムは、まるで主人公が必死に踊り続ける心臓の鼓動のようです。
中間部で一瞬明るい曲調に変わる部分で、どう気持ちを表現するかが演奏のカギとなるでしょう。
本作は、リズミカルでかっこいい曲に挑戦したいお子さまにぴったりです。
物語を想像しながら、情熱的な演奏ができるようになるといいですね!
1851年に公開されたヨハン・ブルクミュラーが作曲した練習曲集『25の練習曲 Op.100』の一曲です。
ブルグミュラー25の練習曲 Op.100 第2番「アラベスク」Johann Burgmüller

ヨハン・ブルクミュラーの練習曲集『25の練習曲 Op.100』から「アラベスク」は発表会で輝く一曲です。
この曲は、イスラム美術の装飾模様を思わせる軽やかでエキゾチックな雰囲気がとても魅力的ですね。
スタッカートで弾むリズムに乗って右手が駆け巡る様子は、まるで小さな冒険が始まるかのようです。
1851年にパリで出版された当時から愛されている本作は、指の独立性を鍛えながら音楽で物語を表現する楽しさを教えてくれます。
日本のコンクールでも課題曲としておなじみで、弾む音と滑らかな音の対比をくっきり表現できるかが演奏を生き生きとさせるカギとなるでしょう。
エチュード・アレグロ中田喜直

1956年に公開された楽譜集『こどものピアノ曲』に収められた、きらびやかで快活な作品です。
この楽曲の特徴は、弾むような16分音符が絶え間なく続く点で、まるで太陽の下を元気に駆け回る姿が目に浮かぶようです。
クライマックスのグリッサンドは虹をかけるような華やかさがあり、聴く人の心を一瞬で掴むことでしょう。
本作は、少し背伸びした曲に挑戦したいという意欲が芽生えた6歳のお子さまにおすすめです。
指を速く動かす技術を楽しみながら磨けるため、弾き終えた時の達成感は格別ですよ!