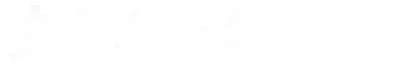【文化祭】プラネタリウムの手作りアイデア
子供から大人までみんなに人気のプラネタリウム。
文化祭の企画にぴったりですよね。
こちらでは。
自分たちでプラネタリウムを作るアイデアを紹介しています。
段ボールや布を使ってドームを作ったり、天井に星の絵を描くか、または今はプラネタリウムのキットがいろいろ売っているので、使ってみるのもオススメです。
学校にある道具を利用しながら、楽しく手作りして文化祭を盛り上げてくださいね!
みんなで観察すれば、ステキな体験になるはずです。
【文化祭】プラネタリウムの手作りアイデア(1〜10)
段ボールのドーム

プラネタリウムといえば、星座の光を投影する道具も重要ではありますが、投影する場所も重要なポイントですね。
ドーム状の場所に光を映すことで、空の広がりを感じさせる、立体的なプラネタリウムが完成します。
そして文化祭における教室の四角い空間にドームを作るには、ダンボールを組み合わせたドームがオススメですよ。
半球を分割したようなパーツをダンボールで作り、最終的にそれを合体させてドームに仕上げていきます。
一度の収容人数は限られますが、ダンボールの強度を考えて、数人が入れるくらいのドームにするのがよさそうですね。
段ボールと布のドーム

文化祭では、教室という限られた空間をうまく活用することが重要です。
プラネタリウムはドーム状の場所に光を投影することが大切なので、教室内でどのようにしてドームを作るのかをしっかりと考えましょう。
教室にあるイスや机を重ねて、ドームの高さを確保して、そこに支柱で枠を作り、暗幕をかけてドームを完成させるという手順がわかりやすいかもしれませんね。
暗幕を使用することで、投影した光がはっきりと映るということも重要なポイントです。
収容できる人数は限られてしまいますが、小さめにドームを仕上げることで正確なドームが作りやすく、立体感がしっかりと感じられる内容ですね。
エアードーム

大きな袋のようなものに空気を送り込み、膨らんだ時にドームの形状が完成するといった内容です。
空気を入れていない状態だと、たたんで収納しやすいというところも重要なポイント、点検をしっかりとおこなえばその後も使っていけますね。
素材がやわらかい布なので、大きなプラネタリウムを安全に展開できるということにも注目ですね。
外からの見た目もやわらかい雰囲気なので、プラネタリウムにお客さんをむかえようという気持ちも伝わるような形ではないでしょうか。
空気の入れ方や、広げ方のバランスを調整して、美しいドームにしていくことが重要かと思います。
【ペーパー工作】プラネタリウムをつくろう!

プラネタリウムは、実際の星空を投影して解説していくといった、学問のひとつとしてのイメージが強いかと思います。
そんな固いイメージから外れて、プラネタリウムの光を投影することに注目して、室内の装飾として使用するのはいかがでしょうか。
厚紙で多面体を作り、そこに星を意識した穴をあけていく、中央に光源を配置することで、室内に光が投影されるといった内容です。
穴の部分に内側からフィルムを貼るなどの工夫を加えると、カラフルな見た目に仕上がり、より華やかな空間が演出されるのではないでしょうか。
家庭用プラネタリウム「Home star」

文化祭でプラネタリウムを披露するには、星の光を正確に再現する機会が欠かせない要素かと思います。
市販されているプラネタリウムの機械は、正確な星空が記録されており、その種類もさまざまなであるという点から、こちらを使ってクオリティを確保するのもよさそうです。
機械の出力によって適した広さが決められているので、それに合わせたドームを準備してプラネタリウムを進行しましょう。
販売されているものを使っているからこそ、どの星空を投影しているかの説明などが加えられると、プログラムとしてのクオリティも上がっていきそうですね。
【天文部】自作プラネタリウム映像

文化祭で披露するプラネタリウムは、クオリティにこだわるのも大切ではありますが、自分たちで作ったという事実も重要なポイントです。
資料を集める、それを映像として編集していくなど、プログラムの中に努力が見えるのも、感動的ではないでしょうか。
プロジェクターとカメラのレンズを工夫すれば、立体的な映像が作れますが、どのように映るのかを考えて進めていくことが重要ですね。
映像に解説を加えていくという定番の流れでもいいですが、どのように映像を作ったのかの説明を加えるのもおもしろいかと思います。
大人の科学マガジン「ピンホール式プラネタリウムの作り方」

プラネタリウムは、ドーム状の会場へと、夜空に広がる星座の形の光を投影する内容ですよね。
どのような形で光を投影するのかによって、夜空の広がりの演出や、その場の雰囲気も変化するため、機械にはしっかりとこだわりましょう。
中央に豆電球などの光源があり、光をかすかにとおすような素材でそれを囲むのがわかりやすいかと思います。
星空が描かれたフィルムのような素材に、光をあてるような内容なら、空の広がりが伝わりやすいのではないでしょうか。
中央の光源の強さによって、星の輝きやそこから受ける印象も変わるので、どの程度の光にするのかも重要なポイントです。