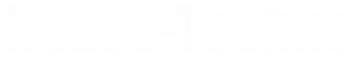ディープハウスの名曲。おすすめの人気曲
「落ち着いたハウスミュージックを聴きたい」「渋いクラシックを探している」「最新のアンダーグラウンドなディープハウスが聴きたい」そんなご要望にお答えするため、ディープハウスの人気曲、シーンのターニングポイントとなった名曲をリサーチしました。
当サイトに寄せられた音楽ファンの声を元に人気のものを選び、クラブDJの私がオススメする曲を新旧交えながらご紹介します。
基本的には、シーンの誕生から40年以上立つハウスミュージックですが根本は変わりません。
だからこそ根強いファンも多く、アンダーグラウンドシーンでは今でも人気があります。
どうぞご覧ください!
- ハウスミュージック名曲で踊る!世界を魅了し続ける代表曲たち
- ハウス・テクノの人気曲ランキング
- 美しきエレクトロニカ~オススメの名曲・人気曲
- 最新のハウスミュージック【2025】
- 【4つ打ちの魅力】ハウス・ミュージックの名盤。基本の1枚
- UKガラージ・2stepの名盤と代表曲を深掘り!ガラージ音楽の魅力を解説します
- 攻撃的ダンスミュージック。ハードコアテクノの名曲
- ドラムンベースの名曲。おすすめの人気曲
- 【2025】グルーヴハウスの魔力!グルーブ感炸裂の洋楽EDM名曲
- 【トランス】高揚感あふれる美しいおすすめの人気曲【2025】
- ソウルミュージックのレジェンドたち。名曲で振り返る歴史と魅力
- プログレッシブハウスの名曲。最新アンセム・フロアヒッツ
- 【初心者向け】ハウスミュージックの有名な海外アーティストまとめ
ディープハウスの名曲。おすすめの人気曲(31〜40)
OutbreakerLa Fleur

有機的なパーカッションと心に染みわたるギターが織りなす、深みのあるサウンドが印象的な一曲です。
スウェーデン出身のプロデューサー、ラ・フルールさんが手がけた本作は、静けさの中に秘められたエモーショナルな高揚感がクセになる、まさに大人のための癒やしのトラック!
元薬剤師という経歴を持つ彼女ならではの、緻密で洗練された音作りも非常に魅力的です。
この楽曲は2018年5月に公開されたEP『Outbreaker EP』に収録されており、穏やかな朝のムードに合うアンセムとしてファンに愛されています。
都会の喧騒を忘れさせてくれるような優しいグルーヴは、きっとあなたの心を解きほぐしてくれるはず。
休日の朝、少し贅沢な時間に浸ってみてはいかがでしょうか?
Love Letters From SicilyMatthias Meyer & Ryan Davis

ドイツのクラブシーンでそれぞれが確かな存在感を放つ、マティアス・マイヤーさんとライアン・デイヴィスさんの作品です。
クラシック由来のメロディセンスとDJならではの構築美が融合し、聴く者を深く引き込みます。
この楽曲は、まるで遠いシチリアの地から届いた手紙のよう。
歌詞はありませんが、壮大で詩的なサウンドが、手紙に込められたであろう切なさや温かい愛情といった複雑な心の機微を雄弁に物語ります。
2018年9月に公開され、イビサのフロアを熱狂させたというエピソードも納得の完成度!
一人静かに自分と向き合いたい夜、本作を聴けば内なる感情にそっと寄り添ってくれるのではないでしょうか。
Breath Of The SoulsNewman

2018年にリリースされ、世界中で高く評価されたニューマンこと、ポール・ニューマンさんの比較的最新の曲です。
美しいメロディにのせられた中東のボーカルと弦楽器の数々。
2018年はエスニックなサウンドが流行った年でもありました。
それはアンダーグラウンドだけではなく、EDMなどのメインストリームなどでも同じです。
さまざまな影響下の中でいち早くトレンドを盛り込んだディープハウス。
I’ll Be Your FriendRobert Owens

数々の名作を生み出した、シカゴハウスの名プロジェクトFingers Inc.。
ラリー・ハード、ロンウィルソンとともにハウスミュージックの歴史を切り開きました。
この曲はロバート・オーウェンズの中でももっとも人気の高いトラックです。
ハウスミュージックに特化したフェスティバルにいけば必ず一度は聴けるアンセム。
非常にスピリチュアルな音色とは裏腹に「僕はキミの友達になるだろう」とシンプルにそして熱く連呼するあたりが、またしてもスピリチュアル。
Gypsy Woman (She’s Homeless)Crystal Waters

世界中で大ヒットしたディープ・ハウスといえば、こちらの『Gypsy Woman (She’s Homeless)』ではないでしょうか?
めちゃくちゃ有名な曲なので、聞き覚えのある方も多いと思います。
「ぱらり~らうら~」というアドリブが耳に残りますよね(笑)。
非常に聴きやすいサウンドに仕上げられているため、ハウスミュージックを聴き慣れていない方にもオススメできる1曲です。
クリスタル・ウォーターズさんの楽曲は他にも名曲がそろっていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください!
ディープハウスの名曲。おすすめの人気曲(41〜50)
Your LoveFrankie Knuckles, Jamie Principle

印象的なイントロのアルペジオ、このフレーズは今なお、あらゆる曲でサンプリングされています。
評価の高さがうかがえる名作。
今は亡き、ハウスミュージックの父、フランキー・ナックルズの初期作品にして、もっとも人気の高い曲です。
ボーカルはジェイミー・プリンシプルが務めミステリアスなムードに仕上がっています。
彼ら2人はハウスミュージック第一世代と呼ばれ、ハウスミュージックの創世に携わっています。
Push The Feeling On (The Dub Of Doom)Nightcrawlers

R&Bが好きな方にオススメしたいのが、こちらの『Push The Feeling On (The Dub Of Doom)』です。
ゴリゴリした感じではなく、登場するフレーズがR&Bテイストなので、スムーズな聴き心地が魅力的な作品です。
サイケデリック・トランスとはひと味違った没入感を味わえるので、集中力を上げたいときに聴くと良さそうですね。
ナイトクローラーさんの楽曲は『Push The Feeling On (The Dub Of Doom)』にも没入感たっぷりのものが盛り沢山なので、ぜひチェックしてみてください!