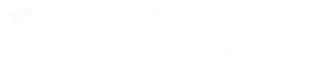【冬】みんなで作ろう!手作り凧まとめ
長いお正月休み、せっかくなら子供たちと体を動かして遊びたい……そう考えている親御さんも多いのでは!
そこで一つ、昔ながらの遊びをやってみてはどうでしょう!
今回この記事では手作り凧のアイデアをまとめてみました。
日本で古くから親しまれている凧はもちろんのこと、ビニール袋やA4紙だけでできるもの、立体的な凧までご紹介しています。
自分で作った凧が大空を自由自在に動く様子は、気分が良いもの!
冬にぴったり、縁起のいいレクリエーションです!
- 身近な材料でこまを手作り!お正月も楽しめる簡単アイデア集
- 【ハンドメイド】おしゃれなこいのぼりの手作りアイデアまとめ
- 日本の伝統遊び「だるま落とし」を作って遊べる!手作りアイデア集
- お正月に!保育で作って飾って遊んで楽しい折り紙のアイデア集
- 【手作り】いろいろな素材で作る、竹とんぼのアイデア集
- 子供が喜ぶくじ引きを手作り!作って遊んで楽しいアイデア集
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 盛り上がるお正月ゲーム。定番から手作りまで楽しいアイデア集
- 【こども向け】風をうけてクルクル回る!手作り風車のオススメアイデア集
- 【正月の遊び】昔ながらの遊び&子供から大人まで盛り上がるゲーム
- 【子供向け】冬休みにオススメの室内で楽しめる遊び・レクリエーション
- 1月に楽しむ!子供向け折り紙アイデア
- 12月の折り紙アイデア!子どもと作るクリスマス&冬の簡単工作
【冬】みんなで作ろう!手作り凧まとめ(11〜20)
八つ凧

8つの輪で構成される変わった形の凧「八つ凧」についてご紹介します!
日立市南部に伝わる伝統的で、歴史も長い凧です。
「八つ凧」の骨組みは丸い輪骨と呼ばれる輪を横に2つ、その下に3つ、さらに下に2つ、そして一番下にハート形のどんびんを組み合わせて作られます。
複雑な構造の「八つ凧」の製作は手間も時間もかかります。
耐久性が高く、長持ちするんですよ。
長い歴史から、海外でも高く評価されているんです。
お正月に向けてぜひ作ってみてください!
連凧

凧が連続して空に浮かぶ様子が圧倒的な存在感を誇る連凧を製作してみませんか?
まずは、ビニールの上下左右の角に合うように竹ひごを十字に固定。
ビニールと竹が離れないように、しっかりと貼り付けるのがコツです。
続いて、凧のしっぽを本体の下部に貼り付けていきましょう。
空に浮かべた時にゆらゆらと揺れるくらい、長いしっぽを製作してくださいね。
連凧を作る時は、同じイラストを描いたり、虹色のように鮮やかな色あいを表現してみるのもオススメですよ。
子供たちと一緒に作って遊べる凧づくりにぜひ取り組んでみてくださいね。
ビニール袋凧

どこのご家庭にもストックがあるビニール袋で作る凧は、気軽に制作できるのでオススメです。
台形に形づくったビニール袋に、ストローの枠を付けてできるシンプルな仕掛け。
角になっている部分をテープで補強、その部分をパンチで穴をあけて毛糸などで通すのがポイントに。
アニメのキャラクターなどの好きな絵を書いても気分が上がりそうですね!
強度が心配かと思いきや、案外上までしっかり飛ぶそうですよ。
丸めて収納もしやすく、ひらひらとした軽やかな舞いを見られます!
奴凧

こちらは奴凧の作り方を紹介する動画です。
まず最初は谷折りで三角形にしてから、もう一度半分に折ります。
そして紙を開き、長方形に折っていきます。
今度は折り線にそって四つ角を全て内側に折ります。
裏返し、そこから再度四つ角を折る。
その後、一番下の三角を開いて長方形にしていきます。
あとは両端も同じように折ると、奴凧が出来上がります。
寒い冬は、コタツに入ってゆっくり折り紙遊びというのもなかなか乙でいいものだと思います。
イーグルカイト

オリジナルのかっこいいデザイン凧を作りたいお子さんにピッタリ、イーグルカイトです。
厚めのごみ袋を用意し下書きに沿ってカッターで切り取ったら、先にマジックで柄を描いておきましょう。
切り出した他のパーツを両面テープで貼りつけ裏返し、竹ひごをセロハンテープで固定します。
もう一度裏返し、穴を開けてたこ糸を通せば完成です!
穴を開ける際はガムテープを貼ってからおこなうと、そのままビニールが裂けていくのを防げます。
竹ひごが重なる部分は、テープを多めに使ってしっかり固定してくださいね。
こま凧

こま凧は日本の伝統凧の一つ。
その名の通りですが昔ながらな子供の遊び道具である、こまに似ていることから名付けられたそう。
こまの形に障子紙を切り取り絵の具で好きな絵を描いたら、あとは竹ひごを付けて完成です!
尾を付けなくても安定して飛んでくれるため、あげる技術も必要ないのがこま凧の魅力。
「せっかく作ったのにうまく飛ばなかった」「あげ方がわからず楽しめなかった」そんな経験がある方はぜひチャレンジしてみてくださいね!
【冬】みんなで作ろう!手作り凧まとめ(21〜30)
インドアカイト

三角形が特徴的な室内でも飛ばせる「インドアカイト」。
こちらは材料にビニール袋を使っています。
袋の角をうまく利用して三角形の形にしているようですね。
袋から三角形を切り出したら、真ん中に1本、三角の左右の辺に1本ずつ骨を取り付け、さらに辺を結ぶように、横向きに1本取り付けてください。
凧の上下に中央の骨を挟んで2カ所ずつ穴を空けたら、糸を通して結んで完成ですよ。
くるくる旋回しながら飛びますので、糸をうまく操りながら揚げてみてください。