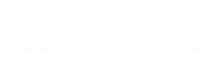高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集
夏休みの自由研究、テーマの選び方で悩んでいる高校生のみなさん。
「短期間でできる実験がいい」「見栄えの良い研究にしたい」など、手軽にできる自由研究を探している方に朗報です!
この記事では科学の楽しさが詰まった、実験や工作を中心とした自由研究のアイデアをご紹介します。
スチームエンジンやプラネタリウムなど、見た人が思わず「すごい!」と声を上げる作品ばかり。
しかも意外に簡単に取り組めるものを集めました。
夏休みの思い出に残るステキな研究を、見つけてくださいね!
- 【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 【大人向け】簡単だけどすごい工作。オシャレで見栄えのする作品集
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
- 小学生の男の子が夢中になる自由研究工作!身近な材料で作れるアイデア
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 簡単だけどすごい工作。小学生が作りたくなる工作アイデア
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 大人が夢中になる!トイレットペーパーの芯の工作アイデア集
- 中学生向にオススメ!短時間でできる自由研究のアイデア集
高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集(61〜70)
バターを作る実験

パンに塗ったり、じゃがバターにしたり、さまざまな食材をおいしくしてくれるバター。
実はとてもシンプルな手順で作れるのをご存じでしたか?
主な工程としては、滅菌した容器に冷やした生クリームを入れ、強く15分振り続けるだけ。
液体が固形に変わり、その固形の部分が無塩バターです。
塩を混ぜるとバターのできあがり!
15分振り続けるのは意外に大変なので、テレビなどを見ながらすると良いかもしれませんね。
どうしてバターができるのかもまとめてみましょう。
媒介変数で模様を描いてみよう

「媒介変数表示」を使って模様を書いてみようというアイデアです。
高校生なら、媒介変数表示を使って曲線グラフの概要を描き、面性を求める問題を見た事があるのではないでしょうか。
基本の式を少し変化させるだけでさまざまな曲線が生まれるので、いろいろと試してみてくださいね。
「アステロイド曲線」、「対数螺旋」、「リサージュ図形」など、有名な形がいくつかあるので、まずはそちらからやってみても良いですね。
式と模様の画像をまとめて、自由研究として提出しましょう。
スピーカーをつくろう
電気信号を物理的な振動に変えて、音に変換する音響装置のスピーカー。
音楽鑑賞や映画鑑賞するときに、音をよくするためにスピーカーを利用している方もいますよね。
実は、スピーカーは簡単な装置で作れますよ。
紙コップとほどけないようによく巻いたコイル、磁石の3つで作ってみましょう。
コイルを紙コップの底にくっつけます。
コイルの先をCDプレイヤーにつなげて、コイルに磁石を近づけてください。
すると、CDの音楽がスピーカーから流れますよ。
磁石とコイルの距離で音の大きさもかわってきます。
簡単な装置なのでぜひ作ってみてくださいね。
プリザーブドフラワー作り

結婚式や母の日のプレゼントとして人気のプリザーブドフラワーを作ってみるのはどうでしょうか。
作り方は生花の水分を抜いて、特殊な液体をかける、というもの……難しそうに聞こえますか?
大丈夫です、調べてもらうとわかりますが、初心者向けのプリザーブドフラワーキットが販売されていますので、そちらを購入してチャレンジしてみましょう。
もちろん自分で材料を準備するのもありですよ。
ロボットアーム工作

1日でできる、というところが夏休みの宿題をギリギリまで残してしまう人へのオススメポイントです。
また、1日でできる工作の中でもクオリティが高く、とても本格的な作りで見た目もかっこいいので、女の子にモテるかもしれません。
動画制作

動画制作を自由研究にしてみるのはいかがでしょうか?
動画制作には頭を使います。
このカットは何秒間見せるのがいいか、この字幕の表示秒数はこれでいいか、どういう構成にすれば視聴者の目を引けるのか、など……。
こういった、消費者の目を意識したものづくりという経験は非常に貴重で、ほかのことにもいかせるはずです。
最近は、スマホさえあれば簡単に動画制作ができるので取り組みやすい題材かもしれませんね。
カビの生え方

湿気が多い夏の時期に多く発生する、カビのメカニズムを知っていく研究です。
どのような環境や状況で発生するのかを理解すれば、日常生活でのカビの予防にもつながっていきますよ。
実験の手順はシンプルで、カットしたパンをさまざまな条件で室内に放置、カビの状況をチェックしていきます。
ワサビやからしと組み合わせるパターン、置く場所を変えるパターンなどで、カビの発生の違いがわかるという内容です。
カビにまつわるおうちの環境がわかれば、物の置き場所や掃除の目安にもなりそうですね。