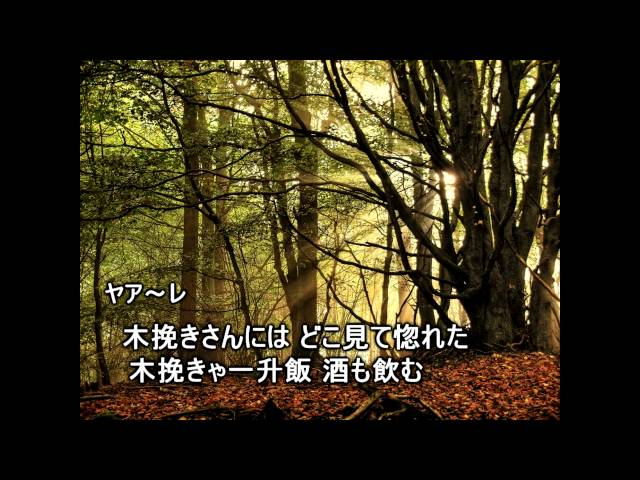熊本の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
『おてもやん』や『五木の子守唄』など、全国的に知られている民謡やわらべうたの舞台となった熊本。
これらの作品には、阿蘇の雄大な自然や、熊本城の勇壮な姿、そして人々の暮らしの営みが鮮やかに描かれています。
西南戦争の哀しみを伝える『田原坂』から、豊作を祝う『肥後米音頭』まで、歌い継がれる民謡の一つひとつに、熊本の歴史と文化が深く刻まれているのです。
この記事では、郷土を思う心や日々の喜びが込められた熊本の民謡、童謡、わらべうたを集めました。
熊本の魂が宿る歌の世界に、耳を傾けてみましょう。
- 熊本を歌った名曲。歌い継がれる故郷のこころ
- 長崎の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 【福岡の民謡・わらべうた】懐かしの故郷の調べが伝える歴史と想い
- 民謡の人気曲ランキング
- 【わらべうた】歌い継がれる懐かしの名曲たち
- 【子育て】親子で触れ合い!手遊び歌・わらべうたまとめ
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 広島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 【秋の童謡】秋のうた・唱歌・わらべうた。秋に歌いたい名曲集
- 【秋田の民謡・童謡】ふるさと愛を感じる郷土の名曲を厳選
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
- 【鹿児島民謡の世界】郷土の心を歌い継ぐ伝統の調べ
熊本の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ(11〜20)
八代おざや節

熊本の八代地方に伝わるこの民謡は、干拓工事で働く人々の作業歌がルーツなのだそう。
三味線や笛、太鼓が織りなすにぎやかな音色が、当時の人々のたくましい息づかいを今に伝えてくれます。
曽我了子さんの歌声で2006年2月にカセットテープバージョンが発売され、2019年10月にはモノマネタレントの荒牧陽子さんがアルバム『熊本民謡編 第1集(心の故郷 日本の民謡)』でカバーを発表した本作は、現在でも地域文化イベントで親しまれています。
困難な時代を生き抜いた人々の魂の歌声が、きっとあなたの心にも響くことでしょう。
魚貫草刈り唄

熊本県天草諸島の魚貫埼の海域で行われるボラ網漁期の約2ヶ月の間、長崎県から仮住まいでやってくる漁師たちがいました。
村の娘と長崎からやってきた漁師の儚い恋を唄った民謡が、熊本県牛深市(現在の天草市)に伝わる「魚貫草刈り唄」です。
阿蘇神社の子守唄山本時雄
熊本県阿蘇地方に伝わる子守唄「阿蘇神社の子守唄」です。
「羽衣の母」や「阿蘇の羽衣子守唄」とも呼ばれているようです。
唄のタイトルでピンと来る人もいると思いますが、阿蘇の田鶴原神社に伝わる羽衣伝説を題材にした唄になっています。
球磨の六調子田中祥子

熊本県南部の人吉市や、球磨川流域を占める球磨郡で、祝い唄と酒盛り唄を兼ねて唄われてきた民謡「球磨の六調子」です。
唄名の「六調子」は、六通りの唄と踊りという説、雅楽の六調子という説、三味線の三本の糸を上下往復させる奏法という説などさまざまな説があります。
阿蘇の木挽き唄岩永清龍
『阿蘇の木挽き唄』は熊本県阿蘇地方に伝わる民謡で、木を切り製材をする山仕事の作業歌でした。
年頃の妹を心配する兄が、木挽きの女房にはなるんじゃないと忠告しています。
仲良く育った木と夫婦仲をかけて上手く作られた、シャレの効いたおもしろい歌ですね。
ポンポコニャ

熊本県熊本市で歌い継がれてきた民謡『ポンポコニャ』。
その昔、熊本市内には花柳界があり、お座敷で歌われていたと伝えられています。
熊本の観光名所が織り込まれた明るい調子の民謡で、聴いているうちに実際に熊本を巡ってみたくなるような、そんな魅力あふれる1曲です。
熊本の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ(21〜30)
熊本民謡「ヨヘホ節」「五木の子守唄」によるラプソディー奥田祐

熊本の魂が息づく2つの民謡を土台に、三味線の響きとバイオリンの旋律が美しく交差する作品です。
和の情緒と洋の表現力が見事に調和し、聴く人の心に懐かしさや深い祈りのような感情を呼び起こします。
本作は紀尾井ホールの委嘱で2017年頃に初演され、バイオリニスト篠崎史紀さんと長唄三味線方の今藤長龍郎さんによる情熱的な演奏映像が残っています。
熊本の原風景に心を寄せたい方や、和と洋が融合した新しい音楽体験を求める方にピッタリ!
じっくりとその世界に浸ってみてはいかがでしょうか。