新潟の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
伝統的な盆踊りや祭りが開催されており、米の栽培面積や収穫量が多いことで知られる新潟県。
佐渡島をテーマにした曲をはじめ、新潟県にまつわる数多くの民謡や童謡をピックアップしました。
祭りの場面でも使用される事の多い民謡は、リズミカルな音からも楽しい様子が伝わるでしょう。
全国的にも親しまれている『佐渡おけさ』などの楽曲が誕生した背景にせまるのもオススメですよ。
新潟の各地方の魅力を伝える民謡や童謡にぜひ耳を傾けてみてくださいね。
- 新潟を歌った名曲。歌い継がれる故郷のこころ
- 民謡の人気曲ランキング
- 青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌
- 長崎の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 富山の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集
- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌
- 【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い
- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も
- 【秋田の民謡・童謡】ふるさと愛を感じる郷土の名曲を厳選
- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ
- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集
- 徳島の民謡・童謡・わらべうた|阿波踊りや地域に根ざした伝統の歌
新潟の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ(21〜30)
岩室甚句都屋初枝
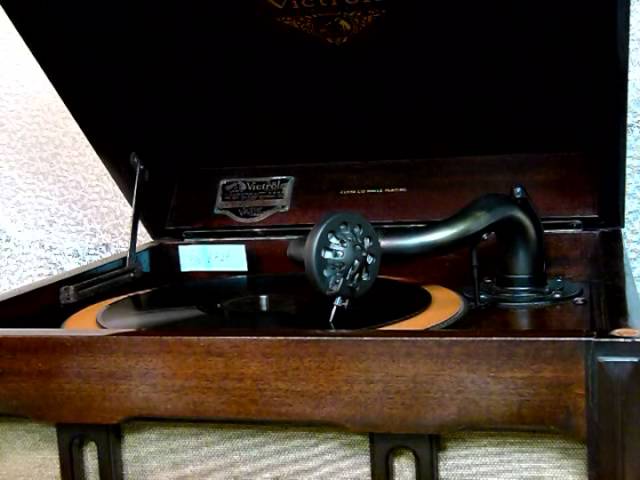
1932年頃、岩室の鴬芸者の小竜と初江が中心となって三味線や太鼓の工夫を凝らし、現在の「岩室甚句」を作り上げました。
近郷の農民たちが盆踊りで唄う「越後甚句」の一種で、「新潟甚句」や「長岡甚句」と同系統のものですが、温泉場の素朴で野暮ったさのある芸風が「岩室甚句」の良いところです。
砂山徳倉さだ子

「砂山」は、新潟県で行われた童謡音楽会に招かれた北原白秋さんが、2000人あまりの小学生たちから新潟にちなんだ歌を作って欲しいと頼まれ作詞した作品です。
市街地に隣接する佐渡島を一望できる寄居浜海岸から見た光景を書き上げました。
新潟小唄曽我直子

「新潟小唄」は新潟県新潟市に伝わる花柳界のお座敷唄です。
新潟毎日新聞主催の「歌舞の夕べ」で「新潟港おどり」が発表されたが反応はいまひとつでした。
そこで新潟新聞社が新たな策で対抗し、詩人の北原白秋さんに詩を依頼、そして民謡・三味線音楽の研究で有名な学者、町田佳聲さんに曲をつけてもらい誕生しました。
お月さまいくつ檀道子、戸坂茂子

新潟県南魚沼郡塩沢町に伝わる遊ばせ唄です。
遊ばせ唄というのは、伝統的な民謡の一種とされている子守唄に分類されます。
子守唄は「寝させ唄」と「遊ばせ唄」に二分されていて、「お月さまいくつ」もその中の1つです。
柏崎おけさ泉マキ

郷土を想う心が伝わってくる民謡「柏崎おけさ」です。
新潟と直江津、佐渡の小木を結ぶ経済流通の重要地点とされていた柏崎は、越後文化の中心地でもありました。
「柏崎おけさ」は三味線の弾き方に特徴がある民謡ですので、注目して聴いてみてください。
佐渡甚句近藤洋子

「佐渡甚句」は相川方面の酒盛り唄です。
元は「相川二上り甚句」という名で佐渡各地の甚句という意味でしたが、戦後になると「佐渡甚句」と呼ばれるようになりました。
この唄は、下の句を反復して唄うのが特徴です。
冒頭から酒に酔い、いい気分で騒ぐ酔っ払いの姿が見えるような賑やかな唄です。
大の阪

新潟県北魚沼郡堀之内町(現魚沼市)で行われる盆踊り唄「大の阪」です。
歌詞の中に「南無西方」という言葉が入っていて、さらに御詠歌風の節で唄われることから「念仏踊り」とも呼ばれています。
物悲しい調子で、優雅に踊られます。


