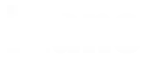【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
ピアノ発表会は、ご家族やご友人をはじめ、さまざまな方に積み重ねてきた練習の成果を披露できる絶好の機会。
高度なテクニックを要する上級者向けのピアノ曲は、発表会でも聴き映えすることでしょう。
本記事では、ピアノ経験をある程度重ねてきた方が発表会で披露するのにピッタリの、聴き映えする作品をご紹介します。
高難度でも意外に聴いている人には難しさが伝わらないものもありますが、今回紹介するのは会場の観客をグッと引きつけられるすてきな作品ばかりです。
普段の練習曲よりも思い切って少し背伸びしたレベルの作品を選び、今までの努力を信じて堂々と演奏してみてくださいね!
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】中学生におすすめ!クラシックの名曲を一挙紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級】ピアノ連弾作品|4手の重厚な響きを味わえる珠玉の名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(61〜70)
半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903J.S.Bach

バロック時代を代表する作曲家、ヨハン・セバスティアン・バッハの名作。
半音階的な動きが特徴的で、革新的な和声構造と大胆な表現力で知られています。
1717年から1723年の間に作曲されたとされるこの曲は、幻想曲とフーガの2部構成で、自由な即興性と厳格な形式美が見事に融合しています。
高度な技術を要する上級者向けの作品ですが、その音楽性の深さは聴く人の心に強く響くはず。
バッハの生存中から高く評価されていた本作は、挑戦する価値のある1曲です。
ロンド・ブリランテOp.62Carl Maria von Weber

ロマン派初期に活躍し、オペラや劇付随音楽、協奏曲などを手掛けた作曲家として知られるカール・マリア・フォン・ウェーバー。
『ロンド・ブリランテ Op.62』は、そんな彼が残したピアノ作品の一つで、『華麗なロンド』『戯れ言』などのタイトルでも親しまれています。
この曲はドレスデンの宮廷のサロンで演奏するために作曲されたもので、上品な華やかさと次々とやってくる、オペラを思わせる場面転換が魅力的な作品となっています。
細かい音の粒をそろえ正確に弾くのはもちろん、曲調の変化にも注目してスケールの大きな演奏に仕上げましょう。
即興曲 第4番 嬰ハ短調 遺作 作品66 「幻想即興曲」Frederic Chopin

ロマン派を代表する作曲家、フレデリック・ショパンの4つの即興曲のうち、最初に作曲されたのが、最も有名な本作。
1音目のオクターブがなった瞬間、この曲だと気づく方も少なくないはず。
左手は1拍を6等分、右手は8等分したリズムになっているため、練習し始めてしばらくは両手奏のコツをつかむのが難しいかもしれません。
しかし、練習を重ねることで、自然に拍頭を合わせられるようになるでしょう。
根気強く練習を続けてみてくださいね!
超絶技巧練習曲 第5番 『鬼火』Franz Liszt

フランツ・リストの楽曲は、超絶技巧と詩的表現を兼ね備えた名曲として高い評価を受けています。
本作は、夜に浮かぶ揺らめく青白い光の幻想的なイメージを象徴しています。
半音階的な速い音型が絶えず続き、音の揺らぎが「鬼火」の幻想的な動きを思わせます。
変ロ長調の調性感を持ちながらも、時折現れる不協和音的な響きやリズムの変則性が、神秘的な雰囲気を作り出しています。
1851年に完成したこの曲は、ピアノ音楽の発展に大きく貢献しました。
クラシック音楽に興味がある方や、技術的な挑戦を求めるピアニストの方におすすめの一曲です。
アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22Frederic Chopin

管弦楽とピアノによる協奏曲的作品、『アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22』。
後にピアノ独奏版として編曲された本作は、ショパンの作品のなかでも屈指の難易度をほこることで知られています。
そんな本作のポイントは、なんといってもコーダの付いた三部形式。
右手の装飾音に高度な技巧が要求されるため、繊細なタッチを苦手とする演奏家からは避けられています。
華やかで明るい繊細が好きな方は、ぜひチェックしてみてください。
クライスレリアーナ Op.16 第7曲Robert Schumann

非常に情熱的で劇的な表現が特徴的なこの曲。
急速なテンポとハ短調の調性が融合し、聴く者の心をつかみます。
約2分30秒の短い演奏時間ながら、ロベルト・シューマンの内面的な葛藤や情熱が凝縮されています。
激しいアクセントを持つアルペッジョの繰り返しが緊張感を高め、中間部のフガートとの対比が印象的です。
1838年に作曲された本作は、シューマンがクララ・ヴィークとの結婚に反対され苦悩していた時期の作品。
ロマン派音楽の特徴である感情表現の豊かさが存分に発揮されており、ピアノ演奏の技術と表現力が試される1曲です。
クラシック音楽の深い感動を味わいたい方におすすめの名曲です。
楽興の時 第4番 ホ短調「プレスト」Sergei Rachmaninov

哀愁ただようメロディが印象的なセルゲイ・ラフマニノフさんの名曲『楽興の時 第4番 ホ短調「プレスト」』。
ラフマニノフさんはピアニストとしても評価が高く、非常に手が大きかったことで知られています。
この作品でもそんな彼の手の大きさはしっかりと反映されており、右手のオクターブが何度も登場します。
細かいスラーがあるにもかかわらず、スタッカートを強調しなければならない部分やオクターブの連続など、高度なテクニックを要するパッセージが多いので、上級者でこの楽曲を練習したことがない方は、ぜひ取り組んでみてください。