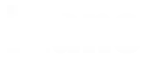【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
ピアノ発表会は、ご家族やご友人をはじめ、さまざまな方に積み重ねてきた練習の成果を披露できる絶好の機会。
高度なテクニックを要する上級者向けのピアノ曲は、発表会でも聴き映えすることでしょう。
本記事では、ピアノ経験をある程度重ねてきた方が発表会で披露するのにピッタリの、聴き映えする作品をご紹介します。
高難度でも意外に聴いている人には難しさが伝わらないものもありますが、今回紹介するのは会場の観客をグッと引きつけられるすてきな作品ばかりです。
普段の練習曲よりも思い切って少し背伸びしたレベルの作品を選び、今までの努力を信じて堂々と演奏してみてくださいね!
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】中学生におすすめ!クラシックの名曲を一挙紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級】ピアノ連弾作品|4手の重厚な響きを味わえる珠玉の名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(41〜50)
魔王Schubert=Liszt

フランツ・シューベルトが作曲し、ピアノの魔術師フランツ・リストが編曲した作品は、聴衆を魅了する傑作です。
ゲーテの詩に基づくこの曲は、父と子、そして魔王の対話を描き、ピアノが馬の疾走感を表現する歌曲の傑作。
リストの編曲により、技巧的に難しいピアノ曲へと生まれ変わった本作も、変化に富んだ大変魅力的な音楽となっています。
オクターブの連打は相当な腕を持つピアニストにとっても一筋縄ではいかない超高難度のパッセージ。
あなたも超人の領域にチャレンジしてみては?
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(51〜60)
演奏会用アレグロ イ長調 Op.46Frederic Chopin

難曲として知られるショパンのピアノ独奏曲『演奏会用アレグロ』。
今回はその中から、こちらの『演奏会用アレグロ イ長調 Op.46』をオススメしたいと思います。
本作の難しさはなんといっても、速いオクターブ。
手の大きさはもちろんのこと、すばやく正確なポジショニングも求められる高難易度の作品です。
ただただ難しいだけではなく、ショパンならではの洗練された演奏効果もすばらしいので、ぜひチェックしてみてください。
ピアノソナタ ロ短調 S.178Franz Liszt

リストの作品には、いかにもリストらしい構成や展開が存在します。
こちらの『ピアノソナタ ロ短調 S.178』という作品はその中でも特に「リストらしい」作品の1つです。
『超絶技巧練習曲』に比べるとやや易しい難易度ではありますが、それでも上級の中でも上位に位置する作品で、重厚なフォルティッシモの連打から非常に速いパッセージまで、幅広い技巧が求められます。
楽譜だけでは簡単に思えるかもしれませんが、実際に弾いてみると難しさを感じる作品といえるでしょう。
エチュード集(練習曲集) 第4番 Op.10-4 嬰ハ短調Frederic Chopin

激しく情熱的な楽曲で、聴く人の心をつかんで離しません。
高速な16分音符のパッセージや左右の手で細かい音型が連続する構成は、まるで嵐のような迫力を感じさせます。
1832年8月に作曲されたこの曲は、単なる練習曲を超えた芸術的価値の高い作品として評価されています。
ピアノ技術の向上を目指す人はもちろん、情熱的な音楽を好む人にもおすすめです。
演奏には高度な技術が必要ですが、その分達成感も大きいでしょう。
クラシック音楽の魅力に触れたい方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
ワルツ 第6番 変ニ長調「小犬のワルツ」Frederic Chopin

ピアノ独奏のために書かれたこの楽曲は、軽快で華やかなメロディが特徴的です。
右手の速いスケールと左手の安定したワルツリズムが絶妙に組み合わさり、まるで小犬が楽しげに駆け回る様子を描写しているかのようです。
1846年から1848年にかけて作曲され、デルフィナ・ポトツカ伯爵夫人に献呈されました。
演奏時間は約1分半から2分と短めですが、高度な技術と表現力が要求される曲でもあります。
クラシック音楽ファンはもちろん、ピアノ演奏を学ぶ方にもおすすめの一曲です。
映画やアニメのBGMとしても使用され、幅広い層に親しまれています。
超絶技巧練習曲集4番「マゼッパ」Franz Liszt

いくつもの高難易度な楽曲を作り、多くの演奏家たちの頭を悩ませてきた作曲家、フランツ・リスト。
難しい楽曲が多い作曲家と聞かれれば、誰もがリストをイメージするのではないのでしょうか?
そんなリストの作品のなかでも、特に難しいといわれている楽曲が、こちらの『超絶技巧練習曲集4番「マゼッパ」』。
あらゆる部分で難しい作品というわけではありませんが、オクターブと重音に関しては無類の難易度をほこります。
「Allegro deciso」から難易度が一気に上がるので、練習ではとにかく正確にポジションを取ることを意識しましょう。
トルコ行進曲Wolfgang Amadeus Mozart

陽気で軽快な旋律が印象的な本作は、18世紀後半に流行したトルコ風音楽の影響を受けた名曲です。
オスマン帝国の軍楽隊を模倣した独特のリズムと、シンバルや太鼓を思わせる力強い音色が特徴的。
1783年頃に作曲されたこの曲は、ウィーン時代のモーツァルトの創造性が遺憾なく発揮された傑作といえるでしょう。
親しみやすい旋律とエキゾチックな雰囲気が見事に融合しており、クラシック音楽入門者から上級者まで幅広く楽しめる一曲です。
華やかな演奏会や発表会でもきっと映えることでしょう。