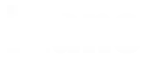【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
ピアノ発表会は、ご家族やご友人をはじめ、さまざまな方に積み重ねてきた練習の成果を披露できる絶好の機会。
高度なテクニックを要する上級者向けのピアノ曲は、発表会でも聴き映えすることでしょう。
本記事では、ピアノ経験をある程度重ねてきた方が発表会で披露するのにピッタリの、聴き映えする作品をご紹介します。
高難度でも意外に聴いている人には難しさが伝わらないものもありますが、今回紹介するのは会場の観客をグッと引きつけられるすてきな作品ばかりです。
普段の練習曲よりも思い切って少し背伸びしたレベルの作品を選び、今までの努力を信じて堂々と演奏してみてくださいね!
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】中学生におすすめ!クラシックの名曲を一挙紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級】ピアノ連弾作品|4手の重厚な響きを味わえる珠玉の名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(21〜30)
ピアノソナタ 第23番 Op.57「熱情」第3楽章Ludwig van Beethoven

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの名作『ピアノソナタ 第23番 Op.57「熱情」第3楽章』。
彼のソナタといえば『悲愴』や『月光』が有名ですが、今回はあえてこちらをピックアップしました。
この作品はベートーヴェンの作品のなかでも、最も有名な『運命』の原型とも言える作品で、彼ならではの感情的な表現が多く登場します。
もちろん、演奏難易度も表現の多さに比例して高まっているのですが、その分、聴き映えのする作品なので、ぜひチェックしてみてください。
バラード 第2番 ヘ長調 Op.38Frederic Chopin

ロマン派を代表するフレデリック・ショパンの作品は、ピアノ発表会でも人気が高いですね。
本作は、穏やかな旋律から荒々しい激情へと変化する劇的な構成が特徴的。
冒頭の静かなヘ長調から急速で激しいイ短調へと転調し、再び元の主題に戻る展開は、聴衆を引き込む魅力があります。
ショパンの故郷ポーランドへの思いが込められているともいわれ、演奏者の技術と表現力が試される1曲。
高度な技巧を要しますが、その分聴き応えも抜群です!
12の練習曲 Op.8 第12番「悲愴」Aleksandr Skryabin

アレクサンドル・スクリャービンの名作『12の練習曲 Op.8 第12番「悲愴」』。
スクリャービンの作品のなかでは特に難しい楽曲として知られていますが、実際のところはショパンのエチュードよりは簡単といった程度です。
しかしながら、やけに跳躍が多い楽曲なので、人によっては暗譜が必須だと思います。
ただし、細かいアルペジオが登場するわけではないので、指回りに自信がない方でも気軽に取り組めるといった側面もあります。
しっかりと聴き映えのする作品なので、ぜひチェックしてみてください。
8つの演奏会用練習曲 Op.40 第1曲「プレリュード」Nikolai Kapustin

20世紀を代表するピアニスト兼作曲家、ニコライ・カプースチンさんの作品です。
1984年に発表された『8つの演奏会用練習曲 Op.40』の第1曲は、クラシックとジャズを見事に融合させた傑作。
ラテンのリズムと複雑な変奏が織り交ぜられ、聴く者を魅了します。
速いテンポと高度な技巧を要する本作は、ピアニストにとって挑戦しがいのある曲。
そのうえ、その魅力的な音楽性から、聴衆を引き付けるのに最適な1曲となっています。
ピアノの実力を存分に発揮したい方や、新鮮な響きを求める方にオススメです。
前奏曲 ト短調 Op.23-5Sergei Rachmaninov

セルゲイ・ラフマニノフさんが1901年に完成させた傑作。
ロシアの風土をほうふつとさせる重厚で情熱的なメロディが特徴的です。
歯切れのよいリズムや、オクターブ以上の音を着実につかむことが求められる和音の連続、オクターブの連打など、高度なテクニックを要するフレーズがたびたび現れますが、中間部では彼の作品らしいロマンチックな旋律を楽しめます。
曲全体に演奏者と聴衆の両方を引き込む魅力的な要素がちりばめられており、発表会で披露するのにピッタリの1曲。
テクニックと表現力ともに大きな成長を期待できる作品です。
半音階的大ギャロップFranz Liszt

リストの名作『半音階的大ギャロップ』。
『超絶技巧練習曲』の『マゼッパ』や『鬼火』とともに、リストの難曲として名高い作品ですね。
そんな本作の難所はなんといっても4-5指を用いた細かい動きではないでしょうか?
指がつりそうになるいやらしい構成に加えて、幅広い跳躍やオクターブも連発します。
並の上級者では正しく演奏することが難しい作品です。
他のリストの作品に比べると、演奏効果がやや低い作品ですが、増三和音や全音音階の響きが好きな方にとってはツボに入る作品といえるでしょう。
12の練習曲 Op.12 第10番「革命」Frederic Chopin

ピアノ発表会で演奏される作品は技術を重視したものが多いため、聴き映えしにくい傾向にあります。
フレデリック・ショパンの名作であるこちらの『12の練習曲 Op.12 第10番「革命」』は、技術的にも難しい作品でありながら、音楽作品としても高く評価されています。
まさに聴き映えのする楽曲としてはうってつけの作品と言えるでしょう。
右手の主題が有名な作品ですが、左手の速い16分音符のアルペジオもなかなかに難しいので、演奏に自信のある方はぜひ挑戦してみてください。