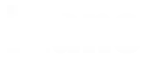【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
ピアノ発表会は、ご家族やご友人をはじめ、さまざまな方に積み重ねてきた練習の成果を披露できる絶好の機会。
高度なテクニックを要する上級者向けのピアノ曲は、発表会でも聴き映えすることでしょう。
本記事では、ピアノ経験をある程度重ねてきた方が発表会で披露するのにピッタリの、聴き映えする作品をご紹介します。
高難度でも意外に聴いている人には難しさが伝わらないものもありますが、今回紹介するのは会場の観客をグッと引きつけられるすてきな作品ばかりです。
普段の練習曲よりも思い切って少し背伸びしたレベルの作品を選び、今までの努力を信じて堂々と演奏してみてくださいね!
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】中学生におすすめ!クラシックの名曲を一挙紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級】ピアノ連弾作品|4手の重厚な響きを味わえる珠玉の名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(51〜60)
夜のガスパール 第3曲「スカルボ」Maurice Ravel

ラヴェルの作品のなかでも、屈指の難易度をほこると言われている作品『夜のガスパール 第3曲「スカルボ」』。
前衛的な表現を作り上げたラヴェルですが、本作でもその個性はいかんなく発揮されており、速いパッセージや難しいオクターブが連発するなかで、細かい表現を達成しなければなりません。
単純な難易度だけなら他の高難易度の曲に劣ることもあるものの、弾くのに精いっぱいの状態であれば、細かい表現を演出していくのは相当難しいといわざるをえません。
表現力に自信のある方は、ぜひ取り組んでみてください。
ハンガリー狂詩曲 第2番Franz Liszt

超絶技巧を要する難曲を数多く作曲したピアノの魔術師フランツ・リストの『ハンガリー狂詩曲 第2番』。
こちらの曲も例にもれず非常に難易度が高く、プロのピアニストでも演奏に苦戦する作品の一つです。
重厚な雰囲気から始まり、徐々に華やかさを増していく様子は、まさに圧巻!
明るく美しいメロディと力強いリズムは、長年にわたり多くのピアノ学習者やピアノ愛好家を魅了し続けています。
弾きこなすには相当な練習が必要になりますが、ドラマチックな世界観を楽しみながらチャレンジしてみてください!
伝説 S.175 第2曲「波を渡るパオラの聖フランチェスコ」Franz Liszt

ひとくちに難曲といってもその種類はさまざま。
『マゼッパ』のような一点集中型の難しさもあれば、あらゆる技巧を含んだ『トッカータ』のようなさまざまな技巧が盛り込まれた難しさもあります。
今回、紹介するこちらの『伝説 S.175 第2曲「波を渡るパオラの聖フランチェスコ」』は後者にあたる作品ですね。
リストの独特の指使いは本作でもしっかりと反映されており、体力もそれなりに必要とする作品です。
カバーしなければならない技術が多いので、一般的な楽曲に対する評価以上に難しさを覚える作品といえるでしょう。
愛の夢 第3番Franz Liszt

フランツ・リストの名作『愛の夢 第3番』。
難易度としては上級に相当する作品です。
譜読みに関しては比較的、簡単で演奏に関してもめちゃくちゃに難しいというわけではありません。
しかしながら、この楽曲は強弱記号がつけられていないことが多いため、弾き手によって印象が大きく変わりやすいという特徴を持ちます。
ここに関しては演奏家の裁量に委ねられるため、表現力においてはバツグンの難しさをほこる作品と言えるのではないでしょうか。
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(61〜70)
幻想小曲集 Op.12 第2曲「飛翔」Robert Schumann

ロベルト・シューマンの名曲『幻想小曲集 Op.12 第2曲 飛翔』。
ピアノ発表会などでも頻繁に耳にする楽曲なので、ご存じの方も多いと思います。
そんなこの楽曲のポイントは、なんといっても左手の存在感ではないでしょうか?
この楽曲は流した伴奏ではなく、しっかりとしたペダル操作で音が濁らないように低音部を演奏しなければなりません。
加えて17小節目からは右手も手の小さい人にとって難しい演奏が登場します。
難易度としては中級程度ですが、聴き映えのする作品なので、ぜひチェックしてみてください。
12の練習曲 Op.25-11「木枯らし」Frederic Chopin

フレデリック・ショパンの練習曲のなかの1曲『12の練習曲 Op.25-11「木枯らし」』。
『木枯らしのエチュード』という名前でも親しまれている作品ですね。
高速の16分音符がピアニストを苦しめる本作。
指が分離しづらい人にとっては異常な難しさを感じるかもしれませんが、そうでない人にとっては繰り返しが多いため、一度コツをつかめてしまえば意外に弾きこなせてしまうかも?
力試しで取り組んでみてはいかがでしょうか?
幻想曲 ニ短調 K. 397Wolfgang Amadeus Mozart

哀愁に満ちた旋律が印象的なモーツァルトの名作『幻想曲 ニ短調 K. 397』。
発表会でも頻繁に演奏されるため、ご存じの方も多いのではないでしょうか?
モーツァルトの作品としては悲劇的な旋律が特徴で、高い表現力が求められます。
分散和音による即興的な序奏が特徴で、そこに難しさを感じる方も多いかもしれません。
中級者が取り組む作品としてはやや難易度が高い楽曲ですが、後半では明るく気持ちの良い演奏が展開されるので、そこで一気にフラストレーションを開放することを目標に練習してみてください。