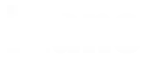【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽
ピアノ発表会は、ご家族やご友人をはじめ、さまざまな方に積み重ねてきた練習の成果を披露できる絶好の機会。
高度なテクニックを要する上級者向けのピアノ曲は、発表会でも聴き映えすることでしょう。
本記事では、ピアノ経験をある程度重ねてきた方が発表会で披露するのにピッタリの、聴き映えする作品をご紹介します。
高難度でも意外に聴いている人には難しさが伝わらないものもありますが、今回紹介するのは会場の観客をグッと引きつけられるすてきな作品ばかりです。
普段の練習曲よりも思い切って少し背伸びしたレベルの作品を選び、今までの努力を信じて堂々と演奏してみてくださいね!
- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選
- 【上級】弾けたら超絶かっこいい!ピアノの名曲選
- 【ピアノ発表会】中学生の演奏にピッタリ!聴き映えする曲を厳選
- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【ピアノ発表会】中学生におすすめ!クラシックの名曲を一挙紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【上級】ピアノ連弾作品|4手の重厚な響きを味わえる珠玉の名曲たち
- ピアノで弾けたらかっこいい!魅力抜群の名曲たちをピックアップ
- 【難易度低め】ラフマニノフのピアノ曲|挑戦しやすい作品を厳選!
【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽(71〜80)
ピアノソナタ第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」第1楽章Ludwig van Beethoven

最も偉大な作曲家の1人、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。
初級者から上級者まで、幅広く親しまれているベートーヴェンですが、なかでもこちらの『ピアノソナタ第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」第1楽章』は中級者から最も親しまれている作品の一つといえるでしょう。
第1楽章は『悲愴』のなかでも屈指の難易度をほこることで知られていますが、中級上位におさまる難易度ですので、中学生でも取り組めると思います。
スタッカートが多く登場しますが、気を取られて短く演奏しすぎないようにしましょう。
3つの演奏会用練習曲 S.144 第2番『軽やかさ』Franz Liszt

いくつもの恐ろしく難しい練習曲を作り上げてきたリスト。
『超絶技巧練習曲』や『パガニーニによる大練習曲』が有名ですが、今回はサロンの要素を持った練習曲を紹介したいと思います。
それがこちらの『3つの演奏会用練習曲 S.144 第2番「軽やかさ」』。
3連符から7連符に変わる印象的な構成で、右手に関してはさまざまな技術が詰め込まれています。
具体的な難易度としてはチェルニー50番の前半と同じ程度といったところでしょうか。
間違いなく上級なので、ぜひチェックしてみてください。
ハンガリー狂詩曲 第6番Franz Liszt

リストの生まれ故郷、ハンガリーをテーマにした名作『ハンガリー狂詩曲 第6番』。
第2番が最も演奏が難しいと言われていますが、こちらの第6番も相当な難易度をほこります。
間違いなく上級のなかでも上位に入る難しさといえるでしょう。
とにかくオクターブの幅が広い本作は、力強さと速さ、そして正確さが求められています。
非常に難しい作品ですが、その分、演奏効果も高いので聞き手としても大いに楽しめるでしょう。
ぜひチェックしてみてください。
バラード 第4番ヘ短調 Op.52Frederic Chopin

ショパンの難曲のなかでも、ショパンらしさが発揮されている作品といえば、こちらの『バラード 第4番ヘ短調 Op.52』ではないでしょうか?
重音が多く、難解なパッセージも幾度となく出現する作品で、ショパンのなかでも屈指の難易度をほこります。
この重音の多さがショパンらしさを物語っているため、彼の作品が好きな方にとっては非常に親しみやすいでしょう。
歌曲集「冬の旅」より「菩提樹」S.561 R.246Schubert=Liszt

フランツ・シューベルトが、ドイツの詩人ヴィルヘルム・ミュラーの詩をもとに作曲した連作歌曲集『冬の旅』。
ドイツリートの名作として知られるこの曲集の第5曲『菩提樹』は、シューベルト研究家が「ほとんど歌えないほど美しい」と称賛するほど、甘美な旋律で多くの人々を魅了し続けている作品です。
ピアノの魔術師フランツ・リストによって壮大なピアノ作品へと変化を遂げても、原曲の繊細な美しさはそのまま!
高度なテクニックを要する作品ですが、技巧面だけに注目せず、シューベルトが作り上げたやさしい世界観を表現できるよう、原曲を聴いてイメージをふくらませましょう。
ハンガリー狂詩曲 S.244 第2番 嬰ハ短調Franz Liszt

ピアノの魔術師フランツ・リストが手掛けた『ハンガリー狂詩曲』は全19曲。
なかでも第2番は特に知名度が高く、リスト自身やフランツ・ドップラーによって管弦楽用に編曲されたものも、たびたび演奏されています。
難易度の高いことでも知られている作品ですが、特に曲の終わり近くに設けられたカデンツァは腕の見せどころ。
自作のカデンツァを挿入して、より華やかに仕上げているピアニストもいます。
楽譜のまま弾きこなすだけでもハードな曲ですが、よりオリジナリティあふれる演奏を目指したい方は、挑戦してみてはいかがでしょうか?
おわりに
いかがだったでしょうか。
ピアノ上級者の方にオススメの聴き映えする作品たちは、いずれも難易度が高く、決して楽に弾けるものではありません。
ですが、苦労と努力を重ねて発表会の舞台で立派に演奏できれば、きっとこれからのピアノ人生への大きな自信へとつながるはずです。
「次の発表会は大曲に挑戦したい」、「聴き映えする曲で聴いてくださる方々をあっと驚かせたい」という方は、ぜひ自分にぴったりの曲を選んで練習に取り組んでくださいね!