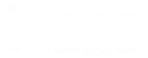【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲
易しく自分でも簡単に弾ける、そしてかっこよくて華やかな聞き映えする曲をお探しではありませんか?
ピアノを習い始めて間もない段階で出演する発表会では、無理もなく弾けるレベルでありながら、聴き映えする華やかな作品を選ぶことが重要です。
特にお子さまの場合は、本人の好みを優先しつつも、指の届く範囲などにも気を配りながら作品や楽譜を選定する必要があります。
そこで本記事では、ピアノを習い始めて間もないお子さまや、大人になってピアノをはじめた方の発表会曲としておすすめの、聴き映えする初級者向け楽曲をご紹介します。
音域の広さや演奏のポイントなどにも触れてきますので、ぜひ発表会曲選びの参考にしてくださいね。
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【幼児のピアノ曲】発表会で弾きたい!華やかなおすすめ作品を厳選
- 【6歳児向け】ピアノ発表会で映えるおすすめ楽曲をピックアップ!
- 【小学生2年生向け】ピアノの発表会で弾きたい!おすすめの名曲&有名曲
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【祝!発表会デビュー】初めてのピアノ発表会におすすめの曲を紹介
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品
- 【初級】ピアノ発表会にもオススメ!弾けたらかっこいいクラシックの作品
- ピアノをはじめた初心者におすすめ!大人も楽しめる楽譜10選
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【5歳児向け】ピアノ発表会にオススメの楽曲をピックアップ!
- 【幼児~小学生の子供向け】ピアノの難しい曲|コンクール課題曲から厳選
【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲(51〜60)
勇敢な騎手 「子供のためのアルバム」よりRobert Schumann

疾走感があふれる音の連なりと力強いリズムが印象的な名曲で、アルバム『子供のためのアルバム』に収録されています。
1848年に長女マリーの誕生日プレゼントとして作曲された本作は、わずか1分ほどの短い演奏時間ながら、豊かな音楽性と高い芸術性を備えています。
スタッカートを効かせた躍動的なフレーズと、イ短調の調性が生み出す緊張感が絶妙に調和し、馬に乗って駆け抜ける騎士の勇ましい姿が目に浮かぶようです。
シンプルな構成でありながら表現力に富んだ本作は、短い演奏時間で聴衆を魅了したい方や、力強い曲調がお好みの方におすすめです。
国際的なピアノ検定試験の課題曲としても採用され、世界中で親しまれている1曲です。
インディアンの踊りWilliam Gillock

アメリカ先住民の文化やリズムをモチーフにしたこの楽曲は、シンプルながらも力強いリズムと独特の旋律が魅力です。
太鼓のような左手の伴奏が印象的で、右手の旋律がそれに呼応するように展開されていきます。
一定のビートと三連符の組み合わせが用いられた本作は、男の子が憧れる力強さと躍動感にあふれています。
アルバム『Two Indian Dances』に収録された作品で、楽曲の背景にある文化や物語を想像しながら表現力を養える点も見どころ。
Gメジャーの調性で書かれた明るく活発な曲調は、発表会やコンクールでも映えることが間違いなしです。
ピアノソナタk.545 ハ長調Wolfgang Amadeus Mozart

穏やかで優美な旋律と、軽快なリズムが調和した作品です。
3楽章で構成された本作は、まるでひとつの物語を聴いているかのような魅力に溢れています。
第1楽章は明るく爽やかな旋律が印象的で、第2楽章では柔らかい表情を見せながら、優雅な雰囲気を醸し出します。
第3楽章では遊び心のある明るい旋律が心を弾ませてくれます。
1788年6月に書かれた本作は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの繊細な技巧と豊かな表現力が存分に活かされており、華やかで洗練された響きを楽しめます。
心温まる旋律とピアノならではの魅力が詰まった本作は、気分転換や癒しの時間を求める方におすすめの1曲です。
ソナチネ 第3楽章William Gillock

古典的なソナタ形式に基づきながら、明るく快活な雰囲気が魅力の本作。
現代的な感覚も取り入れた親しみやすいメロディーと構造で、ピアノ発表会での演奏に花を添えます。
アルバム『Accent on Analytical Sonatinas』に収録され、ロサンゼルス音楽教師協会のソナタ・コンテストでも課題曲として採用されています。
技術的な要素と音楽的表現のバランスが絶妙で、華やかな演奏効果も期待できます。
小学校高学年の生徒さんの実力を存分に引き出せる本作は、ピアノ発表会で聴衆を魅了するのに最適な1曲です。
【初級者向け】やさしい&弾きやすい!ピアノ発表会で聴き映えする曲(61〜70)
子供のためのアルバム Op.68 第8曲「勇敢な騎士」Robert Schumann

ドイツのロマン派を代表する作曲家、ロベルト・シューマンのピアノ曲、何だか難しそう……と思われる方も多いかもしれませんが、発表会でもおすすめできる作品はちゃんと存在します。
『乱暴な騎士』という邦題でも知られるこちらの『勇敢な騎士』は、短いながらも三部形式の楽曲構成で中間部の転調など練られた楽曲展開のドラマ性やロマン派らしい旋律を味わえる名曲で、技術的にもそこまで難しいものではないため、挑戦しやすい作品と言えましょう。
8分の6拍子というリズムと連続する3連符に注意しつつ、乱暴になりすぎない程度に力強く演奏してみてくださいね。
無言歌集 第1巻 Op.19 第4曲 ないしょの話Felix Mendelssohn

穏やかで優雅な旋律が心に染み入る優しい小品です。
1830年に書かれたこの楽曲は、メロディーが歌うように流れていき、まるで誰かに密かな思いを語りかけているような印象を受けます。
本作は楽譜が読める程度の演奏スキルがあれば十分に取り組める作品で、左手のシンプルな伴奏と右手の表情が豊かな旋律で構成されています。
ゆっくりとしたテンポで物語を紡ぐような雰囲気が魅力的で、歌詞がないにもかかわらず豊かな感情表現が込められています。
ロマン派音楽の優美さを味わいたい方や、表現力を磨きたい方におすすめの一曲です。
穏やかな時間の流れを楽しみながら、じっくりと練習に取り組んでみてはいかがでしょうか。
ミッキーマウスマーチJimmie Dodd

世界中で愛されているミッキーマウスのテーマソングとして作曲され、アメリカの子供向け番組『ミッキーマウス・クラブ』のオープニングテーマに起用されたことをきっかけに世界中で知られることとなった『ミッキーマウスマーチ』。
幅広い年代から人気のこの曲は、1オクターブ以内でメロディを演奏できる初心者の方でも弾きやすい楽曲です。
まずは指の動きをじっくり覚え、押さえる鍵盤をある程度把握できたら、ミッキーのハッピーオーラを表すかのような弾むリズムを付けて演奏してみましょう!