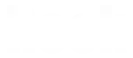従来のスタイルで鳴らされるロックの方法論とは違う、さまざまなアイデアや実験的な趣向を凝らして表現する音楽ジャンルがポストロックです。
定義としてはかなり曖昧な上にサブジャンルも多々あるのですが、ポストロックという括りの中でも世界的な成功を収めたバンドやアーティストは少なくありませんし、ここ日本でもポストロックの方法論に影響を受けた多く存在しているのです。
今回の記事では、最近ポストロックに興味を持ち始めた洋楽ファンに向けて「まずはこの1枚」な名盤の数々を一挙ご紹介します!
ポストロック全盛期の1990年代から2000年代のアルバムを中心としたラインアップとなっておりますから、ぜひチェックしてみてくださいね!
- 【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚
- 洋楽ポストパンクの名曲。まずは聴いてほしい人気曲まとめ
- プログレッシブロックの名曲。おすすめの人気曲
- 【初心者向け】洋楽ポストロックの人気曲。おすすめの名曲まとめ
- 【洋楽】まずはこの1曲!オルタナティブロックの名曲・人気曲
- 【まずはここから!】ジャズロックの名曲。おススメの人気曲
- ダークサイケの名曲|暗く怪しいサイケの世界へ…
- 【2026】まずはここから!おすすめの洋楽ポストロックバンドまとめ
- 偉大なアメリカのロックバンド【All Time Best】
- 【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ
- プログレッシブロックの名盤。一度は聴きたい人気のアルバムまとめ
- 洋楽ロックの名盤。一度は聴きたいオススメのアルバムまとめ
- 【洋楽】90年代エモコアの名盤。まずは聴いてほしい1枚
【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚(1〜10)
Laughing StockTalk Talk

スリントの『Spiderland』と並んで、90年代初頭のポストロックの源流的な作品として高い評価を受けている作品が、イギリスの音楽グループであるトーク・トークが1991年に発表した通算5枚目のアルバムにしてラスト・アルバム『Laughing Stock』です。
初期のポストロックはアンダーグランドなハードコア出身のミュージシャンが多いイメージもありますが、1981年に結成された彼らは何とデュラン・デュランにも通じるニューロマンティックとされるシンセポップを鳴らしていたキャリアを持つ異色の存在なのですね。
キャリアを重ねるごとに実験的かつアーティスティックな方向へと舵を切った彼らの音楽性は、1988年に発表された4枚目のアルバム『Spirit of Eden』で顕著となって内外から高い評価を獲得。
その後はメンバーの脱退を経て生まれた作品が、こちらの『Laughing Stock』なのですね。
ジャズやクラシックの要素を即興演奏を軸としたアンサンブルで昇華、どこか曖昧で浮遊するミニマルな音世界はまさにロックというジャンルの脱構築と呼べるものかもしれません。
ポストロック勢のみならず、オルタナティブロックやブリストル系のアーティストたちにも影響を与えたサウンドであり、まさに真の意味で「オルタナティブ」な作品であり、ポストロックを語る上でも絶対に欠かせない名盤をぜひ一度聴いていただきたいですね。
Don, AmanSlint

ポストロックというジャンルにおいて最も重要なバンドの1つが、1986年にアメリカはケンタッキー州ルイビルにて結成されたスリントです。
アンダーグラウンド・シーンにおいて活動を続けた彼らは決して商業的に成功を収めたようなバンドではありませんが、ハードコア由来の張りつめたような緊張感が支配するバンド・アンサンブルが織り成す静と動のサウンドは、モグワイやゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーといった、後にポストロックと呼ばれるバンドの中心的な存在となる面々に多大なる影響を及ぼしたのですね。
彼らが1991年にリリース、その後すぐに解散してしまったためにラスト・アルバムとなった『Spiderland』は、まさにポストロックやマスロックと呼ばれるジャンルの金字塔的な1枚として名高い名盤中の名盤!
水面に顔を出してこちらを見つめるメンバーのモノクロ写真が使われたジャケットも印象深い本作は、上述したように他に類を見ない独創的なギター・サウンドで後続のバンドに強烈なインスピレーションを与えました。
アメリカのハードコアやパンク、オルタナティブ・ロックなどの重要作品を多く発表した名門レーベルのタッチ・アンド・ゴー・レコーズからリリースされたということも踏まえつつ、ポストロックの源流を知りたい方は確実にチェックしてみてくださいね。
The Summer EndsAmerican Football

スポーティで男らしいバンド名ですが、そのようなイメージとは真逆の繊細かつ緻密なバンド・アンサンブルで生まれる楽曲の美しさが高い評価を受けるアメリカン・フットボール。
ジョーン・オブ・アークなどのバンドを率いて、USインディ界においてカリスマティックな存在として著名なティム・キンセラさんの実弟であり、ともに90年代エモコアの重要バンドキャップン・ジャズのメンバーとして活動していたマイク・キンセラさんを中心として1997年に結成したアメリカン・フットボールは、EPとアルバム1枚ずつを残して実質3年程度の活動で解散した伝説のバンドとして一部のマニアには知られていました。
2014年に奇跡的な再結成を果たして日本にも来日、新作をリリースするなど2020年代の今もマイペースながら活動を続けています。
そんな彼らが1999年に発表したセルフタイトルのデビュー・アルバムは、インストゥルメンタルを重視したマスロックと呼ばれる変拍子を織り交ぜた複雑なアンサンブルをあくまで柔らかで繊細な感性で昇華、ジャズ的な要素をも感じさせるアルペジオの妙とナイーブなボーカルが織り成すサウンドで、日本のポストロック系のバンドにも多大なる影響を及ぼしました。
限りなく繊細でありながら、パンクやハードコア出身ならではの張りつめた緊張感が常に感じ取れる、という点は改めて強調しておきたいところ。
toeなどのバンドがお好きな方も、絶対に聴いてほしい大傑作です!
DjedTortoise

ポストロックとされるバンドの中でも、最も有名かつ重要な存在の1つがトータスでしょう。
いわゆる「シカゴ音響派」をけん引した存在であり、ツワモノぞろいのメンバーが持つ卓越した演奏テクニックと膨大な音楽知識、当時としては画期的なパソコンのハードディスク・レコ―ディングなどを採用するなど、まさに「ロック以降」のサウンドを展開して世界中にポストロックというジャンルを知らしめたバンドです。
彼ら自身はポストロックにとらわれることもなく、生のバンド・サウンドによるアプローチやテープ録音への回帰など、さまざまな手法を凝らして常に音楽シーンにおいて革新的なバンドとして君臨し続けていることが素晴らしいですよね。
そんなトータスにとっての出世作であり、ポストロックの金字塔といっても過言ではない作品が、1996年にリリースされたセカンド・アルバム『Millions Now Living Will Never Die』です。
スリントのギタリストだったデイヴィッド・パホさんが加入してからは初となるアルバムであり、静と動を駆使した轟音系のポストロックとはまた違う、従来のロックのフォーマットにとらわれない多彩なアイデアが込められた緻密な構成が織り成す楽曲群は、インストでありながらも豊かなメロディを感じさせ、聴くだけでそれが1つの貴重な音楽的体験であると断言してしまいましょう。
Svefn-g-englarSigur Rós

アイスランドが生んだ至宝、シガー・ロス。
ポストロックの文脈で有名となったバンドではありますが、今となってはそのような枕詞は不要なくらいに、アイスランド出身の最も有名なグループの1つとして世界的な知名度を誇ります。
母国アイスランド語と「ホープランド語」と呼ばれる造語による歌詞と中性的なボーカルによる繊細なメロディ、静と動を駆使したポストロック~シューゲイザー的なアンサンブルとアンビエントにも通じる静ひつな音響空間、限りなく美しい音の粒子が時に不穏なノイズへと変化する一筋縄ではいかない音世界は、白昼夢と悪夢を行き来するかのようなドラマチックな音楽的体験をリスナーに与えてくれます。
日本語で「良き船出」という意味を持つ1999年にリリースされたセカンド・アルバム『Ágætis byrjun』は、そんなシガー・ロスの名前を世界的に知らしめるきっかけとなった1枚。
ここ日本においても、当時このアルバムで彼らのことを知ったという音楽ファンも多いでしょう。
ヨン・ソゥル・ビルギッソンさん、通称ヨンシ―さんによる天使のようなファルセット・ボイスと弓でギターを奏でる独特のスタイルから生まれる旋律、上品なストリングスの導入、リスナーをここではないどこかへと誘う轟音ノイズ……シガー・ロスに興味を持った方は、まずこの1枚をオススメします!
East HastingsGodspeed You! Black Emperor

1976年に暴走族をテーマとした日本のドキュメンタリー映画『ゴッド・スピード・ユー! BLACK EMPEROR』からそのグループ名を拝借した、という時点で普通のバンドではないことが強烈に伝わってきますよね。
カナダ産ポストロックの聖地、モントリオール出身のゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーは、1994年に結成された大所帯のバンドであり、大作指向で実験的な音楽性と政治的な主張を込めた楽曲およびアートワークなど、独自のスタンスで活動を続ける存在としてシーンに衝撃を与えました。
2003年に活動休止するも2010年には活動を再開、2020年代に至る今も彼らにしか成し得ない音世界で世界中の熱狂的なファンを喜ばせ続けています。
本稿で紹介しているのは、1997年にリリースされた記念すべきファースト・アルバム『F♯ A♯ ∞』です。
10名ほどのミュージシャンが参加した本作は、全3曲で組曲のような構成となっており、フィールドレコ―ディングやサンプリングを使った重苦しく不穏な空気感と、伝統的なロック・バンド的な楽器以外にもチェロやバイオリンなども使われた大所帯ならではの複雑なアンサンブル、この世の終わりのような静寂から感情の揺れをそのまま形としたような爆発的なノイズまで、他に類を見ないサウンドの衝撃度は今も語り草となっておりますね。
この黙示録の如き世界観に引きずり込まれたら最後、彼らのとりことなってしまうでしょう!
Mogwai Fear SatanMogwai

極端な静寂と耳をつんざくほどの轟音ギターが鳴らされるすさまじいバンド・アンサンブルで、シーンをあっと言わせたのがスコットランドはグラスゴー出身のモグワイです。
ここ日本における人気・知名度も抜群で、今やポストロックという枠内をこえて数え切れないほどのバンドへ影響を与えた偉大な存在ですよね。
作品をリリースするごとに音楽性にも変化が見られ、インストゥルメンタル主体ではありますが、曲によってはボーカルを取り入れるなど常に意欲的な音楽的冒険を忘れない彼らですが、今回はトレードマークと言える強烈な轟音ギターが味わえる初期の大傑作ファースト・アルバム『Mogwai Young Team』を紹介します。
富士銀行恵比寿支店の写真を使ったアルバム・ジャケットが問題視され、国内盤ではロゴの部分が削除されたという曰くつきの作品でもあるのですが、内容の素晴らしさは2020年代の現在も色あせないどころか、このアルバムがなかったら生まれなかった後続のバンドも多くいただろう、と本作を聴いた方であれば誰もが納得することでしょう。
ゆったりと展開していくドラマチックな楽曲の中で、ハードコアから影響を受けた暴力的なまでのフィードバック・ノイズは明確な説得力を放ち、夢想的なシューゲイザー的な轟音とは全く違うというのも強調しておきたいところ。
ライブでも定番の楽曲であり、アルバムのラスト曲にして16分をこえる大作『Mogwai Fear Satan』を聴けば、この楽曲を当時20歳そこそこのメンバーが作り上げたのか……と思わず脱帽してしまうはず!