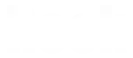【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚
従来のスタイルで鳴らされるロックの方法論とは違う、さまざまなアイデアや実験的な趣向を凝らして表現する音楽ジャンルがポストロックです。
定義としてはかなり曖昧な上にサブジャンルも多々あるのですが、ポストロックという括りの中でも世界的な成功を収めたバンドやアーティストは少なくありませんし、ここ日本でもポストロックの方法論に影響を受けた多く存在しているのです。
今回の記事では、最近ポストロックに興味を持ち始めた洋楽ファンに向けて「まずはこの1枚」な名盤の数々を一挙ご紹介します!
ポストロック全盛期の1990年代から2000年代のアルバムを中心としたラインアップとなっておりますから、ぜひチェックしてみてくださいね!
- 【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚
- 洋楽ポストパンクの名曲。まずは聴いてほしい人気曲まとめ
- プログレッシブロックの名曲。おすすめの人気曲
- 【初心者向け】洋楽ポストロックの人気曲。おすすめの名曲まとめ
- 【洋楽】まずはこの1曲!オルタナティブロックの名曲・人気曲
- 【まずはここから!】ジャズロックの名曲。おススメの人気曲
- ダークサイケの名曲|暗く怪しいサイケの世界へ…
- 【2026】まずはここから!おすすめの洋楽ポストロックバンドまとめ
- 偉大なアメリカのロックバンド【All Time Best】
- 【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ
- プログレッシブロックの名盤。一度は聴きたい人気のアルバムまとめ
- 洋楽ロックの名盤。一度は聴きたいオススメのアルバムまとめ
- 【洋楽】90年代エモコアの名盤。まずは聴いてほしい1枚
【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚(1〜10)
First breath after comaExplosions in the sky

アメリカはテキサス出身のエクスプロージョンズ・イン・ザ・スカイは、ポストロックと呼ばれるバンドの中でも、長尺な楽曲の中で静と動のパートをうまく使ったドラマチックなアンサンブルが特徴的な、初期のモグワイ辺りを始祖とする轟音ギターを鳴らすグループの代表的な存在です。
ポストロックやエクスペリメンタル系の作品を多くリリース、日本のMONOやENVYといったバンドの作品も扱っている老舗のレーベル「Temporary Residence」の看板バンドであり、彼らに影響を受けた後続のバンドも多くいるのです。
彼らのアルバムはどれも完成度が高く、作品によって轟音ポストロックにとらわれないサウンドにも挑戦しているのですが、本稿では最高傑作として評価されることも多い2005年リリースの名盤サード・アルバム『The Earth Is Not The Cold Dead Place』を紹介しましょう。
繊細なギターのアルペジオはさらに研ぎ澄まされ、轟音ギターは初期の荒々しさや重苦しさとは違う、どこか救いすら感じさせる眩い光が差し込まれたような響きでリスナーを包み込んでいきます。
1曲1曲の完成度も高く、彼らの名前が広く知られるきっかけとなった作品であり、最高傑作と呼ばれることも多い1枚ですから、初めて彼らのサウンドを聴く方にもオススメと言えるでしょう。
轟音ギターのカタルシスをもっと味わいたい、という方は前作『Those Who Tell The Truth Shall Die,Those Who Tell The Truth Shall Live Forever』を推薦します!
WindowThe Album Leaf

トータスなどに代表されるシカゴ音響派、そしてモグワイなどの轟音ギターで魅せる静と動の世界を持ったポストロックとされるバンドとはまた違う、繊細なエレクトロニカ的な要素と美メロが際立つポストロックを鳴らして高い評価を受けているのが、カリフォルニアはサン・ディエゴ出身のジミー・ラヴェルさんによるソロ・プロジェクトのアルバム・リーフです。
ジミーさんはもともとトリステザというポストロック系のバンドや、グラインドコアやハードコア・パンクの要素を独自に織り交ぜた音楽性と昆虫の衣装でのライブ・パフォーマンスで知られるザ・ロカストなどのメンバーとして活動していた経歴を持ち、1998年に自身のソロ・プロジェクトとしてスタートさせたのがアルバム・リーフなのですね。
初期は知る人ぞ知る存在でしたが、2004年にあのシガー・ロスの所有するスタジオで録音された大傑作サード・アルバム『In a Safe Place』が高く評価され、以降は美メロ系のポストロック好きには周知の存在としてここ日本でも熱心なファンを得るまでに至りました。
『In a Safe Place』はマルチ・インストゥルメンタリストであるジミーさんを中心として、ヨンシ―さんを除くシガー・ロスのメンバーも参加、アイスランドならではのひんやりとした叙情性と、音の細部にまでUSハードコアの出自を感じさせる独特の緊張感が見事に融合した叙情系ポストロックの名盤。
必然として鳴らされるグリッチ・ノイズ、数曲で聴くことのできるジミーさんの繊細なボーカル入りの曲も含めて、全曲最高です!
Fire Back About Your New Baby’s SexDon Caballero

ポストロックに興味を持ち、調べていく中で「マスロック」なるジャンルを発見して一体どんなジャンルなのかな、と思われた方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
一般的にはキング・クリムゾンなどの超絶技巧のプログレやスティーヴ・ライヒさんなどのミニマル・ミュージックなどからも影響を受け、変拍子満載の複雑なリズム展開やギター・フレーズ、不協和音にノイズがちりばめられたサウンドが特徴とされるジャンルです。
実は商業的に成功しているバンドの中でもマスロック由来のアンサンブルを取り入れているバンドも多く、掘り下げるとなかなか奥深いジャンルなのですね。
本稿の主役であるドン・キャバレロは、ドラマーのDamon Cheさんを中心として1991年に結成されたマスロック~ポストロック系の代表的なバンドの1つ。
後にバトルスを結成するイアン・ウィリアムスさんが在籍していたことでも知られていますね。
現在も活動を続ける彼らが最初の解散前に発表した通算4枚目のアルバム『American Don』は、変則的なギターのリフと手数の多いドラムスを軸として複雑怪奇に展開していく楽曲展開が実にクールでカッコ良く、ピンと張りつめた緊張感の中で織り成すバンド・アンサンブルの妙は今もなお色あせることはありません。
インストを聴き慣れない方には最初は戸惑いもあるかもしれませんが、この音のおもしろさに気付けば、必ずや音楽の趣味も広がっていくことでしょう。
【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚(11〜20)
AtlasBattles

2000年代中盤以降、まさに「ロックの先」を行く革新的なバンドの1つとしてシーンを激震させた存在といえば、2020年代の現在は2人組として活動を続けるバトルスでしょう。
ドン・キャバレロなどのマスロック・バンドで活動したギタリストのイアン・ウィリアムスさん、90年代のオルタナティブメタル・バンドとして著名なヘルメットの黄金期を支えたドラマーのジョン・ステイナーさん、もとリンクスのデイヴ・コノプカさん、そしてフリージャズの世界で巨匠と呼ばれるアンソニー・ブラクストンさんの実子であるタイヨンダイ・ブラクストンさんという強烈な4人組として2003年に結成された彼らは、他に類を見ない独創的な音楽を鳴らしていた初期のEP作品の時点で注目を集めたバンドでした。
ここ日本では早くから来日公演を果たしてたこともあり、耳の早い音楽ファンの間では話題となっていましたね。
多彩なルーツを持つ彼らの音楽性を一言で述べるのは困難ですが、2007年に満を持してリリースされたデビュー・アルバム『Mirrored』は、ポストロック的なサウンドはもちろん、エレクトロニカなどの電子音楽にハードコアやオルタナティブロックなど、さまざまな要素を圧倒的な演奏技術と先鋭的なセンスで融合させた名盤でありつつ、キャッチーなフックをも兼ね備えたバランスの良い作品として初心者にもぜひオススメしたい逸品ですね。
A French GalleasseRachel’s

現在はいわゆるポスト・クラシカルのミュージシャンとして2014年には来日も果たしており、世界中で高い評価を受けるピアニスト兼作曲家、アメリカはケンタッキー州出身のレイチェル・グライムスさんが在籍してたバンドのレイチェルズ。
1990年代の半ばに活動した伝説のポスト・ハードコア系のバンド、RODANのギタリストであったジェイソン・ノーブルさん、そしてレイチェルさんらを中心として1991年に結成されたレイチェルズは、いわゆる伝統的なロックの文脈からは逸脱したサウンドを指向しており、室内楽やマイケル・ナイマンさんなどのミニマル・ミュージックからの影響を感じさせるサウンドが後の「ポスト・クラシカル」の源流としても評価されているのですね。
他の著名なポストロック系のバンドと比べて知名度は劣りますが、ポストロックを掘り下げていく上でレイチェルズの鳴らす音楽はぜひチェックしていただきたいところ。
本稿で取り上げている『Selenography』は1999年にリリースされた、通算4枚目となるアルバム。
ロック的なビートは皆無、上品かつミニマルな室内楽のアンサンブル、そして繊細なハープシコードの音色が胸を打つ珠玉の1枚です。
ハードコア出身のメンバーが中心人物でありながら、このような静ひつな音世界を作り上げたということ自体が興味深いですし、そういった激しい音楽をルーツに持つミュージシャンがポストロックには多く存在しておりますから、そういった点も含めて注目してほしいですね。
Svefn-g-englarSigur Rós
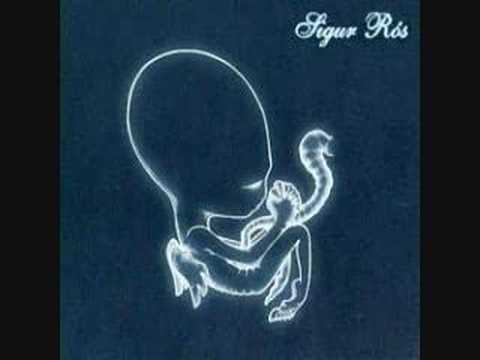
アイスランドのポスト・ロック・バンドであるSigur Rósによって、1999年にリリースされたトラック。
彼らの母国外での最初のリリースとなったEPの、タイトル・トラックとして使用されました。
映画「Vanilla Sky」や「Cafe de Flore」などで使用されています。
FredericiaDo Make Say Think

カナダ出身のポストロック系の大所帯のバンドといえば、ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーや少し毛色は違いますがブロークン・ソーシャル・シーンなどが挙げられますよね。
そのブロークン・ソーシャル・シーンのメンバーも在籍しているのが、カナダはトロント出身のドゥー・メイク・セイ・シンクです。
ギターやベースにドラムといったロック・バンドの基本的な楽器に加えて、トランペット奏者やバイオリン奏者などがメンバーとして参加、ジャズ的な素養も感じさせる長尺なインストゥルメンタル・ナンバーを特徴としています。
基本的に生楽器を中心とした温かみのあるアンサンブルを軸としながらも、ドラマチックな轟音ポストロックとはまた違った形でうなりを上げる轟音ギター、熱狂的なホーン・セクション、時にはドラムスにまでディストーションをかけた強烈なサウンド、不協和音もちりばめられた一筋縄ではいかないエクスペリメンタルな楽曲展開が、彼らならではのフリーキーでおもしろみのある音世界を演出。
同時に、実際に彼らのライブを見た私個人的には祝祭のような輝きに満ちた音楽に対する喜び、無邪気な好奇心が感じ取れるのが素晴らしいのですね。
そんな彼らの音世界が1つの頂点を迎えた2003年リリースのアルバム『Winter Hymn Country Hymn SecretHymn』を、ぜひ聴いてみてください!