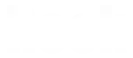【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚
従来のスタイルで鳴らされるロックの方法論とは違う、さまざまなアイデアや実験的な趣向を凝らして表現する音楽ジャンルがポストロックです。
定義としてはかなり曖昧な上にサブジャンルも多々あるのですが、ポストロックという括りの中でも世界的な成功を収めたバンドやアーティストは少なくありませんし、ここ日本でもポストロックの方法論に影響を受けた多く存在しているのです。
今回の記事では、最近ポストロックに興味を持ち始めた洋楽ファンに向けて「まずはこの1枚」な名盤の数々を一挙ご紹介します!
ポストロック全盛期の1990年代から2000年代のアルバムを中心としたラインアップとなっておりますから、ぜひチェックしてみてくださいね!
- 【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚
- 洋楽ポストパンクの名曲。まずは聴いてほしい人気曲まとめ
- プログレッシブロックの名曲。おすすめの人気曲
- 【初心者向け】洋楽ポストロックの人気曲。おすすめの名曲まとめ
- 【洋楽】まずはこの1曲!オルタナティブロックの名曲・人気曲
- 【まずはここから!】ジャズロックの名曲。おススメの人気曲
- ダークサイケの名曲|暗く怪しいサイケの世界へ…
- 【2026】まずはここから!おすすめの洋楽ポストロックバンドまとめ
- 偉大なアメリカのロックバンド【All Time Best】
- 【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ
- プログレッシブロックの名盤。一度は聴きたい人気のアルバムまとめ
- 洋楽ロックの名盤。一度は聴きたいオススメのアルバムまとめ
- 【洋楽】90年代エモコアの名盤。まずは聴いてほしい1枚
【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚(11〜20)
Ghost Ship in a StormJim O’Rourke

愛嬌のあるルックスも印象的なジム・オルークさんは、革新的かつ先鋭的なミュージシャンとして世界的に有名な存在です。
ソロ・アーティストとしてオリジナル・アルバムや映画のサントラ作品などの素晴らしい作品を発表し続け、ガスター・デ・ソルやソニック・ユースのメンバーとして参加、海外や日本を問わず多くのアーティストのプロデュースなど、オタク気質で多岐に渡る音楽活動とジャンルレスな音楽性を持つオルークさんを何か1つのジャンルにカテゴライズするのは困難なほど。
現在は日本に在住しているオルークさんをポストロックの文脈で語るなら、やはり挙げておきたい作品が1999年にリリースされた名盤ソロ・アルバム『Eureka』でしょう。
日本の漫画家、イラストレーターの友沢ミミヨさんによるインパクトの強いジャケットも印象的な本作は、本人にとっては初となる「歌モノ」指向のアルバムであり、同時に雑食な音楽性に裏打ちされた奇妙なポップさが他にはない個性を生み出した傑作なのですね。
バート・バカラックさんのカバーもさらりと盛り込んだセンス、実に牧歌的な歌心、一音一音に対する偏執的なまでのこだわりなど、ジャケットのイメージ通りどこかブラックなユーモアを兼ね備えたオルークさん流儀のポップネスは、2020年代を過ぎた今だからこそ改めて若い音楽ファンにも聴いてほしいですね!
The Audio PoolThe Album Leaf

The Album Leafは、1998年にカリフォルニア州サンディエゴで結成されたJimmy LaValleによるソロ・ミュージック・プロジェクトです。
このトラックは2001年にリリースされた2枚目のアルバム「One Day I’ll Be on Time」に収録されています。
A Street SceneBark Psychosis

「ポストロック」という音楽ジャンル名は、批評家であるサイモン・レイノルズさんがとあるバンドのアルバムを評する際に使った言葉が起源、とされています。
そのバンドこそがイギリスはロンドン出身のバーク・サイコシスであり、彼らが1994年にリリースしたデビュー・アルバム『Hex』が該当の作品なのですね。
ポストロックを定義付けた重要なアルバムと言えますし、ジャンルを掘り下げていく上では避けては通れない作品だと言えましょう。
バンド自体はデビュー・アルバムをリリース後に解散、2004年以降は中心人物にしてプロデューサーやミキサーとしても活躍しているグラハム・サットンさんのソロ・プロジェクトとして再始動しています。
こちらの『Hex』ですが、作品のリリース当初は残念ながら商業的な成功を収めることはできませんでしたが、その先鋭的な作風が高く評価され、前述したようにポストロックの歴史における金字塔的な作品として君臨し続けています。
ロック的なダイナミズムを意図的に排除、ジャズ的な要素を取り入れた緩やかなアンサンブルとアンニュイなボーカルを軸として、細部にまでこだわりを見せるアンビエントな音響空間、生楽器と打ち込みやサンプリングの絶妙な融合から生まれるインテリジェンスな音楽は、リリース時点では「ポストロック」としか呼べなかったというのも理解できるはず。
90年代英国ロックの裏名盤としても、ぜひ。
Distant ShoreDirty Three

オーストラリアはメルボルンにて1992年に結成されたダーティ・スリーは、多くのポストロック・バンドの中でもギターとドラム、そしてバイオリンという変則的なトリオとして世界的に知られているバンドです。
リズムを担うドラムスとハーモニーやメロディを生み出すギター、そして隙間の多いサウンドを埋めるように物悲しげな旋律で存在感を放つバイオリンという特異なアンサンブルは、既存のロックとは全く違った音世界を生み出しています。
スロウコアの文脈で語られることもあるミニマルな展開、ロードムービー的と称されるイメージを持った世界観は、まさに唯一無二の個性を放っているのですね。
そんな彼らが1998年にシカゴの名門レーベル、タッチ・アンド・ゴーよりリリースしたサード・アルバム『Ocean Songs』は、彼らの名前を広く世に知らしめ、高い評価を受けた素晴らしい傑作。
アルバムのタイトルにあるように、楽曲にも海にまつわる題名が付けられており、一種のコンセプチュアルな作品としても楽しめる本作は、USインディーズ~ハードコア・シーンにおける最重要ミュージシャン兼エンジニア、スティーヴ・アルビニさんがレコーディング・エンジニアを手掛けたこともあり、ひりついた緊張感に満ちた音像も印象深いですね。
バストロやガスター・デル・ソウルといったバンドを率いたデイヴィッド・グラブスさんもゲスト参加、シカゴ人脈も関わった作品という意味でも、ポストロックを掘り下げたい方には必ずチェックすべき作品だと言えましょう。
Await Rescue65daysofstatic

2000年代半ば、イギリスのシェフィールドから突如現れた65デイズオブスタティックは、ポストロックなどを愛好する音楽ファンに衝撃を与えたインストゥルメンタル主体のバンドです。
彼らのサウンドの特徴は、ロックの文脈から外れた方法論で新たなサウンドを生み出すポストロック系のバンドとは違い、ひんやりとした質感の電子音、凶暴な轟音ギターとすさまじい手数の多さで打ち鳴らされる人力ブレイクビーツ、叙情的なピアノのフレーズに荘厳なメロディが展開していくといったようなものであって、その音楽スタイルのインパクトは「モグワイ・ミーツ・エイフェックス・ツイン」と形容されたほど。
その評価が決して誇張ではないことは、特に初期の作品を聴けば理解できるはず。
今回紹介している『One Time for All Time』は2005年にリリースされた彼らにとっては通算2枚目となるアルバムであり、デビュー時のスタイルをよりダイナミックに、さらにドラマチックに仕上げた逸品です!
本作を引っ提げてサマーソニック2006に来日、単独来日公演も果たしたことが懐かしく思い出されます。
冷徹な知性とあふれ出す激情が渾然一体となって迫りくる轟音サウンド、思わずはっとさせられるピアノの導入、流麗なストリングス……まずは本稿でも取り上げているアルバム収録曲にして名曲『Await Rescue』を聴いて、その素晴らしさを体感してみてくださいね。
The Everyday World of BodiesRodan

スリントやバストロといった、ポストロック~マスロックの源流としても評価されている伝説的なバンドたちまでさかのぼった方であれば、ぜひ手にしていただきたいのがスリントと同じくアメリカはケンタッキー州ルイヴィルが生んだ伝説、ロダンです。
活動期間は3年程度、リリースしたオリジナル・フル・アルバムはたったの1枚ではありますが、冒頭で述べたようにポストロックやマスロック、ポスト・ハードコアのひな形のようなサウンドを作り上げた彼らの音楽は非常に高く評価されているのです。
後にジューン・オブ・44を結成するジェフ・ミューラーさん、マルチプレイヤーにしてシンガーソングライターとしても著名なタラ・ジェイン・オニールさんといったメンバーが在籍し、ゲスト参加していたメンバーがレイチェルズへと発展するといったように、USインディーズの裏歴史をたどる上でも絶対に欠かせないバンドなのですね。
こちらの『Rusty』には、それこそレイチェルズにも通じる「静」のパートを軸とした『Bible Silver Corner』のような楽曲もあれば、硬質なギターやドラムスがソリッドな緊張感と爆発的なサウンドを生み出す変則ハードコア・チューン『Shiner』があり、そのどちらの要素も内包した11分ごえの大作『The Everyday World of Bodies』といった曲も含まれているのです。
決して聴きやすい音というわけではないのですが、少しでも本作に興味を持たれた方はぜひCDやレコードを手にしてみてほしいですね。
【洋楽】ポストロックのすすめ~基本の名盤・オススメの1枚(21〜30)
RespiraTristeza

叙情的なエレクトロニカやポストロックを融合させた美しい音楽で、ここ日本でも熱心なファンの多いジミー・ラヴェルさんのソロ・プロジェクト、アルバム・リーフ。
そのジミーさんがかつてギタリストとして在籍していたバンドが、ポストロックの名バンドであるトリステザです。
ポストロックやエモといったジャンルに詳しい方でないとあまり知られていないバンドかもしれませんが、とくにアルバム・リーフがお好きでトリステザを知らない、もしくは叙情性豊かなインストゥルメンタル・サウンドを鳴らすバンドを探しているという方であれば、ぜひ知っていただきたい存在なのですね。
今回は、ジミーさん在籍時の2000年にリリースされた傑作アルバム『Dream Signals In Full Circles』を紹介しましょう。
揺らめくようなギターのアルペジオと淡い音像で紡がれる音世界は心地良さを感じさせ、それでいて芯の強さを持ったリズム隊が生み出す反復するビートが、雰囲気重視のバンドとは一線を画す説得力を生み出しています。
この音をハードコアや激情エモーショナル・コアといったジャンル出身のミュージシャンたちが鳴らしている、ということ自体が素晴らしい。
2000年代以降の日本のポストロック系のバンドにも大いに影響を与えた名盤です!