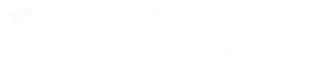【小学生向け】みんなで楽しめるお正月クイズ!意外と知らない豆知識を3択で楽しく学ぼう
お正月といえば、おせち料理やお年玉、初詣と楽しみがいっぱいですよね。
だけれど、どうして鏡餅にみかんが乗っているの?
おみくじを引いた後はどうすればいいの?
意外に知らないお正月の豆知識、お子さんに聞かれて答えられなかった経験はありませんか?
そこでこちらでは、子供も大人もみんなで楽しめるお正月にまつわるクイズを集めました。
年神様のこと、初夢の正しいタイミング、お雑煮の由来など、知っているようで知らなかった日本の伝統が盛りだくさん。
お正月休みに親子で挑戦しながら、日本の文化をより深く味わってみてくださいね!
- お正月クイズで盛り上がろう!日本のお正月に関する一般問題
- 【子供向け】1月の雑学クイズ&豆知識問題。お正月を楽しく学ぼう
- 思わず誰かに話したくなる!1月の雑学&豆知識特集
- 小学生向けの盛り上がるクイズ。みんなで一緒に楽しめる問題まとめ
- 【簡単】小学生向けのなぞなぞ
- 【子供向け】12月の雑学クイズ&豆知識問題!行事や季節のことを学べる!
- 【簡単で面白い】高齢者にオススメのお正月クイズ
- 【小学生向け】盛り上がるクリスマスクイズ!楽しく学べる問題
- 【子供向け】今日のクイズまとめ。今日にまつわるクイズで遊ぼう!【2026年1月】
- 【ひっかけクイズ】子供から大人まで盛り上がるクイズ問題
- 思わず誰かに話したくなる!12月の雑学&豆知識特集
- 【高齢者向け】1月のクイズで脳トレ。お正月や冬の雑学で盛り上がろう
- 【楽しい!】クリスマスパーティーで盛りあがるクイズ
【小学生向け】みんなで楽しめるお正月クイズ!意外と知らない豆知識を3択で楽しく学ぼう(1〜10)
おせち料理に入っている数の子は何の卵?
- サケ
- ニシン
- トビウオ
こたえを見る
ニシン
数の子は、ニシンの卵です。おせち料理に使われる数の子は、子孫繁栄や家族の繁栄を願う縁起物として、日本のお正月には欠かせない食材です。ニシンは大量に卵を産むことから、その卵である数の子も「子宝に恵まれるように」という意味を込めて食べられています。プチプチとした食感も特徴的で、古くから日本の伝統的な正月料理として親しまれています。
おせち料理をお重に詰める理由は何?
- 洗い物の負担を減らすため
- おすそわけするため
- 福やめでたさが重なるようにとの願い
こたえを見る
福やめでたさが重なるようにとの願い
おせち料理をお重に重ねて詰めるのは、福やめでたさが幾重にも重なって訪れるようにという願いが込められているためです。日本の伝統的な文化では「重ねる」ことに意味があり、家族の幸せや繁栄が何重にも続くようにとの願いが込められています。そのため、見た目の美しさや保存のためだけでなく、縁起の良さを大切にした日本らしい風習として受け継がれているのです。
童謡の『お正月』を作曲したのは誰?
- 古関裕而
- 滝廉太郎
- 三木たかし
こたえを見る
滝廉太郎
童謡『お正月』は、日本の伝統的なお正月の風景を歌った有名な童謡です。この曲は明治から大正時代の作曲家、滝廉太郎さんによって作曲されました。滝廉太郎さんは『荒城の月』や『花』などの名曲も手がけ、日本の音楽史に大きな影響を与えた人物です。『お正月』は子どもたちから大人まで幅広く親しまれ、お正月シーズンには学校や家庭でよく歌われていますね。
【小学生向け】みんなで楽しめるお正月クイズ!意外と知らない豆知識を3択で楽しく学ぼう(11〜20)
羽根つきの罰ゲームでは顔に何を塗る?
- 生クリーム
- 絵の具
- 墨
こたえを見る
墨
羽根つきは日本のお正月の伝統的な遊びの一つ。また羽根つきで負けたときの罰ゲームとして、顔に墨を塗るのが昔からの習わしです。黒色は鬼が嫌う色とされており、魔除けの意味を込めてこの風習が生まれたのです。墨を顔に塗ることで笑いが生まれ、お正月ならではの和やかな雰囲気を楽しめますよね。昔から子どもから大人まで親しまれている楽しい風習です。
香川県ではお雑煮にどんなおもちを入れる?
- あんこ入りのおもち
- 草もち
- きなこもち
こたえを見る
あんこ入りのおもち
香川県のお雑煮の特徴は、白味噌仕立ての汁にあんこ入りのおもちを入れることです。この珍しい組み合わせは、香川県独自の文化として有名で、多くの県民が正月にこのスタイルでお雑煮を食べます。甘いあんこと白味噌のまろやかな味わいが絶妙に合うことから、長年親しまれています。また、お雑煮には地域によってその土地ならではの材料やおもちの形・味付けがあるため、全国各地の違いと比べてみるのも面白いですよ。
おせち料理に入っている栗きんとんに込められている意味は?
- 健康運
- 金運
- 恋愛運
こたえを見る
金運
栗きんとんは、おせち料理の中でも特に人気のある一品で、その鮮やかな黄金色は金塊や財宝を連想させることから「金運アップ」の象徴とされています。新しい年の始まりに栗きんとんを食べることで、家庭や自分自身にたくさんの豊かさや財産が訪れるように、という願いが込められています。栗きんとんの鮮やかな色合いが、お祝いの席を華やかにしてくれますね。
鏡餅を乗せている台の名前は?
- お膳
- 三方
- 神棚
こたえを見る
三方
三方は日本の伝統的な儀式や神事で使用される台で、お正月には鏡餅を乗せるために用いられます。四角形に作られた木製の台の三面に穴が空いているのが特徴で、残りの一面が祭壇側となります。鏡餅を三方に乗せて神様にお供えすることで、感謝や願い事を表します。お正月の飾りとして欠かせない存在で、日本の文化や風習を伝える重要なアイテムです。