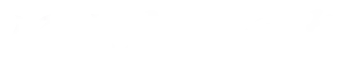【童謡】春を歌おう!楽しい童謡、民謡、わらべ歌曲集
春は暖かく過ごしやすい気候なので、外へ出かける機会も多いではないでしょうか?
桜の美しさやさわやかな春風を感じたとき、懐かしいあの歌、この歌が浮かんだ人も多いかもしれませんね。
こちらの記事では、春にぴったりの童謡や民謡、わらべうたを紹介します。
「懐かしい春の童謡を聴きたい」「春を感じられる歌が知りたい」など、春をめいっぱい感じたい方にオススメです。
懐かしの名曲から、保育園や幼稚園で歌われているお子さんに楽しんでもらえる歌までたっぷりお届けしますね。
- 3月の童謡・民謡・わらべうた。楽しい春の手遊び歌
- 【春の歌】春うた・春の名曲。人気の春ソング
- 【高齢者向け】人気の春の歌。音楽療法にもオススメの童謡と歌謡曲まとめ
- 【子供向け】4月に歌いたい、オススメの童謡やわらべ歌集
- 【春うた】3月に聴きたい仲春の名曲。春ソング
- 【春うた】4月に聴きたい名曲。四月を彩る定番曲
- 昭和初期の春の歌。春を感じる歌謡曲や唱歌まとめ
- 【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ
- 春に聴きたい元気ソング。ポカポカする春うたの名曲
- 【2月の歌】節分や冬にまつわる童謡・民謡・わらべうた・手遊び歌を紹介!
- 小学生におすすめの春ソング。春の名曲、人気曲
- 春うたメドレー。春に聴きたい名曲ベスト
- 5月に親しみたい童謡&手遊び歌!新緑の季節にピッタリな歌
【童謡】春を歌おう!楽しい童謡、民謡、わらべ歌曲集(41〜50)
いちごはいちご作詞:小滝清美 /作曲:藤田大士

明るくリズミカルな楽しいメロディと、心温まる歌詞が魅力的な1曲です。
NHK『おかあさんといっしょ』の1997年5月の今月のうたとして放送され、小滝清美さんが作詞、藤田大士さんが作曲を手掛けました。
主人公がケーキになる夢を追いかけながら、自分らしさを見つけていくストーリーが優しく描かれており、子供たちの想像力を豊かにする歌となっています。
速水けんたろうさんと茂森あゆみさんの歌声で親しまれ、その後も杉田あきひろさんとつのだりょうこさんによって歌い継がれてきました。
アルバム『NHKおかあさんといっしょ メモリアルアルバム』にも収録され、多くの子供たちに愛されています。
お散歩や外遊びの時間に口ずさんだり、春の遠足や楽しいお出かけの際にみんなで歌ったりするのにピッタリです。
家族と一緒に歌えば、春の喜びを分かち合えるすてきな思い出になることでしょう。
空にらくがきかきたいな作詞:山上路夫/作曲:いずみたく

5月の新緑が輝く季節にピッタリな、夢いっぱいの童謡をご紹介します。
山上路夫さんといずみたくさんが手掛けた本作は、子供たちの豊かな想像力を育む楽しい歌です。
大きなリンゴの木やブルドッグ、長い橋など、のびのびとした夢が詰まった歌詞と、軽快で明るいメロディが魅力的です。
アルバム『こどものうた~パクパクいただきます!』や『うきうきワクワク!
こどものうた』に収録されており, 幼稚園や保育園の教材としても使われています。
お散歩中に空を見上げながら歌ったり、友達と一緒に絵を描きながら歌ったりと、春の喜びを感じながら楽めるすてきな1曲です。
てんとうむし作詞:清水あき/作曲:小林つや江

清水あきさんと小林つや江さんが贈る、小さな赤い昆虫を愛らしく歌った童謡です。
明るく軽快なメロディに乗せて、赤い体と黒い斑点が印象的なかわいらしい姿を優しく描写しています。
本作は、アルバム『こどものうた200』や『自然をうたおう!』そして1981年発行の『みんなのうた86曲』に収録されており、多くの子供たちに親しまれてきました。
のどかな春の日差しの中、お散歩をしながら自然と口ずさみたくなる親しみやすい曲調です。
保育園や幼稚園での音楽活動はもちろん、子供たちとご家族で春の自然を楽しむひとときにピッタリな1曲です。
どんないろがすき作詞:阪田修/作曲:乾祐樹

明るくリズミカルなメロディと親しみやすい歌詞で、子供たちの色彩感覚を育める心温まる楽曲です。
坂田おさむさんと神崎ゆう子さんの優しい歌声が、赤や青、黄色、緑といった色の世界へと導いてくれます。
1992年6月にビクターエンタテインメントからリリースされ、NHK『』おかあさんといっしょ』の6月と7月の今月の歌として放送されました。
本作は優しいメロディと色の名前を楽しく学べる要素が詰まっているので、お散歩中や外遊びの時間に、お友達や家族と一緒に歌うのにピッタリです。
新緑が輝く春の季節に、身近な色に興味を持つきっかけとしてもオススメの1曲です。
バスごっこ作詞:香山美子/作曲:湯山昭

大きなバスに乗って出かけるワクワク感をメロディに込めた、香山美子さんと湯山昭さんが贈る元気いっぱいの童謡です。
リズミカルな曲調に乗せて、乗り物遊びを楽しむ子供たちの様子が優しく描かれています。
手や体を動かしながら歌えるので、お子さんも自然と笑顔になれる1曲です。
本作は保育や教育の現場で長く親しまれており、遊び歌としても活用されています。
春の行楽シーズンに向けて、お散歩やお出かけの前に親子で一緒に歌ってみませんか?
みんなでリズムを取りながら楽しめば、子供たちの心にきっとすてきな思い出が刻まれることでしょう。
つくしはつんつん

自然の息吹を感じさせるわらべうたの傑作。
単純な言葉遊びのなかに、植物が芽吹く瞬間の描写が見事に織り込まれていて、まるで春の野山を散策しているような楽しさを味わえます。
音楽としての高い芸術性よりも、気軽に口ずさめる親しみやすさが、長年にわたり愛され続けている理由でしょう。
手遊びとしても親しまれ、保育の現場で幅広く取り入れられています。
日本人の持つ季節感と、自然をいつくしむ心が見事に表現された本作は、子供から大人まで世代を超えて楽しめます。
自然豊かな春の訪れを感じながら、家族や友人と声を合わせて歌ってみませんか?
故郷唱歌

青い山、清らかな水、そして幼い頃に遊んだ思い出。
懐かしい故郷の風景と、離れて暮らす家族や友人への思いを優しく包み込むメロディーは、誰の心にも響く普遍的な魅力を持っています。
1914年に文部省唱歌として発表された本作は、高野辰之さんと岡野貞一さんによって生み出され、当時の日本の農村風景や生活を色濃く反映しています。
1998年の長野オリンピック閉会式で歌われ、多くの人々に感動を与えました。
ト長調の3拍子で紡がれるシンプルで覚えやすい旋律は、卒業式や成人式など人生の節目に歌われ続けています。
郷愁を誘う歌詞とメロディーは、故郷を離れて暮らす全ての人の心に寄り添う、まさに日本の心を象徴する楽曲といえるでしょう。