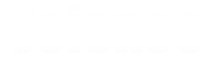小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
夏休みの宿題の中でもとくに手ごわいのが自由研究。
毎年どんな内容に取り組もうか悩んでいる小学生の方は多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、とくに小学5年生にオススメの自由研究アイデアを紹介していきますね。
実際に5年生で習う理科や社会、家庭科の内容にまつわるアイデアを中心にピックアップしています。
一学期に学校で習った内容の中から興味のある分野を選んでもいいですし、教科書を読んで気になった内容に関連するものに取り組むのもオススメ。
それではここからオススメのアイデアを紹介していきますね!
- 【小学校5年生】自由研究テーマ&工作|学びにつながるアイデア集
- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集
- 【小学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】
- 【簡単だけどすごい!】高学年の女子向けの工作アイデア
- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 【夏休みの宿題に!】見たら作りたくなる 小学生向け簡単ですごい工作
- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集
- 高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集
- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集
- 【夏休み工作】女の子向けのおしゃれなアイデア
- 【大人向け】簡単だけどすごい工作。オシャレで見栄えのする作品集
小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】(21〜30)
ペーパーランプシェード

室内を明るく照らすペーパーランプシェードは、温かみのある雰囲気と丸みのあるフォルムが癒やしあを与えてくれるアイテムです。
水を加えたボンド液を風船に塗り、障子紙を貼り合わせていきます。
ライトを入れる部分を残しておき、紙吹雪に使用するコンフェッティと呼ばれる薄い紙やペーパーフラワーなどを貼ります。
洗濯バサミなどでつるして1日〜2日乾燥させましょう。
つまようじなどで風船を割ったら、ライトを内側に入れてランプシェードの完成。
好きな色の素材を選んだり、紙を貼り付ける作業を子供たちが楽しめるオリジナルアイテムです。
固形燃料作り

可燃物を固めることで持ち運びに便利で扱いやすく加工された固形燃料。
ホームセンターやインターネットで購入できる燃料を自作する方法を紹介します。
ナイフでけずった15グラムの石鹸をコップに入れたら、燃料用アルコールを150グラムそそぎます。
固形物を完全に溶かすために、メタノールが沸騰しない程度の温度で湯煎しましょう。
冷めない状態で缶に入れたものを固めたら燃料の完成です。
メタノールは毒性が高いため、口に入れないように注意しましょう。
缶の大きさやかたちによって固まる速度が変わるので、自由研究のテーマとしてさまざまな固形燃料を作ってみるのもオススメですよ。
小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】(31〜40)
手作りクレーンゲーム

お菓子やぬいぐるみ、フィギュアなどを取るクレーンゲームは子供たちから人気を集めていますね。
「この景品はこのアームの動きで取れるかな……」というドキドキが家でも楽しめる装置を自作してみましょう。
段ボールや空き箱を使って本体を作ります。
次に、ストローや割り箸でクレーンアームを作り、糸でつなげて動かせるように工夫しましょう。
景品は、小さなオモチャやお菓子など、好きなものを用意しましょう。
クレーンゲームの仕組みを調べながら作ることで、工作の楽しさに気づくきっかけにもなります。
製作過程だけでなく、完成したゲームで遊んで楽しめる自由研究のアイデアです。
糸かけアート

花びらのような美しい模様が広がる糸かけアート。
本来のものは、板にクギを打ち付けて作る必要がありますが、紙に切り込みを入れてお手軽に挑戦できる方法があります。
円形にカットした厚紙に等間隔で線を引いたら、画用紙を合わせてカット。
切り込んだ部分に番号を書いておくと、順番を間違えずに作業できます。
番号と反対側にある切り込みに向かって順番に糸をかけていき、一周したら糸をカット。
2週目からは糸の色を変えて位置を1つずらして糸をかけます。
この作業を繰り返して糸かけが終わったら、裏側に画用紙を貼り付けて完成です。
リニアモーターカー作り
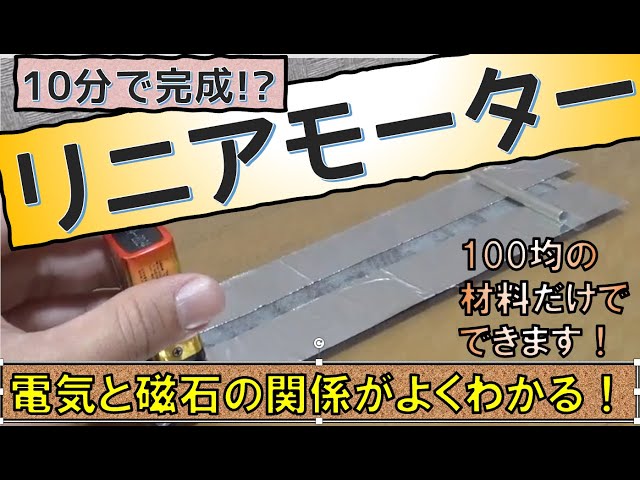
乾電池をつなげて作るリニアモーターカーの作り方を紹介します。
両面テープを貼り付けた下敷きに磁石を2段取り付けましょう。
ここで、反発する磁石の力を抑えて隙間なく貼るのがポイント。
車両部分に使用するメラミンスポンジをカットして、コの字になるようアルミテープを貼り付けます。
磁石を取り付けた下敷きをテープに引っ掛けたら、クリップ線をレールにつなげましょう。
リード戦をアルミテープにはさんで、電池を直列につなげたら準備完了。
理科の実験とおもちゃの製作が同時に楽しめる自由研究のテーマです。
流れる水のはたらきの実験

5年生では浸食作用、運搬作用、堆積作用など、流れる水の働きについても授業で習うと思います。
それらの働きを実験を通して実際に観察してみましょう。
実験方法は、土を集めて作った斜面に水の通路を作りそこに水を流します。
浸食作用、運搬作用、堆積作用が実際にどのように現れるのか、流す水の量でその働きは変わるのか、水の通路が真っすぐの場合とカーブの場合でそれぞれの作用の現れ方が異なるのかなど、さまざまな条件で試してみてその結果をレポートにまとめてみましょう。
メダカの走流性を調べる

魚のたんじょうについても5年生で習う内容ですよね。
そこで、それに関連してメダカの性質である走流性について調べてみましょう。
走流性とは、水の流れに対して一定の運動をする性質のことで、メダカの場合は水の流れに逆らって動くんですよね。
実験方法はメダカが泳いでいる水槽の中を優しく円を描くようにかき混ぜて水流を作り、メダカどのように泳ぐかを観察します。
またこれに関連して、メダカが泳いでいる水槽の周りをしま模様の紙で覆い、それを回すとメダカどのように泳ぐのかも観察すると興味深いレポートが完成するでしょう。