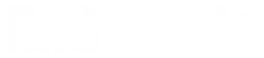【グリーグの名曲、人気曲】ノルウェーの自然を感じられる作品たち
ノルウェーの民族音楽からアイデアを得て、国民楽派の作曲家として注目されたエドヴァルド・グリーグ。
数々の名曲を残し、没後も後世にその名前をとどろかせました。
グリーグの作品は、ノルウェーの自然豊かな風景を連想させる美しい作品が多くあります。
本記事では、そんなグリーグの名曲、人気曲を紹介します。
ピアノ曲や歌曲、管弦楽曲や吹奏楽曲などさまざまなジャンルの作品があるので、クラシックに馴染みがある方もそうでない方も、ぜひ一度彼の作品に触れてみてください!
【グリーグの名曲、人気曲】ノルウェーの自然を感じられる作品たち(61〜70)
ペール・ギュント第1組曲より「オーゼの死」Edvard Grieg

ヘンリック・イプセンの戯曲『ペール・ギュント』のために作曲した劇付随音楽。
この戯曲は、夢想家で大ぼら吹きである主人公のペール・ギュントが世界を旅して、最後に年老いて故郷に戻るまでの波乱万丈の生涯を、ドタバタと描いた物語です。
一度町から出たペールが故郷へ戻ると、母オーゼは死の淵にありました。
オーゼがペールの空想話を聞き、ほほ笑みながら亡くなっていく場面でこの曲が演奏されます。
最愛の母をなくしたペールの深い悲しみが伝わってくるような作品です。
ペール・ギュント第2組曲 より「ソルヴェイグの歌」Edvard Grieg

ノルウェー音楽から影響を受けた、国民楽派の代表的な存在として知られている、ノルウェー出身の作曲家、エドヴァルド・グリーグ。
オーレ・ブルやニルス・ゲーゼを師に持ち、職業的な演奏家にはなりませんでしたが、すさまじいピアノのテクニックを持っていたことで知られています。
そんな彼の代表的な作品の一つが、こちらの『ペール・ギュント第2組曲 より「ソルヴェイグの歌」』。
切なさや美しさはもちろんのこと、冒険をイメージさせるようなミステリアスなメロディーが登場したりと、一つの作品のなかにさまざまなイメージが膨らみます。
ホルベルク組曲 第1曲「前奏曲」Edvard Grieg

ノルウェーが生んだロマン派の天才作曲家エドヴァルド・グリーグ。
1884年、ノルウェーの知識人ルートヴィヒ・ホルベルクの生誕200周年を記念して作曲したのが、この名作です。
本作は、バロック時代の組曲を模した5つの楽章で構成されており、第1曲目はエネルギッシュな前奏曲。
バッハの作品を思わせる高尚な雰囲気にあふれ、キラキラと輝くようなメロディは聴衆の心をつかむこと間違いなしです!
指の基礎練習を重ねながら丁寧に取り組むことで、華やかな世界観を存分に表現できるでしょう。
発表会で堂々と演奏する姿を思い描きながら、練習に励んでみてはいかがですか?
ワルツEdvard Grieg

グリーグの豊かな叙情性が遺憾なく発揮され彼の代表作となった『抒情小曲集』の中の1曲。
曲名にもある通り、ワルツのリズムである3拍子で書かれている曲です。
曲に合わせてワルツが踊れるように、3拍子を意識しながら弾きたいですね。
グリークはノルウェーを代表するピアニスト・作曲家ですが、彼の作品の中にはどこかノスタルジックな民族的性格を持つ物が多くあります。
この曲も、「ワルツ」という社交的なダンスのリズムの中に、民族的なメロディーが絶妙に絡みあっている魅力的な1曲です。
抒情小品集 第10集 Op.71 第3曲「小妖精」Edvard Grieg

エドヴァルド・グリーグが1901年に作曲した『抒情小品集 第10集 Op.71 第3曲「小妖精」』は、幻想的な世界観を持つピアノソロの楽曲です。
この曲は、ノルウェーの風土が生んだ民話や自然の美しさを音に託した作品で、小学校低学年の子供たちにとっても親しみやすい響きをもっています。
取り組む際は、軽やかなタッチで妖精が舞うようなイメージを持ちながら、ペダリングやリズムの正確さに注意して練習することがポイント!
コンクール曲としてこの曲に取り組むことで、音楽の奥深さやピアノ演奏の楽しさを実感できるはずです。